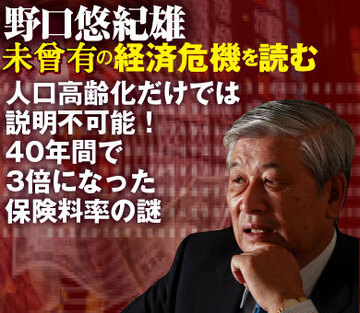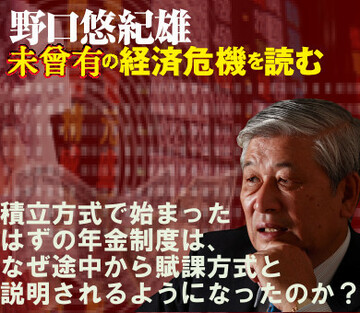いま世界で起きているのは、マクロ経済学の教科書に書いてあるとおりの事態だ。すなわち、有効需要の激減が、経済活動に大きな影響を与えている。
したがって、それがいかなる影響を持つかを、マクロ経済学のモデルで分析できる。income-expenditure model(所得・支出モデル)と呼ばれる最も簡単な形のモデル(利子率や価格の変動を考えないマクロ経済モデル)でも、かなりのことがわかる。
日本の立場から見ると、現在重要な変化は、輸出の落ち込みだ。これを外生的な変化として捉え、消費支出や輸入は所得に比例して変化すると考えて、生産=支出の関係を立てる。これを解けば、「乗数効果」を取り入れた分析ができる(設備投資や住宅投資をどう考えるかも重要だが、とりあえずいくつかの値を想定することでも、かなり意味ある分析ができる)。
もう少し拡張したモデルを考えるなら、開放経済下のマクロモデルである「マンデル=フレミング・モデル」を用いればよい。これは、経済学を勉強した人でも、あまりはっきりと覚えていないかもしれない。「そう言えば国際経済学の講義で聞いたことがある」程度の認識しか持っていない人が多いかと思う。しかし、現下のさまざまな問題に対して、常識では必ずしも得られない答えを与えてくれる。
たとえば、「変動相場制の下で財政支出を拡大しても、円高になって貿易黒字が減少するから、経済拡張効果はない」ということなどがわかる。この点は、現下の経済危機に対する対応を考える際に、大変重要なことだ。仮に10兆円規模の経済対策を考えようが、効果は期待できないわけだ。ましてや、2兆円の定額給付金など、何の効果もないことがわかる。
マクロ経済学が
はじめて意味を持った
これまで、私は、「マクロ経済学はくだらない」と考えていた。マクロ経済理論では、需要の変動が経済活動に影響を与えるというのだが、仮にそうしたことがあったとしても、小さな変動しかありえないだろう。経済活動の基本を決めるのは、供給側の要因であるに違いない。つまり、生産能力、労働者の状況、技術などである。
高度成長期の日本経済を見ていた人なら、誰でもそう考えたことだろう。1930年代のイギリスを対象としたケインズ経済学は、高度成長時代の日本経済の現実とはおよそかかわりのない理論であり、「現実の世の中のことはさておき、ケインズはこう言っている」というだけの話でしかなかった。つまり、経済学説史以外の何物とも思えなかったのである。学生の興味をひきつけられなかったのも、当然のことだ。こんな理論を教室でまじめに教えていたというのが、信じられないことだ。