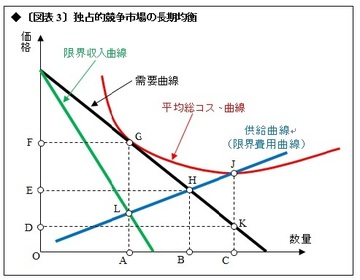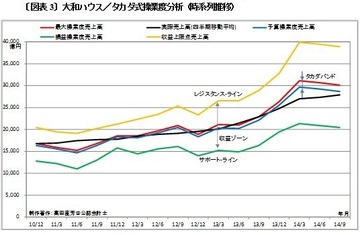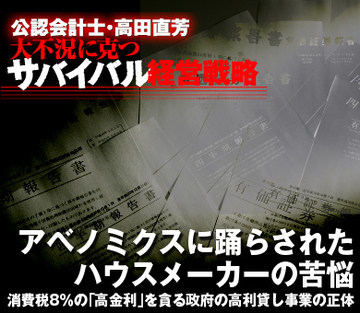前回コラムでは「円高の恐怖」を扱った。この2週間で政府・日銀が為替市場に介入し、米国債の格付け引き下げ問題も加わって、いまや「円高の泥沼化」である。そこで今回は、メディアなどで頻出する「為替レート感応度分析」というものを紹介しよう。輸出型企業であれば「1円の円高」によって「どれくらいの利益が吹き飛ぶか」という物騒な話である。
「当社の取引先は国内ばかりだから、円高など関係ない」というのは大間違い。取引先のさらにその先をたどっていけば販路は海外へと通じ、円高のシワ寄せは巡りめぐって国内の中小零細企業に襲いかかる。それが貿易立国を標榜するニッポンの産業構造である。
為替レートといえば2010年10月に国会で、為替デリバティブを利用した中小企業の窮状が取り上げられた。11年3月に金融庁から「中小企業向け為替デリバティブ取引状況に関する調査の結果について」が公表されたが、その後のフォローを聞かない。東日本大震災で、ドサクサのウヤムヤになっているようだ。
企業が円高対策を何ら講じることなく、円高コストを甘んじて受けているケースは想定しにくい。銀行がその間隙を、為替デリバティブで突いたようなものだ。
生産現場が「銭」単位でコストダウンに取り組んでいるというのに、為替レートが「1円」異なるだけで数千万円の利益が吹き飛ぶ。為替デリバティブに手を出した中小企業にとって、「それは自己責任だ」といわれても、恨み骨髄に入る思いだろう。
為替変動の影響は本当に約3000億円!?
トヨタの営業利益増減分析に首を傾げる
それに懲りて現在では、「ヘッジ取引」というものが多くの企業で採用されている──はずなのだが、トヨタ自動車の決算短信を見ていたとき、「ん~、そうなのか?」と首を傾げる事項があった。次の〔図表 1〕は、その一部抜粋である。「為替変動の影響」と「原価改善の努力」以外の項目を、筆者のほうで「営業努力その他」にまとめている。
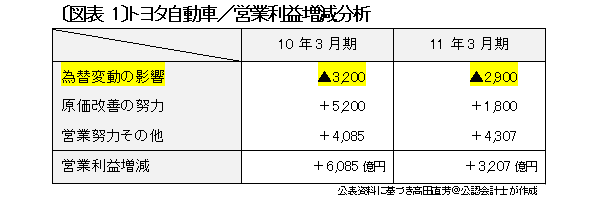
企業会計基準適用指針19号『金融商品の時価等の開示に関する適用指針』3項(3)では、金利や為替などの「変動に対する金融資産及び金融負債の感応度が重要な企業」は、財務諸表への注記が求められている。今後、〔図表 1〕のような注記を行なう企業が増えていくことだろう。
ところで、〔図表 1〕に示した両期の連結損益計算書のほうには「為替差益」683億円と143億円もそれぞれ計上されていた。これらと相殺しても〔図表 1〕で黄色に染めた「為替変動の影響」は、焼け石に水だ。それほどの大きさである。
読者は、〔図表 1〕に計上されている「為替変動の影響」を見て、どのような印象を持たれるだろうか。「さすが、ニッポンを代表するトヨタだけあって、桁違いだ」と感心するのだろうか。
筆者の印象は「トヨタは、これだけ巨額の為替変動を放置するほど無能な企業なのか」である。というよりも、トヨタの「為替変動の影響」が、こんなに巨額であるはずがない、というのが筆者の見解なのである。
そこで今回は、上場企業やメディアなどが利用する「為替レート感応度分析」の真偽を確かめてみよう。