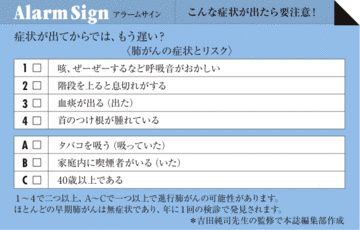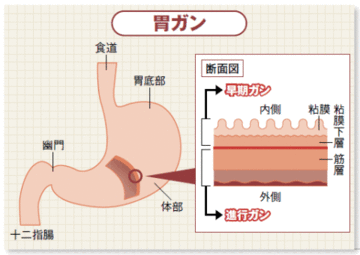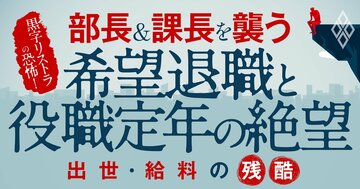いまや、がん治療の主役に躍り出た分子標的薬。力を発揮するには「標的」の絞り込みが鍵を握る。がん特有の遺伝子変異が生み出す分子であること、その働きを封じることでがん細胞に致命的なダメージを与え、正常細胞には影響が少ないことが条件だ。最も成功した例は一部の血液がんに特有の遺伝子変異によるBcr‐Ablタンパクで、これを標的とするイマチニブは慢性骨髄性白血病の治療成績を一変させた。
一方、より複雑に発症因子が絡む固形がん(一般的な臓器がんなど)では、それ一つですべてを決定づける遺伝子変異と標的があるとは考えられず、分子標的薬の限界を噛み締める日々が続いた。しかし2006年、自治医科大学ゲノム機能研究部の間野博行教授(当時)らのグループが世界で初めて、一つの「標的」で固形がん消滅が期待できる変異と分子を発見したのだ(07年、「ネイチャー」誌発表)。
その標的はEML4‐ALK。一部の肺がんに存在する遺伝子変異が生み出すタンパクで非常に強力ながん化能を持つ。実際、人為的にEML4‐ALKを作るように操作されたマウスは、わずか生後数週間で肺がんを発症する。つまり、肺がんの本質的な発症原因であることが証明されたのだ。ヒトのEML4‐ALK陽性肺がんは肺腺がんの約5%に認められ、若年者、女性、非喫煙者に多い。