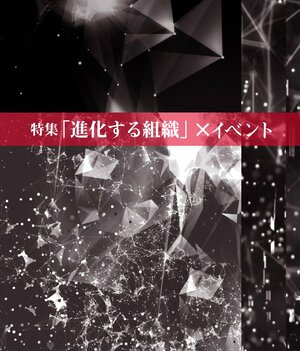「新規事業のメンター」が
メンバーにフィードバック
 島雄輝(しま・ゆうき)
島雄輝(しま・ゆうき)リクルート リクルート経営コンピタンス研究所コンピタンスマネジメント推進部部長。 リクルートに2007年入社。事業開発室のフリーマガジン『R25』編集部に配属。10年、Media Shakersに出向し、『R25』デジタル関連メディアの立ち上げやプロモーションに携わり、『R25』編集長、メディアプロデュース部長、営業部長、事業開発室長などを歴任。17年よりリクルート経営コンピタンス研究所に異動し、ナレッジマネジメントに携わる。20年より現職、リクルート横断のナレッジ共有イベント「FORUM」の責任者に。兼業でインフォグラフィックメディアZUNNYの代表を務める
島 社内で新規事業コンテストを毎年開催し、年間約1000件の応募があり、検討を進める中で淘汰されていきます。その中から数年に一度、あるいは10年に一度、我々の基幹といえるような事業が出てくる。
例えば、一つの事業部で100億円以上稼げたり、従業員を1000人規模で抱えられたりするような事業になったケースがある一方、途中で撤退した事業もたくさんありました。結果として、その事業撤退が人材流出につながったこともあったと思います。
新規事業には、社会の「不」を解決するという目的がありますが、あくまで慈善事業ではなく、きちんとビジネスとして成立させる。そこに対して、何年間でここまで行き着こうと区切る「ステージゲート方式」で、期限と規模をきちんと定めることは、打数の集積の結果だと思います。
長内 それが、島さんの講演にあった「型」の話につながっていくのですか。
島 運営としての型に近いかなと思います。それぞれの新規事業は、マーケットも違えば、我々が得意としてきたマッチングビジネスだけでもない。リクルートはBtoBtoCモデルですが、CtoCのマッチングになると、また全然、性質が違うこともあれば、自分たちのケイパビリティーと同じこともあります。
運営サイドとしては、その型の失敗のラインを決めて、そこから何を学び取るのかをはっきりさせる。そのため、事業開発室に「新規事業のメンター」チームを形成するとともに、情報や人の接続で後押ししているのが我々リクルート経営コンピタンス研究所です。そこで各事業からの兆しをキャッチアップして新規事業メンバーにフィードバックする、アクセラレーターのような役割を社内にも設けています。
長内 なるほど。ありがとうございます。四家さんはいかがですか。
 四家千佳史(しけ・ちかし)
四家千佳史(しけ・ちかし)コマツ執行役員スマートコンストラクション推進本部長 (兼)EARTHBRAIN代表取締役会長。1968年福島県生まれ、97年にBIGRENTAL(本社:福島県郡山市/建設機械レンタル業)を社員3人で創業。2008年、社員数700人までに成長した同社と、コマツレンタル(コマツ100%出資)が経営統合、同時に代表取締役社長に就任。15年1月にコマツ執行役員スマートコンストラクション推進本部長に就任、21年7月にEARTHBRAIN代表取締役会長に就任(兼務)、現在に至る
四家 私もよく、社内外から困難だったことを質問されますが、正直ぱっと思い付かないんですね。
よく考えてみたら、100年間ものづくりをしている会社で、これまでと全然違う新規事業をするときは、全てが困難だと思います。ですから、困難をあまり困難だと思わず、ワクワクしながら取り組んでいました。
長内 ここ20年ほど、日本の新事業や新製品にかつての勢いを感じないところもあると思いますが、皆さんは何が問題だと思いますか?新しいアイデアが出にくくなっているのか、それ以外に何か課題があるのか。
島 リクルートですと、自分たちが考える効率というものが、結果的にマーケット全体をポジティブに回すサイクルになっているのか。それによって、事業を考える範囲がすごく変わってきたと思います。
事業を新しく始めるときも、大企業など大きな顧客の目線で考えると、そのニーズに合わせたものになってしまう。マーケットをどう捉えるかですが、単純な売り上げなら、そちらの方がおそらく大きいでしょう。
ただ、顧客の数を考えたら、中小企業の皆さんのニーズに応えるものも考える必要があります。それによって、機能開発の優先順位や検証すべきことが変わってきます。いずれにせよ、日本の社会環境が年々厳しくなっていますので、今までと同じような成功確率ではいけません。そのために、一般社員のみならず、組織のリーダーもアップデートをだいぶ求められていると感じています。
 宇野大介(うの・だいすけ)
宇野大介(うの・だいすけ)ライオン歯科材事業推進部、ライオン研究開発本部イノベーションラボ所長(2018~22年)。1990年、ライオン入社。歯磨剤の開発、クリニカブランド ブランドマネジャー、オーラルケア製品の生産技術開発を担当。2018年1月、イノベーションラボの立ち上げと同時に所長就任。ライオンが掲げるパーパス「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」に向けた、新規事業の創出をミッションとするイノベーションラボを率いる。23年1月より、ライオン歯科材事業推進部。趣味は、読書、ゲーム、SF、アニメ、ウイスキーなど(23年3月時点)
宇野 母数が減るから、成功しているイノベーティブなものが少ない。そういうことかなと思います。何かの資質が極端に落ちた、というわけではなく、単に打席数が減っているということだと思います。
四家 コマツもそうですが、成熟した企業というのは、社員には本業に集中させ、新しいことに挑戦させないような仕組みになってしまっているのではないか、ということです。
「ダイバーシティー&インクルージョン」と打ち出しながら、やはり新卒で企業に入り、定年まで勤める人が圧倒的に多いし、そういう評価制度、人事制度になっています。別にそこに悪意はないはずですが、実は日本の製造業全体が、新規事業にチャレンジさせずに、本業をしっかりやっていくという仕組みになっているのではないかと感じています。
長内 島さんの講演の中で、「コアコンピタンスのアップデート」というのがありました。
過去の成功体験というのは、すごく強いと思います。ただ、今までのコアコンピタンスが強ければ強いほど、新しいことをしにくくなってしまうと思いますが、そこを抜け出すために必要なヒントというか、カギとは何だと思いますか。