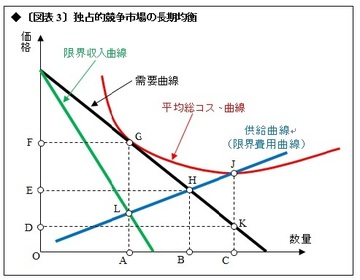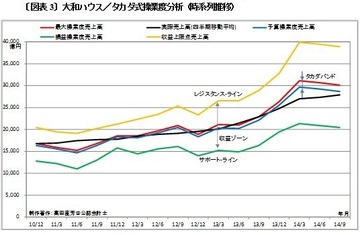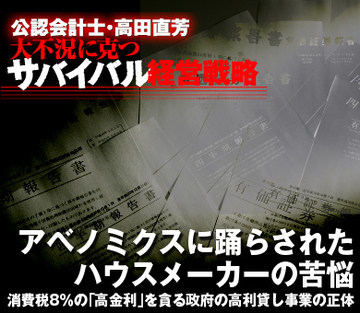第21回コラム(トヨタ&ホンダ&ニッサン編)の冒頭で「鉄は国家なり」という言葉を紹介した。鉄血宰相ビスマルクか、鉄鋼王カーネギーの発言に、太陽王ルイ14世の「朕は国家なり」を捩(もじ)ったものなのだろう。
その「鉄」を国家戦略の基本に据え置いて、経済政策を大々的に展開していった時期が、かつてのニッポンにはあった。第2次世界大戦後、疲弊した経済を復興するために立案・実行された「傾斜生産方式」と呼ばれるものだ。
当時、敗戦国ニッポンで利用できる経営資源(ヒト・モノ・カネ)は限られていた。その資源配分を、アダム・スミス以来の自由放任主義に任せるのではなく、国主導の「計画経済」によって差配し、産業の立て直しを図ろうとしたのである。
具体的には「石炭と鉄鋼」をニッポンの基幹製品と位置づけ、当初はこれらを二本柱とした産業の拡大と充実に努める。次に、電力・造船・自動車など他の産業へ波及するような仕組みを構築する。こうした一貫性のある経済政策が、1960年代の高度経済成長として花開いた。
先ほど「計画経済」という表現を用いたように、この政策はマルクス経済学者(有沢広巳)の立案によるものであり、実行したのは吉田茂内閣である。わが国がときどき「世界で最も成功した社会主義国家」と評されるのは、傾斜生産方式の成功によるところが大きい。現在の鳩山政権が「基本的な国家戦略がない」と酷評されるのとは大違いである。
さて、傾斜生産方式は戦後ニッポンの復興に役立ったが、高度経済成長が進展するにつれて綻(ほころ)びが生じた。二本柱の1つである石炭が、海外からの安価な石油に取って代わられ、石炭業界が斜陽化してしまったからだ。大所高所の経済政策も、意外と短命であった。
もう1本の柱である鉄鋼業界は、現在でも重厚長大産業の中核にあるが、地球温暖化排出ガスのA級戦犯として逆風にさらされる状況にある。ここ数年の原材料高を鉄鋼価格に転嫁できないのも、頭痛の種だ。H形鋼や鋼板などで大幅値上げが予定されているようだが、それによって自動車や家電などの内需を縮小させては、大幅減産というしっぺ返しを受ける恐れもある。
強風と頭痛に悩まされて、国内にある高炉の火のほとんどが消えてしまうのではないか、と懸念されるほど。かつては基幹産業の骨格を構成したコークスも、いまや風前の灯火で燃やされている程度だといえるだろう。
鉄鋼業界が今後、どのように変節するかは産業政策論などに委ねることにして、今回のコラムでは短期的な業界動向を検証していこう。