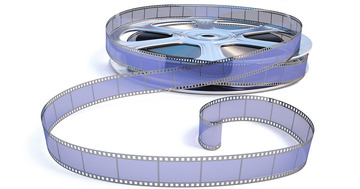東京・新宿の、大型書店。一階にある細長い通路で、足が止まった。
《こんなところに、エレベーターガールがいる》
ワンピースに帽子、手には白い手袋。おきまりの制服で、ホールの前に立っている。三基あるエレベーターのうち一基が到着すると、すかさずその前に歩み寄り、客をさばいている。
人波に押されて乗り込むと、ドアの中にもエレベーターガールがいた。決して広いとは言えない空間で、操作ボタンに張り付くようなかっこうで案内業務をしている。
途中階でさらに客が乗り込んでくると、中は一層、混雑した。その混み具合を見るなり、彼女はくるりと左45度に向き、身を縮めるようにしつつ、壁に向かって案内業務を始めた。
それを見て、5年以上前のある出来事を思い出していた。
取材で知り合った自称フリーターの若い男性に、「彼女たち、どんな気持ちで仕事をしていると思う?」と質問された。
場所は、とある駅ビル。彼が指さす先には、制服姿のエレベーターガールがぽつんと立っていた。
「毎日、上ったり、下りたりでつまらない」
目に映ったままを、答えたつもりだった。だが、彼は《何もわかっていないなあ》という表情で、「それは違う」と否定した。
「毎日、お客さんと接することができて楽しい。彼女たちはきっと、そう思ってるんじゃないかな」
「儲からなくても幸せ」ではいられない?
“過剰サービス”と追い詰められた彼女たち
エレベーターガールは日々、どんな思いでシゴトをしているのか。当人たちに取材を申し込もうと、改めて書店の代表番号に電話をかける。
「エレベーターガールのことなら、ビルのメンテナンス会社に聞いて下さい」