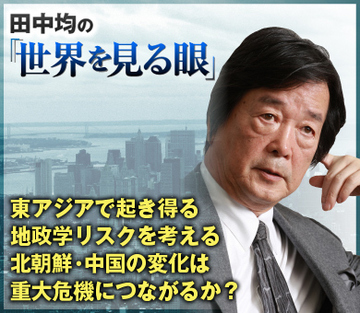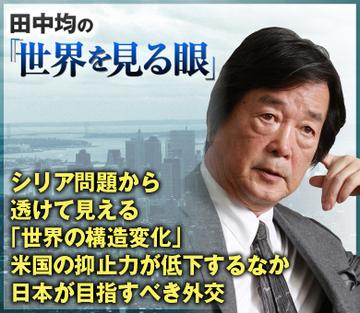「脅えるアメリカ社会」ではボストンマラソン爆弾事件を中心に据え、様々な角度からテロ事件の余波やアメリカ社会に存在する恐怖心を紹介してきた。本連載は今回で最終回となるが、取材期間も含めた連載中に感じた疑問について、テロリズムの歴史や各国の対テロ政策にも詳しい明治大学政治経済学部のリュボミール・トパロフ特任講師に聞いた。ブルガリア出身のトパロフ氏はボストンのノースイースタン大学で国際政治やテロリズムについて教鞭をとり、2010年より日本を拠点としている。
テロリズムは政治暴力の一つ
かつては支持された手法だった
 リュボーミル・トパロフ (Liubomir Topaloff)
リュボーミル・トパロフ (Liubomir Topaloff)1973年ブルガリア・ソフィア生まれ。父は著名な作家で現バチカン大使。ソフィア大学を卒業後、アメリカにわたり、シカゴ大学で修士を、ノースイースタン大学で博士号を取得(専門は世界の安全保障問題)。2005年から2010年までノースイースタン大学で講師として勤務し、2010年夏に来日。現在は明治大学政治経済学部で特任講師を務める傍ら、アジアの安全保障問題についてもブルガリアのメディアに寄稿している。
――ボストンマラソン爆弾事件のようなテロと、冷戦時代に世界各地で発生したテロでは、何か違いはあるのでしょうか? 時とともにテロリズムの定義は変わっていくのでしょうか?
私の見解としては、テロリズムとは暴力的な手段を用いて社会に不安を与えることで、市民の国家や社会に対する怒りや不満を誘発させる行動だ。意外なことに19世紀末まではテロリストに対する社会的な支持が強い国もいくつか存在し、テロリストも自らをテロリストと呼ぶことに誇りを持っていたほどだ。
帝政ロシアのアナーキストも自らをテロリストと呼び活動したが、帝政に不満を抱く一般市民からの支持率はかなり高かった。現在では考えられないが、テロリストがポジティブなニュアンスを持たれる時代が存在したのだ。彼らはテロそのものが当時の政治体制を転覆させるとは考えていなかったが、当時の政府が市民に対する締め付けを強化せざるを得ないような状況を作り出し、それによって民衆による革命が始まると考えていた。