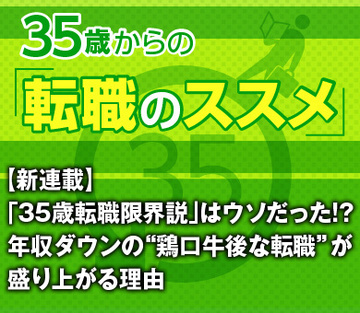世界同時金融危機からユーロ危機に至る最近のマクロ経済の重要なトピックに、激変する金融業界の“赤裸々な内幕”を織り交ぜて解説する『外資系金融の終わり』が発売直後から大きな反響を呼んでいる。本連載ではそのメインテーマともいえる外資系金融機関の「報酬」と「組織」、そして金融システムの変化について、藤沢数希氏に解説してもらう。
外資系金融機関の給与水準
僕が最初に書いた本『なぜ投資のプロはサルに負けるのか?』(ダイヤモンド社)のなかで、貧乏な研究者だった僕の給料が2年目で大学教授の給料を軽く超えた、と書いたのだが、じつは3年目で僕の給料は日本の多くの上場企業の社長の給料を超えていた。そんな外資系金融機関の給与水準というものがどういうものだったのか、ここでくわしく説明しよう。
人によってぜんぜん違うのだけれど、フロントオフィスに採用された新人の年収は、1年目はだいたい600万円~800万円のベースと、ボーナスが100万円~300万円ぐらい。2年目で、700万円~1200万円ぐらいのベースと、ボーナスが300万円~1500万円ぐらい。3年目ぐらいで大きく差がつくのだが、これぐらいの経験年数でヘッドハントされて他社に移籍すると、ベース1500万円以上で、ボーナスが1000万円~3000万円ぐらいになっている。外資系では基本給のことをベースサラリーといい、これを12で割った金額が月給として支払われる。これに年1回のボーナスというのが基本的に外資系の給与のしくみである。
つまり、運が良ければ新卒で年収1000万円超えるし、新卒から3年目でJリーガーよりも給料がかなり上で、一軍のプロ野球選手よりもちょっと下ぐらいになっているのだ。日本の上場企業の社長の年収は平均すると3000万円ぐらいなので、入社3年目で上場企業の社長よりも給料が高くなっていたりする。
しかし、新卒から伸び悩む人もいて、アシスタント的な仕事を長時間やらされ続け、トータル年収1200万円ぐらいで足踏みしている出来の悪い人もたくさんいたし、実力がないのにクソみたいな雑用を奴隷のようにこなさない反抗的な人は、だいたい会社を辞めさせられていた。
2006年や2007年のバブルのピーク時には、アメリカの名門大学のファイナンス学科で博士号を取った学生には、初年度から2000万円ぐらいの年俸を提示していた。インターンとして僕のデスクに来ていた中国人の青年は、カリフォルニアのバークレーで金融工学の博士号を取っていた。彼は、他の投資銀行からクオンツとして初年度2000万円のオファーを提示されていて、僕はちょっと驚いた。さすがに実務経験がゼロの新卒に2000万円のオファーというのは、なかなかすごいと思った。彼はどうしてもトレーダーになりたいらしく、クオンツのオファーを保険にして、他の投資銀行からトレーダーのオファーを得ようと就職活動を続けていて、僕たちのデスクに来ていたのだ。