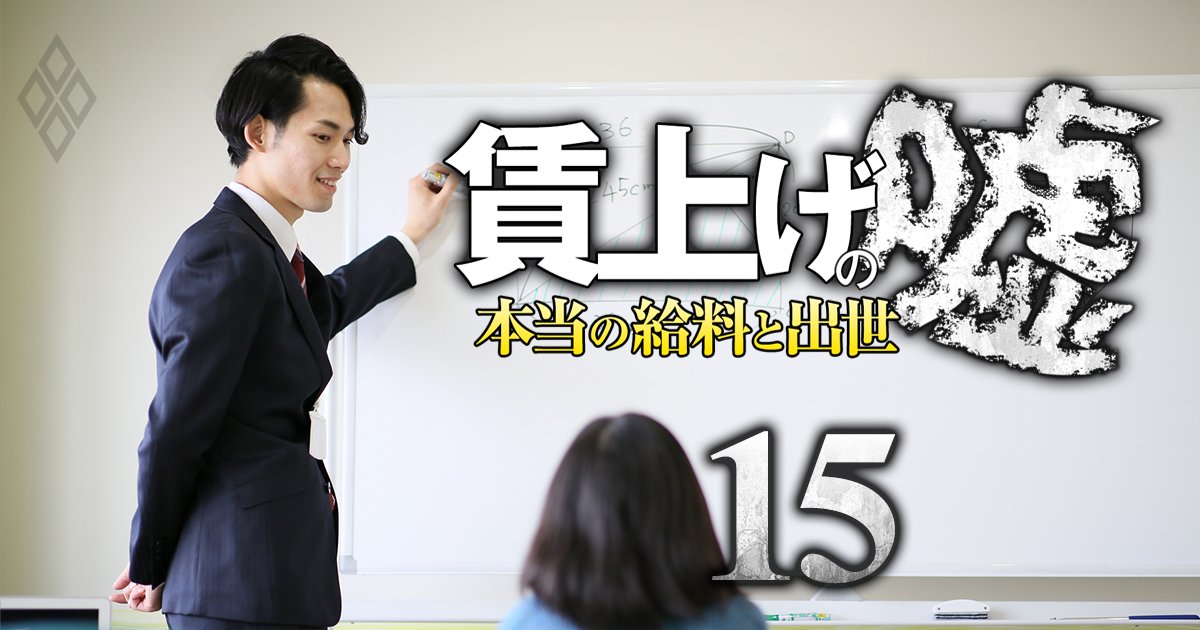賃金予想が改善しない2つの背景
ベアなしの認識から飛べる機運が必要
もちろん今後、日銀のシナリオに沿って春闘の賃上げ分の転嫁が進み、サービス価格の上昇が加速する可能性はある。
鍵を握るのは、賃上げ分のサービス価格への転嫁を消費者が許容するか否かだ。そのハードルを越えることができれば、企業は来年度以降の賃上げにさらに前向きに臨めるようになり、それが消費者の購買力を高め、好循環に入っていける。
筆者の研究室が春闘の一次回答後(3月19日から22日)に実施したアンケート調査によれば、「自分の賃金は先行き変わらない」との回答が65%と過半を占めており、賃金予想の改善ははかばかしくない。
背景には、そもそも賃上げの恩恵を十分に受けていない人が少なくないという事実がある。そこで、賃上げが十分ではない層への所得補填(ほてん)を行う必要がある。政府は昨年11月に決定した経済対策で消費者の可処分所得を底上げすることを決めており、6月には所得税減税が予定されている。今後も、好循環を定着させるための所得補填を躊躇(ちゅうちょ)すべきではない。
賃金予想が改善しないもう一つの背景としては、2年連続の賃上げの恩恵を受けつつも、その持続性に今なお自信を持てていない人が少なくないという事実がある。ベアなしの認識からいまだ“飛べずにいる”のだ。
22年春に始まった好循環は2周目を終え、3周目に入ろうとしている。2年前には筆者を含め誰も想像できなかった、新しい世界が開けたのは確かだ。
しかしこの先も安泰かといえば、決してそうではない。高い賃上げが今後も続くというナラティブ(物語)をいかにして社会全体に浸透させるかが、好循環の成否を決める。