財政・税制 サブカテゴリ
日本銀行の追加利上げは、高賃上げや設備投資増など内需の堅調に加え、円安による物価上昇回避で高市政権とのあつれきが生まれなかったなどの好環境が追い風になった。ただし、2026年以降の「緩やかな利上げの継続」には、日銀の言う基調的物価上昇率や中立金利について市場などに説得力のある説明をする必要がある。

日本銀行は10月の金融政策決定会合で政策金利据え置きを決めたが、植田総裁の発言からは12月あるいは来年1月会合で利上げを決める可能性が高い。高市政権との関係も円安やインフレ加速が困る点では一体であり、追加利上げで政府と日銀が衝突する事態はないと考えられる。

合法的に相続税を払わず子孫に資産を残そうと、富裕層は次々とタックスヘイブンへ渡り、慣れない生活に苦労しながらその時を待つ。一方で国税も切り札を懐に忍ばせ、時機をうかがう。

第121回
26日水曜、NHKが「自民党税調、ビール系税率一本化を見送り」と報じた。「ビールではない、ビールみたいな飲料」で競争する日本の業界は、世界で類を見ない「歪んだ市場」とされてきており、ビール税制の正常化は今年の税制改正の目玉のひとつだった。

第120回
人工知能(AI)の発達で仕事を奪われる中間層が続出するという予測を、政府やシンクタンクが公に発表するようになってきた。欧州では、ベーシックインカム(BI)によってそうした人々の生活を保証しようという議論もある。果たしてその議論は現実的か。

第27回
公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2015年度の運用実績が5.3兆円の赤字になったと発表した。この赤字が巨額だということで「問題だ」と声高に叫ぶ政治家も出てきたが、実際の問題はそこにあるのではない。
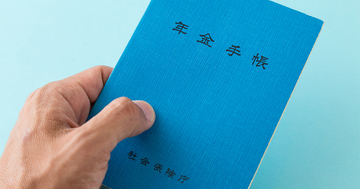
第119回
英国のブレグジット(EU離脱)は、税制に大きな影響を及ぼすだろう。英国とEUとの取引が「域外」取引になるので、ヒト・モノ・カネ・サービスの自由な移動を裏付けていた様々な税制上の特権を、一気に失うことになる。日本企業への影響も大きいだろう。

第114回
財政の尻を日銀が面倒見る「財政ファイナンス」が刻一刻と深まっている。そして「ヘリコプターマネー」が取り沙汰されるようになった。空からカネを撒くような、究極の不健全財政。亡国のリスクを孕む奇策が、日本で社会実験される可能性が膨らむ。

第111回
かつて「権力の守護神」と呼ばれていた財務省だが、今やその威光はない。消費増税先送りの次は、「2020年度プライマリーバランス黒字化」の看板を下ろすことになるだろう。財務官僚に無力感が広がり、「破局願望」さえ漂うようになった。

第116回
安倍政権による消費増税延期は、大きな波紋を広げた。国民全員に負担増を求める消費税は、これまで多くの政権の基盤を揺るがせてきた。しかしこのままでは、日本の社会保障の充実も財政再建も図れない。増税延期から見えてきた課題を4点にまとめてみた。

第114回
パナマ文書問題で浮き彫りになったことは、脱税の問題とは別に米系多国籍企業を中心とする「租税回避」の問題である。アグレッシブな租税回避は、企業倫理に関する問題だけに、日本型コーポレートガバナンスの成熟度が試されていると言える。

第113回
5月10日に公表が予定されているパナマ文書に関して、マスコミの報道が日に日に大きくなっている。先週ワシントンDCで開催されたG20会合の声明文を解読しながら、個人課税を念頭において、パナマ文書問題に関わる3つの論点について述べてみたい。

第107回
「パナマ文書」が世界を震撼させている。先進国はどこも財政難で、真っ先にすべきは税金を払うべき企業や個人が、合法的に逃げる「租税回避」の解消のはずだ。ところが対策は遅々として進まない。それはなぜか。

第106回
首相は「消費増税先送り」へと動き始めたが、日銀の見立ては「景気は緩やかに回復中」だったはずで、ならば消費税見送りという結論にはならない。後世、黒田氏は「中央銀行の規律を崩壊させた総裁」と言われるのではないか。

第110回
2017年4月から予定されている消費税10%への引き上げの先送り論が、官邸周辺から出てきている。それが現実となれば、アベノミクスは行き詰まるだろう。適切な分配政策による成長を実現するため、本当にやるべきは所得税改革だ。

第104回
G20では財政を含めた可能な限りの政策が必要とされたが、具体策は各国の宿題になった。財政出動を求める声が噴き出すことは必至で財務省は頭を抱える一方、首相官邸はほくそ笑んでいるという。

第108回
2014年に最も注目された税務訴訟に、ヤフーとIBMの「租税回避行為」に関するものがある。「損失」を利用することで、自らの税負担を軽減する取引だ。2社の訴訟を通じ、国際標準から大きく遅れた日本の租税回避議論を検証する。

第102回
金融政策が、更なる異次元に踏み込んだ。とうとうマイナス金利。提案した黒田総裁ら正副総裁の3票を除くと審議委員の投票は3対5で反対が多かった。「効かない」「危ない」という疑念が示されたのだろう。

第107回
予算委員会で、軽減税率導入にまつわる議論がこれから本格化する。国民の軽減税率に対する支持率も、次第に落ちてきている。軽減税率導入によって空く「1兆円」の大穴をどう考えるべきか、政府の国会答弁の論拠はあまりにも怪しい。

第105回
2017年4月の消費税率10%引上げに向け、軽減税率の導入が決まった。 驚くことに、「新聞」にまで軽減税率の適用が決まったのだ。これで、軽減税率の旗振り役だった読売をはじめとする新聞社は、安倍政権に大きな借りをつくった。
