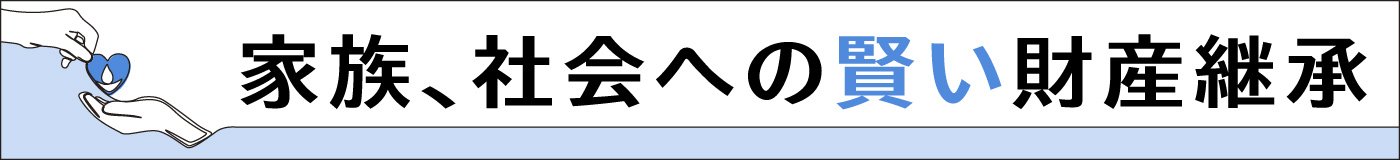長野:若い頃、私は自分のことに精いっぱいだったと思います。自分にできることを模索する中で、テレビ局の女性アナウンサーとして働く道を選びました。そこからキャリアを重ね、本当にやりたいキャスター・ジャーナリストを目指し、アメリカでは「メディア環境学」を学びました。
社会貢献を考え始めたのは40代になってからです。キャスターになる夢をかなえ、母を支えられるようになり、いろいろな環境が整ったときにアフガニスタンやパレスチナなどの難民キャンプを取材する機会があり、そこからようやく考え始めたという感じです。
茂木:すてきなお話ですね。僕自身、脳科学に携わる中で、「利他性」という在り方についてよく考えています。人が子どもから大人になっていく過程とは、受け取る側から与える側へ、支えてもらう側から支える側へと変わっていくことだと思うのです。この前提で言えば、子どもの成長において何より大切なのは「安全基地」(精神的に守られ、安心できる場所)です。それが親である場合もあれば、地域や社会全体である場合もあります。大人になるというのは、誰かにとっての「安全基地」になっていくこと――僕の人生も、そうだったと感じています。
 茂木健一郎氏(脳科学者)
茂木健一郎氏(脳科学者)もぎ・けんいちろう◉1962年生まれ。理学博士。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。屋久島おおぞら高校校長。専門は脳科学、認知科学。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして、脳と心の関係を探求している。
「安全基地」を世界規模で考えなければならない時代
長野:ひと昔前は「社会で子どもを育てる」という言葉がありました。今は、社会に余裕がない……。いえ、昔だって社会に余裕があったわけではないと思うのですが、昔と今を比べると、私たちを取り巻く情報量に差があり過ぎて、脳が処理できるキャパシティーを超えているように感じます。そのため余裕がないというか、それこそ利他的に生きることが昔よりは難しくなってきましたよね。隣近所や町内という狭い社会の中で生きている頃は、近所の子どもたちはコミュニティーで育てようという気持ちを持てましたが、それが難しくなっていると感じます。
茂木:長野さんのおっしゃること、すごく共感します。日本という国が比較的良い環境を保っているのは、一人一人の努力の積み重ねだと感じています。海外の人たちが憧れを持ってくれるのも、やはりそこに何か温かいものがあるからでしょう。
でも、その豊かさは、他国からのエネルギーや食料に支えられている面がある。だからこそ、僕らも「日本らしい貢献」って何だろうと考えていく必要があると思うんです。
今の世界は、経済も安全保障も環境問題も、全てが国を越えて密接につながっています。どこかで起きた出来事が、僕たちの日常に直結することもある。
それは「安全基地」を世界規模で考えなければならない時代になっているということなのでしょう。
ただ残念ながら、各国が独自のエゴで動くようになっている今の国際情勢では、紛争により住み慣れた場所を追われたdisplaced people、難民の人たちがさらに増えていく可能性が高いでしょう。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が難民の保護や支援に取り組むというミッションは、ますます重要になっていかざるを得ないと思います。
長野:日本って災害が多いですよね。例えば東日本大震災では、多くの人が被災地にボランティアに行ったり各地で募金活動を行ったりしました。これはすごいことだと思います。ですから日本は他人を助ける意識が遅れているという感じは全くないのですが、島国のため、他の国と国境を陸地で接していない分、難民の実情を知らなかったり関心が届かなかったりするのかなと感じることはありますね。
 長野智子氏(キャスター・ジャーナリスト・国連UNHCR協会理事)
長野智子氏(キャスター・ジャーナリスト・国連UNHCR協会理事)ながの・ともこ◉1985年フジテレビアナウンス部に入社。夫の米国赴任に伴い渡米。ニューヨーク大学大学院で「メディア環境学」を専攻。2000年4月より「ザ・スクープ」(テレビ朝日系)のキャスターとなる。24年より、国連UNHCR協会理事。
遺言を書いて前向きな気持ちになった
茂木:長野さんは、国連UNHCR協会の理事をされているのですね。
長野:2019年から報道ディレクターとして、UNHCRの難民支援の最前線の現実を伝える役割を担ってきました。シリアの難民キャンプでは、子どもたちが支援物資のコンピューターを使って勉強する施設ができていました。子どもたちは「日本からの支援でこういう勉強ができるので、いつか脚本家になって日本で映画を撮るのが夢」と話してくれて、それを聞いてとてもうれしく思いました。難民支援は今の生活を助けるだけでなく、子どもたちの未来を助けることができるということを実感しました。
茂木:支援と切り離せないのがお金ですが、僕は物を欲しいとは思わないから、生きたお金の使い方をずっと考えてきました。ようやくそれは、人との関係に使うことだと思うようになりました。そこで人と人をつなぐ場をつくるために使ったり国連UNHCR協会のチャリティ・アンバサダーとして東京マラソンに参加し出走したりしています。いわゆるぜいたくをするというより、人のために使った方が深い満足感が得られるということに気付いたのです。
長野:私たちの年齢になると何となく分かってきます。私は2年前に事故で大けがをしました。入院しているときに「もう明日死ぬかもしれない」と思い、遺言書を書きました。私の財産は家族や家族の一員である猫にも残しますが、遺贈寄付(遺言によって財産を特定の団体などに寄付する仕組み)という方法でUNHCRを通じて難民支援もするつもりです。
茂木:遺言書を書いて変わったことはありましたか?
長野:遺言書を書くことは自分の人生を深く振り返ることにつながると気が付きました。エンディングノートのようなものでもいいと思うのですが、書くことは、自分の意思を文字にすること。自分自身の今を整理できるのです。前向きな気持ちにもなれますよ。
茂木:今日のお話で、自分の人生の終わり方を考えることは「未来をどう支えるか」を考えることでもあると気付かされました。僕はなるべく元気に働いて、自分にできる支援の形をしっかり考えていきたいと思います。
特定非営利活動法人 国連UNHCR協会
〒107-0062 東京都港区南青山6‐10‐11
TEL:0120-972-189(通話料無料/平日10~19時)
《遺贈に関する資料請求はこちら》
https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/legacy