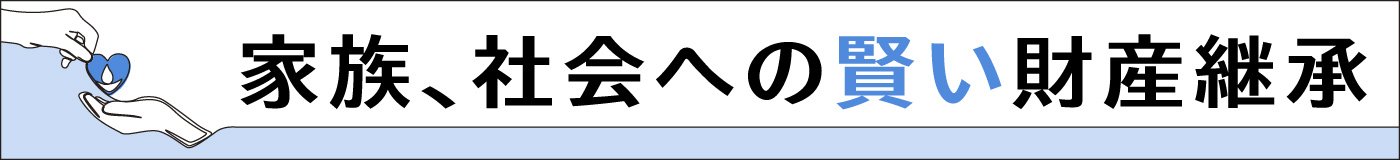日本は寄付文化が根付いていないといわれるが、それでも給料の一部、年金の一部というように、身の丈に合った寄付を続けている人も少なくない。
相続や寄付に詳しい税理士・髙山亜由美氏は、「財産がたくさんある人が、社会貢献のための寄付をしているという話はよく聞きます。また、生活を少し切り詰めても、困っている人を助けたいとの思いから、毎月少しずつ寄付するというような方もいます。どちらもその気持ちは素晴らしいし、寄付という行為によってご自身の心の平安を得ているのかもしれません」と語る。
ただ、こうした寄付は多くの場合、生前に限られた行為であり、自身が最期を迎えるとともに、その志も途絶えてしまうことが多い。その思いを次の世代へとつなげる手段として注目されているのが「遺贈」である。
「遺贈」は「相続」や「贈与」とは違い、聞き慣れない用語ではないだろうか。まずは「相続」「贈与」「遺贈」の違いを正しく理解することが大切だと髙山氏は語る。
「『相続』とは、亡くなった人の財産が相続人に継承されること。『贈与』は任意で行う財産の無償移転、『遺贈』は、故人の残した遺言にのっとって、その遺産の一部、あるいは全てを譲ることを指します」
この遺贈の中でも、公益団体に限定した遺贈を「遺贈寄付」と呼ぶ。「子や孫に財産を遺すことはもちろんしたい。しかし自分が長年関心を持ってきた、例えば、難民救済などの人道支援、子どもへの教育や環境保全活動などにも役立てたい――」。自分が大事にしてきた価値観や思いを公益団体を通じて形にするのが遺贈寄付だ。
実現の鍵は「遺言書」と「準備」
遺贈(遺贈寄付)を実現するためには遺言書の作成が不可欠だ。
遺言書の形式には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がある。自筆証書遺言は、遺言者が、原則自分で全文を書く(自書する)形式。遺言の内容が曖昧だったり不正確だったりすると、相続人同士の争いに発展しかねないが、自宅保管か法務局へ預けるかを選択できる。法務局に預けると、死後に、指定した人へ通知されるため、遺言書の存在を知らずに手続きが始まってしまう事態を防ぐことができる。
一方、公正証書遺言は公証人が作成するため法的な信頼性は高いが、公証役場には相続人等への通知制度がないため、遺言書の存在に誰も気付かないというケースがある。こうした事情から髙山氏は、「公正証書で内容の正確性を確保しつつ、自筆遺言を法務局に預けて通知性を高める、という併用で対処をするケースもあります」と語る。
遺贈(遺贈寄付)を実現するには、遺言書を作成した後、定期的な見直しも欠かせない。「理想は年1回、少なくとも数年に1度は見直すことをお勧めします」(髙山氏)。
財産や家族構成、家族との関係、寄付先の状況などは時とともに変化する。遺言は、“状況の変化に合わせ柔軟に変更すべきもの”と考えることが賢明だ。
財産は、単なる「お金」ではない。それは人生をかけて築いたもの。ただ「遺す」のではなく、自らの理念や思いを社会へ「託す」遺贈(遺贈寄付)を、選択肢の一つに入れておきたい。