成長が見込まれる航空機産業市場
わが国の航空機産業が全産業に占める割合は、先進国のなかでも非常に小さく、08年度の機械工業生産額で見ると自動車産業の6%、全体の約1・4%にすぎない。一方、世界の旅客輸送量は、10年~29年の20年間に年平均5・0%の増加が予測され、この需要の伸びを背景に、同期間のジェット機の運航機数は現在の2・1倍の約3万5700機となり、新規需要機数は約2万9100機になることが予測されている(「平成21年度 民間輸送機に関する調査研究」日本航空機開発協会)。
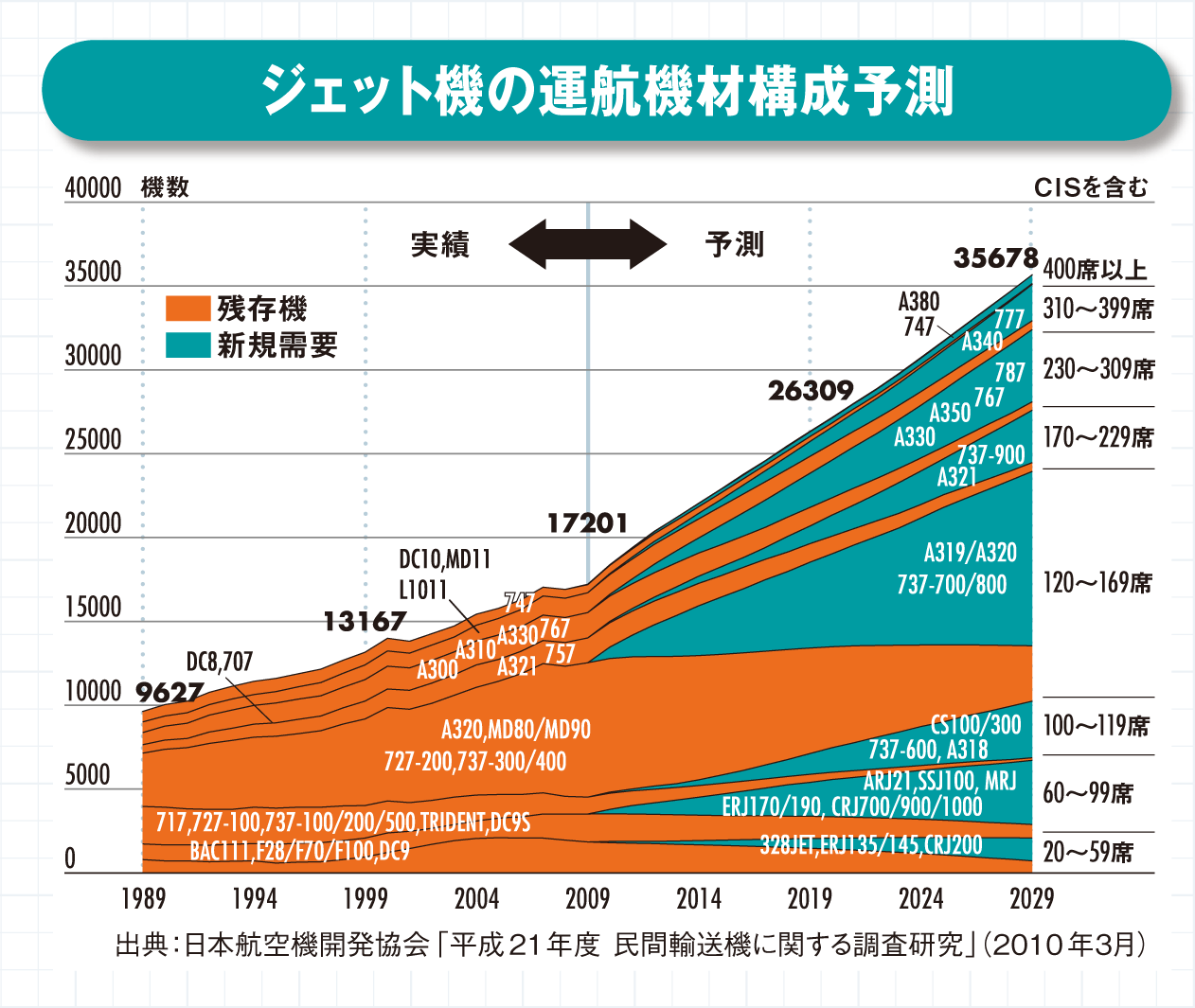
航空機産業は部品調達のグローバル化が進展し、多くの日本企業が欧州エアバス社のA380や、米ボーイング社のB787などにおいて製造分担をしており、B787の機体製造では約35%を日本企業が占めている。今後、B787が増産体制に入るほか、純国産プロジェクトである三菱重工業の三菱リージョナルジェット(MRJ)が12年から、ビジネス機分野のホンダ・ジェットもこれから本格生産に入ることから、部品生産発注が大幅に増えることが予想される。
航空機は、約300万点もの部品から成り立ち、広いすそ野産業が関連産業として存在する一方、徹底した国際認証制度の下で高度な品質管理と安定供給の保証が求められるため、現状は重工系メーカーの下に下請け企業が連なるピラミッド型の産業構造となっており、新規の参入は難しい。しかし、今後、次世代の基幹産業となることも期待されることから、国内各地域では、航空機産業への参入に向けた取り組みが始まっている。
アジア拠点化に向け立地競争力の向上を
わが国の立地競争力について、経済産業省が日本未進出企業を中心に調査したところ、2年前の調査に比べ、アジアの中核拠点としての競争力を失っていることがわかった。特に、従来は競争力を有していた「アジア地域統括拠点」や「R&D拠点」でも首位から転落するなど、アジアでの地位が低下している。
この大きな要因の一つがビジネスインフラの問題だ。たとえば実効法人税率をOECDは約26%に、アジア諸国は約25%に引き下げているのに対し、日本では約41%で高止まりしている。世界の空港における空港貨物取引量や、主要港湾の取扱コンテナ数などの国際競争力も大きく低下している。
諸外国では、特定産業や機能などにターゲットを絞った産業政策・企業誘致を積極的に展開しており、日本に立地する企業が本社機能や開発拠点を海外に移転する動きも見られる。
立地競争力を高めるためには、海外からの投資を戦略的かつ重点的に呼び込み、高付加価値機能の集積を図る「日本のアジア拠点化」が必要である。さらに、実効法人税率の見直しや高度人材の育成・呼び込み、輸送・物流関連の制度改善とインフラ強化、租税条約ネットワークの拡充などの「制度改革」によって、事業環境の魅力を向上させる取り組みが、早急に必要となっている。
今後の企業立地においては、新たな産業の胎動に着目するとともに、グローバルな視点を持った立地戦略に転換し、競争力のある事業環境を整備していくことが重要になる。
※「週刊ダイヤモンド」9月18日号も併せてご参照ください。
※この特集の情報は2010年9月13日現在のものです。