省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が1974年に施行されたきっかけは、オイルショックだった。当時はエネルギー安全保障の意味合いが強かったのだが、それから30余年、地球環境問題への危機意識の高まりに伴い、省エネ=CO2排出削減という面が評価されるようになってきた。今春施行となった改正省エネ法は、低炭素社会実現に向け、いよいよ「企業への規制」色を濃くしている。さらには、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)の縛りもある。企業はこの事態を、どう乗り越えていくべきか。また、新エネルギーや省エネルギーの〝技〟をいかに使うべきか。今回は電力の話題を中心に、住環境計画研究所の中上英俊所長に聞いた。
改正省エネ法で
エネルギー消費調査を
改正省エネ法では、エネルギー管理を行うべき対象が、工場・事業場から企業単位となり、コンビニエンスストアなどフランチャイズチェーンも同様に本部がエネルギー管理を行うことが義務づけられた。すでに特定事業者(または特定連鎖化事業者)はエネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を選任、11月には同法改正後初の定期報告書、中長期計画書の提出期限がやって来る。
「今まで手つかずだった企業のエネルギー消費の詳細が、企業のトップまで情報として上がり、それをフィードバックして現場の社員一人ひとりまで戻せるようになりました。これは画期的なことです。なにしろ日本にはこれまで国全体のエネルギー消費の実態調査のデータすらなかったのですから」と、住環境計画研究所・中上英俊所長は語る。
国勢調査のようにエネルギーの「使われ方」を調べる実態調査は、米国などでは行われているものの、日本は未着手だ。「京都議定書で定められたマイナス6%」「鳩山前首相が国連で表明したマイナス25%」などの数値も、じつは元になるCO2排出量を誰かが測っているわけではない。これは、考えてみると驚くべきことである。
「今まではこうなるはずだ、こうすべきだで、話が進んできました。でももう、京都議定書の約束期間に入り、実績としての減った成果が問われています。データを洗い出し、さまざまな施策がどう効果を上げているかを、評価しなくてはならないのです」(中上所長)
最先端の研究に期待
同時に現実も直視する
環境対策に「効果」とその「検証」が求められるようになった現在。たとえばスマートグリッド(次世代送電網)の研究に期待が集まるようになってきた。電気の流れを需要と供給の双方向からとらえ、発電から電力消費段階までを通信網で結んで自動的に需給調整できるシステムを組むわけだから、流れを明確に捕捉しやすい。そこに昨秋開始した太陽光発電など、再生可能エネルギーの余剰電力全量買取制度などを絡めると、より大きな省CO2効果が期待できる。
「ただ、最先端の研究や施策に期待するのはいいが、現実に目を向けることのほうがもっと重要であることを知ってほしいと思います。一般の消費者が生活し、企業がビジネス活動を続けるなかに、省エネや省CO2を組み込める仕組みこそが必要なのです」(中上所長)
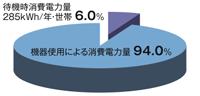 家庭の消費電力量(4,734kWh/年・世帯)に占める待機時消費電力量の割合
家庭の消費電力量(4,734kWh/年・世帯)に占める待機時消費電力量の割合
現実には、最も省エネ・省CO2に効果を発揮するのは、今回の改正省エネ法のような規制だといわれている。次いで、「わが社は環境経営で行く」といった企業トップの決断。さらに一般消費者の行動に火をつけることができたら、国全体の省エネ・省CO2は格段に進む。
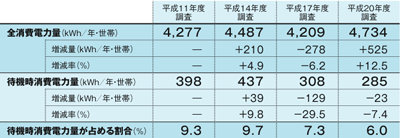 家庭における全消費電力量と待機時消費電力量の推移 住環境計画研究所が待機時消費電力調査を最初に行ったのは1995年。家電のスイッチを切っても、プラグが差し込まれているだけで電力消費が発生しており、そうした待機時消費電力は、家庭における電力消費全体の約1割を占めていることが明らかにされた。これに対し家電メーカーなどが各社、待機時消費電力削減目標を掲げて改善を推進、ビデオデッキやテレビ放送チューナーを中心に改善が進み、現在は、待機時消費電力は電力消費全体の6.0%にまで縮小している。出所:(財)省エネルギーセンター「平成20年度待機時消費電力調査報告書」
家庭における全消費電力量と待機時消費電力量の推移 住環境計画研究所が待機時消費電力調査を最初に行ったのは1995年。家電のスイッチを切っても、プラグが差し込まれているだけで電力消費が発生しており、そうした待機時消費電力は、家庭における電力消費全体の約1割を占めていることが明らかにされた。これに対し家電メーカーなどが各社、待機時消費電力削減目標を掲げて改善を推進、ビデオデッキやテレビ放送チューナーを中心に改善が進み、現在は、待機時消費電力は電力消費全体の6.0%にまで縮小している。出所:(財)省エネルギーセンター「平成20年度待機時消費電力調査報告書」
以前、「家電の待機時消費電力量が大きいことは問題。電気代換算で1戸当たり年間1万円相当になる」ということが話題になったのを覚えているだろうか。あのときの仕掛け人が、中上所長である。「1万円というのは消費者にとりインパクトのある金額だったので、関心が急速に高まった結果、メーカーも待機時消費電力低減に力を入れるようになり、年々、大幅に低減効果が表れています」という。実際、日本の待機時消費電力低減は、欧米からも注目されるほど短期間に成果を上げている。