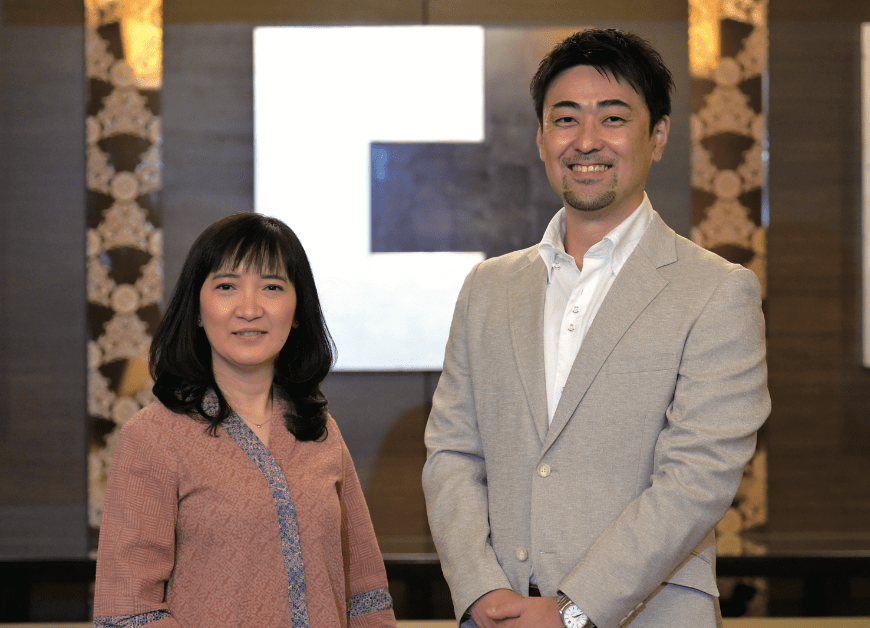
インドネシアの独立系ノンバンクとして、主力の自動車販売金融事業で業界上位のポジションを占めるOTO(オト)グループ。2013年から本格的にスタートした同社のDXと顧客体験(CX)の変革に常に伴走してきたのが、アビームコンサルティングインドネシアだ。OTOグループのヴィクトリア・ルスナ氏とアビームの村山明氏が、DX/CXのあるべき姿を展望する。
銀行系、メーカー系に対しCXで差異化を図る
村山 まずOTOグループについて、簡単にご紹介いただけますか。
ルスナ OTOグループはオートローン(自動車販売金融)を中心とするノンバンクであり、傘下に四輪向けのOTOムルティアルタ(OTO Multiartha)、二輪向けのサミットOTOファイナンス(Summit OTO Finance)の2社があります。この2社には、住友商事が49.9%、三井住友銀行が35.1%、インドネシア財閥のシナルマス(Sinar Mas)が15%を出資しています。
1994年に現CEOであるジョハン・マルズキ(Djohan Marzuki)が創業し、従業員数は現在6000人程度です。
創業以来の私たちのビジョンは、インドネシア社会に手頃なオートローンを提供することです。特にインドネシアの中低所得者層は、銀行から融資を受けることが容易ではないので、より多くの人が金融サービスにアクセスできるようにすることが、私たちの重要なミッションだと考えています。
そこで2018年にはビジョンとミッションを再定義しました。一言で言えば、私たちはインドネシアの金融サービスをリードするソリューションプロバイダーを目指しています。オートローンだけでなく、リースや保険、新車の残価を担保とした個人ローンなどサービスを拡充しており、法人と個人のお客様の金融面でのさまざまな課題に対して、ワンストップソリューションを提供できる存在になることが現在のビジョンです。
村山 日本では政府レベルでも民間レベルでも、DXが大きな課題となっています。
私がインドネシアに赴任したのは2013年ですが、それ以降、急成長したのが二輪タクシーの配車アプリとしてスタートし、食品や医薬品のデリバリー、電子決済などにサービスを広げてスーパーアプリ化したゴジェック(Gojek)、インドネシアのアマゾン・ドットコムと呼ばれるeコマース大手のトコペディア(Tokopedia)です。マレーシアを本拠とするゴジェックのライバル、グラブ(Grab)もインドネシアで急速に普及しました。これらの企業が生活に密着した各種サービスのデジタル化を牽引したことにより、インドネシア社会のデジタル受容度は、世界的に見ても非常に高い水準にあります。
また、インドネシアを代表するユニコーン(評価額が10億ドル以上の未上場企業)だったゴジェックとトコペディアの2社は、合併によってデカコーン(評価額100億ドル以上の未上場企業)となり、2022年3月に株式を上場しました。
このようにデジタルネイティブ企業の動きは非常にダイナミックですが、インドネシアにおけるDXの進展をどのように受け止めていますか。