全く新しいUIにはユーザーに学習を強いる弊害がある
伊藤 意匠登録出願の書類はデザイン開発のどの段階で作成するのですか。
 特許庁 審査第一部 情報・交通意匠 伊藤翔子 審査官
特許庁 審査第一部 情報・交通意匠 伊藤翔子 審査官
高部 デザインモック(試作画面)が出来上がると、画面のイメージが分かります。ただ、それは完成品ではなく締め切りギリギリまで詰めていくので、出願に必要な図面と願書の文章のうち、文章を先にドラフトして、 画像が完成した段階で図面を作成し、文章を微調整するという流れになります。弊社のユーザーファーストの考え方やスピード感を踏まえると、待っているのではなく、「デザイナーに伴走していく」というやり方が合っていると思います。
町田 意匠権を取るためにデザインしているわけではないということは、知財部の皆さんも理解しているので、コンフリクト(衝突)はありませんね。
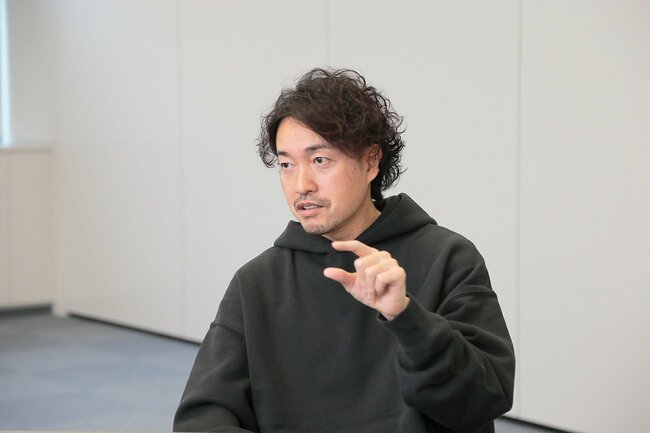 LINEヤフー Design Executive Center UXD本部 町田宏司 本部長
LINEヤフー Design Executive Center UXD本部 町田宏司 本部長
高部 知財部も権利を取ること自体が目的ではないという点は同じですから、デザイナーに権利を取るためにこうしてほしいと要求することはありません。ヒアリングした中で、デザイナーが今は実装できないけれど将来は実装したいと考えていることがあれば、将来の実装に対応した出願を考えます。
町田 伴走という話を続ければ、デザイナーはユーザーに選ばれるものがいいものと考えているので、いいものを競合会社が持っているのなら分析研究をして、取り入れられるものは取り入れる。権利を侵害しそうであれば知財部に相談して、ブラッシュアップしてより良くするというプロセスを経て弊社らしいプロダクトに変えていく。インターネットの世界にあるオープン&シェアという考え方が反映されているのだと思います。
伊藤 良いプロダクトをさらに使いやすいデザインにして差別化を図ることで、LINEヤフーらしさも表れてくるということですか。UIのデザインは、全く違う新しいものを作って他社の権利を避けていこうというような開発の進め方とは違う考え方なのですね。
町田 既にいいUIがあるのに、別の新しいUIを作ることが正しいとは思いません。ユーザーに新しい学習を強いることになるからです。インターネットの世界は同じような機能を持つUIであれば、最も使いやすい正解らしき方向へどんどん収斂していくので、デザインがどうしても似てしまうことはあるでしょう。そこで知財部の皆さんに「それは似過ぎ」というふうに待ったをかけていただかないと、そのまま出してしまいます(笑)。