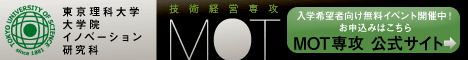テレビメーカー各社は、テレビ事業の大幅な赤字を解消すべく改革を進めているものの、その進展は芳しくない。テレビにおける大イノベーションであった液晶などのフラットパネルディスプレイ技術が、なぜこれほど短期間で競争力を失い、テレビ事業の存続を脅かすものになったのか。技術経営の探究を一方の軸とする東京理科大学専門職大学院の教授陣が、現代のビジネス課題を講義する【LECTURE Theater 2013】第4回は、自ら液晶パネル開発の最前線にいた坂本正典教授に、日本のテレビ敗北の真因を聞いた。
後ろ向きで高級展望車に乗り、
「技術バカ」と呼ばれてはにかむ技術者たち
液晶パネルや有機EL(エレクトロルミネッセンス)の研究と開発に取り組んできた技術者として現役の技術者の心中を察するならば、彼らは今、豪華な特急列車の最後尾の展望車に後ろ向きで乗っているような気分ではないでしょうか。
 東京理科大学専門職大学院
東京理科大学専門職大学院イノベーション研究科 教授
坂本正典(さかもと・まさのり)
東京大学工学部卒業。同大学院物理工学専攻博士課程修了。工学博士。1979年東芝入社、総合研究所主任研究員、液晶開発センター開発部長、米国MIT客員研究員(物理)、日本液晶学会理事、東京大学工学部非常勤講師等を歴任。Covion GmbHの有機EL材料Business Managerを経て、2004年より現職。共著に『液晶便覧』(丸善)、『Alignment Technologies and Applications of LiquidCrystal Devices』(Taylor & Francis)、『技術者のためのマネジメント入門』(日本経済新聞社)など。日本MOT学会理事。
目にするのは、過ぎ去る景色ばかり。美しく感動的なその景色は誰かの演出によるもので、自分はただ眺めるだけ。本音をいえば、鈍行の電車でもよいから運転席に座り、鉄路の先の景色を真っ先に我が物にしたいという気持ちを抑え切れずにいることでしょう。
現在、日本メーカーの研究開発や営業の現場では、「努力をしているのに、なぜ中国や韓国のメーカーに勝てず、報われないのか」という呻きにも似た声が充満しています。そして、責任者たちは、出口を見つけられない苦労に身悶えています。
実際、日本で開催されるフラットパネルディスプレイの国際的な展示会として「FPDインターナショナル」に、サムスン電子やLG電子などは出展しなくなりました。「もはや日本から学ぶべきものは何もない」と言っているかのようです。かつてのように「日本メーカーは、技術力はあるのに商売が下手」などと自嘲気味に笑っていられる状況ではありません。とはいえ、「ひたすら技術を追究すれば再び勝てる」というわけでもない。
評論家の吉本隆明は、「第2の戦後も終わった」と看破しました。第1の戦後はものづくりに全力を傾注し、第2の戦後では製品を世界中に売りまくった。そして今、私たちの眼前にある「第3の戦後」では、例えば、犬や猫の顔写真が並ぶ意見交換の場所に人々が集まり、夢中になっている。科学的思考法でいえば、単なる思いつきにすぎないような技術やアプリケーションが収益化の主流になっているのです。
今、技術開発はハードウェアそのものよりもシステム開発にシフトしなければならないのに、それがなかなか進まない。どうしてこのような事態になったのでしょうか。
もちろん、技術者の責任も大きい。「技術バカと呼ばれる喜び」から抜け出せなかったことです。例えばTFT液晶の開発では、アイデアそのものは日本オリジナルではありませんが、日本の技術者たちはコストの安いアモルファスシリコンの活用策や回路設計の微細化、そして無欠陥製品の製造など、パーフェクトなものづくりをめざしました。
私がTFT研究に取り組んでいた1980年代頃は、名刺サイズぐらいのディスプレイでポケットテレビを作るのが精一杯で、画像ムラは出るし、部品から発生する高周波で雑音だらけの状態でした。当時は誰もが「A4版ほどの大きさで、無欠陥のパネルを量産することなど到底無理」と思っていました。
しかし、そこにノートパソコンという“女神”が登場します。10.5インチ液晶搭載のノートPCは、ビジネスの現場で圧倒的な支持を得て、TFT液晶は、それがなければ製品として成立しない「キラーアプリケーション」として成功を収めていきます。
一方、現在、開発競争が続く有機ELはどうでしょうか。フラットパネルという意味では液晶と同じで差別化が難しく、それ自身がキラーアプリケーションになりうる製品(乗り物)はまだなく、しかも有機ELの強烈な特徴である「曲げられる」という性質も、消費者の「曲がるものは安物ではないか」という誤解をなくすに至っていません。有機ELは、出発当初から安価な部品というイメージを背負い、その宿命的な課題を乗り越えるものづくりが求められているのです。では、日本メーカーが苦悶から脱出できる糸口はあるのでしょうか。