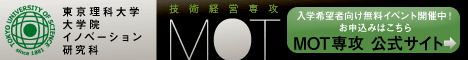シャープのブラックボックス戦略の功罪
思わず快哉をあげたサムスン会長
ソニー、パナソニック、シャープ、そして東芝も、テレビ事業で惨敗です。それにはさまざまな原因と理由がありますが、ここではシャープの液晶事業における「ブラックボックス戦略」を例に考えてみましょう(事前にお断りしておきますが、シャープの戦略的決断について批判的なスタンスを取っているのではありません。あくまでもビジネス環境との関係のなかで、その戦略を検証しようとするものです)。

シャープは、液晶パネルやテレビの開発で、徹底したブラックボックス戦略を採用しました。部品の発注は細切れで、外注先もバラバラ。取引先は、自ら製造した部品が、シャープの液晶テレビでどのような機能を発揮するのかさえ定かではない。その製造工程の全貌を知る者は、社長以下数人しかないなどと伝えられたこともあります。マスコミはその戦略を、「素晴らしい技術だからこそ、中韓などの新興国メーカーに対抗する戦略として有効」と評価していました。
しかし一方で、サムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長は、シャープの戦略を聞いて、「助かった。これで勝てる可能性が生まれた」と快哉したといいます。それは、どういうことなのでしょうか。
1990年代後半から2000年代初頭にかけて、中国は文化大革命による「凍った歴史」から解き放たれ、徐々に生産能力を高めていました。もしシャープがオープンな水平分業体制を選択して、中国メーカーに生産を委託したらどうなるか。サムスンは、急速に力を付けるであろう中国メーカーへの対抗策を練らなければなりませんでした。しかし、シャープのブラックボックス戦略により、歴史のスピードは一挙にスローダウンする。これで李会長は「助かった」と思ったのです。
そしてもう一つ、実は液晶技術そのものが、すでに爛熟期に入っていたという事情があります。シャープはブラックボックスと言っていましたが、液晶パネルの要素技術はすでに技術者たちの知るところであり、特許が公開されなくても手の届く技術レベルにあったのです。李会長は、シャープがブラックボックス化しても追い着くことは可能であることを見込んでいたのです。
それなのに、なぜ、シャープはブラックボックス化に突き進んだのか。その大きな誤解の一つが、「世界のものづくり大国としての日本の地位は維持できる」という強い自負でした。つまり、日本のメーカーはまだまだ製造力で世界と勝負ができると考えたのです。亀山工場だけでなく、堺工場の稼働も予定に入り、そうした思いはいっそう強まっていきます。
後の2009年に、片山幹雄社長(当時)は、「シャープはエンジニアリング企業になる」と宣言しますが、体質転換は思うように進みませんでした。亀山や堺に賭けた思いは、それほど強く、体質転換を阻害するものだったのです。
しかし、私は、シャープのブラックボックス戦略が全面的に間違っていたとは考えていません。「半分わかっていて、半分わかっていなかった」という感じでしょうか。つまり、ブラックボックス化すべき場のハンドリングを間違えたのです。
製品が発案されて市場に出るまでの時間を横軸、情報の質の高低と量の多少を縦軸にとったグラフをイメージすると、情報の質と量は研究段階から徐々に増え始め、生産段階でピークを迎え、その後急速に下降する曲線を描きます。
ブラックボックス戦略は、生産歩留まりに関する技術を秘匿するには極めて重要な戦略ですが、研究や開発の段階までも含めた製品の全サイクルを対象にすれば、ごくごく単純な鎖国状態を引き起こしてしまうだけです。
江戸時代の鎖国により、近代西洋科学の発達から大きく出遅れたように、シャープの鎖国は、ものづくりがオープンソース化する世界的な流れに乗り遅れる事態を招きました。むしろシャープは、ものづくりにおける日本を軸とする垂直統合型の流れに変化はなく、部品改善や製造改善による歩留まりの向上こそが競争優位であると考えたのです。
しかし、世界のメーカーは、まったく違った風景を見始めていました。オープン化であり、ファブレス化だったのです。