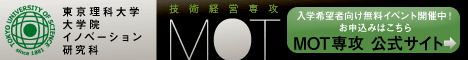インターフェース時代に
メーカーは何に力を注ぐべきか
テレビ事業の赤字が、他社ほど大きな額になっていないのが東芝です。地デジ放送の開始に伴うテレビの買い換え需要商戦では、「レグザの不思議」といわれるほど黒字で健闘しました。
シャープのブラックボックス戦略の挫折とは好対照に、レグザの不思議には、戦略の妥当性を議論する以前の、現代の世界のものづくりの実情が色濃く映し出されています。それには、単純で簡単な事実が一つあったのです。

そもそも東芝は、フラットパネルを持っていませんでした。水平分業といえば聞こえはよいですが、要するにパネルを外部調達して組み立てていたのです。最新の最大サイズのパネルを自家生産しているという名声や評判は獲得できませんでした。
しかし、レグザには重要な教訓が示されています。それは、「現代のデジタル家電における品質や性能は、0か1しかなく、安物だから0.5ということはない」ということです。0は困るけれども、1であれば問題はない。安く買ってコストを削減した分だけ、メーカーは、画像エンジンの高度化など、消費者に独自性を理解してもらえる部分の研究開発に注力すればよいのです。それがファブレス化の衝撃といえるものです。
電子・電機製品は、いまやインターフェースさえ合致すれば、どの会社の部品を使っても完成品を作れます。デスクトップパソコンが、失礼ながら素人でも自作できてしまうのは、現代の電子・電機製品の特性を見事に証明しています。つまりメーカーが、すべての部品や関連技術を持つ意味が薄れている。言葉を換えれば、昔ほど商売としてのうま味がないのです。
こうした事態を受けて、日本の電子・電機メーカー各社は、赤字事業の合従連衡を進め、開発や生産の効率を上げようとしています。かつてのように、垂直統合でメーカー同士の交流が少なく、異なる発想を持ち寄って革新的な技術を生み出す機会も乏しかったことを考えれば、合従連衡に伴う人材のシャッフルは一歩前進といえるでしょう。
しかしながら、根本的なビジネスモデルは、まだ何も変わっていないのではないでしょうか。私には、そういう疑問が残っています。例えば、かつて半導体では、日本は「超LSI技術研究組合」を組成し、一挙にアメリカの半導体産業を衰退させました。その勢いを受けて、いくつもの研究コンソーシアムが組成されましたが、超LSI技術研究組合を超えるほどの成果を生み出せていません(どのコンソーシアムも、表向きには「成功裏に終了」ですが、その後の日本の半導体産業の衰退を見れば、胸を張れるものではありません)。
それはなぜか。超LSI技術研究組合は、技術のキャッチアップのための組合であったからです。キャッチアップ段階は、どの国でもどの業種でも強烈な団結心と追究力が生み出されます。しかし、その後、創造段階に入ると事情は一変します。どのメーカーも、できれば自分たちだけが美味しいところを手にしたいのが本音です。それゆえ、合従連衡においても、2社統合なら2に、3社統合ならば3にとどまるような成果では統合の意味をなさず、5や6もの成果を出せる抜本的なビジネスモデルの追究が不可欠です。
私は東芝を退社した後、一時期ドイツのメーカーにいましたが、その時、「日本のように技術を持ちながらも停滞しているのは、逆に先頭にいる証左かもしれない」と同僚に話したところ、「ドイツはそれを1960年代から味あわされ続けている」とさらりと返されました。それほど、構造やビジネスモデルの抜本的な改革は難しいのです。