今月の主筆
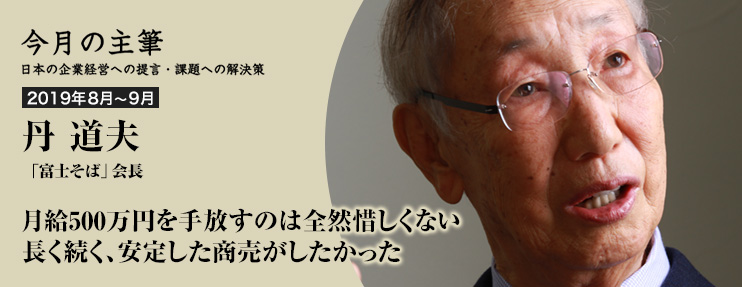 第1回
第2回
第3回
第4回
第1回
第2回
第3回
第4回
バックナンバー

丹 道夫
「富士そば」 会長
そば好きじゃない富士そば会長が非効率経営で成功した理由

元谷芙美子
アパホテル 社長
アパホテルが五輪後の「供給過多」を怖れず拡大戦略に走る理由

小林一雅
小林製薬 代表取締役会長
小林製薬のユニークすぎる商品群は「米国のトイレ」に原点があった

大田弘子
政策研究大学院 大学教授
残業削減と生産性向上の二兎をどう追うか、大田弘子氏が語る働き方改革の本丸

青野慶久
サイボウズ 代表取締役社長
サイボウズ青野社長が説く「会社というモンスター」に振り回されない覚悟

柴山和久
ウェルスナビ 代表取締役CEO
退職金・年金が減る時代、世界水準の資産運用が日本に必要な理由

塩崎 均
近畿大学 名誉学長
近畿大学が志願者数日本一になれた理由、塩崎名誉学長が語る

西 和彦
アスキー創業者 東大大学院IoTメディアラボディレクター
マイクロソフトはなぜスマホ時代の敗者となったのか、元アスキー西和彦が語る

大林豁史
ドトール・日レスホールディングス 代表取締役会長
ドトール・日レス、飲食46ブランドを束ねる男の「外食人生」のルーツ

矢野博丈
大創産業 会長
ダイソー矢野会長「自分は不運、こんな会社すぐ潰れる」と疑い続けた弱気人生

坂本 孝
俺の 社長
「ブックオフ」「俺のイタリアン」生んだ70代起業家・坂本孝が挑む“次”

市江正彦
スカイマーク 社長
スカイマーク再建に片道切符で乗り込む銀行マンを導いた「奇縁」

大塚勝久
匠大塚 会長
匠大塚会長が“父娘げんか”を経て語る「事業承継ここを誤った」

辻本憲三
カプコン 代表取締役会長CEO
「モンハン」のカプコン会長が予言、ゲームは“スポーツ”にもなる

益子 修
三菱自動車 CEO
三菱自・益子修CEOが説く、企業も国も改革には「女性の力」が不可欠だ

澤田秀雄
エイチ・アイ・エス会長兼社長 ハウステンボス社長
ハウステンボス再建、HIS社長に電撃復帰…澤田秀雄の「失敗と再生」史

似鳥昭雄
ニトリホールディングス 代表取締役会長兼CEO
ニトリ“一人勝ち”の裏には「ロマン」と「ビジョン」があった

永井浩二
野村ホールディングスグループ CEO・代表執行役社長
野村證券の社長を決めるのは前任者ではない、「時代が選ぶ」

佐藤康博
みずほフィナンシャルグループ 社長・グループCEO
みずほFG社長、銀行業界激動の時代に見つけた「勝利への解」とは

高田 明
ジャパネットたかた創業者 A and Live代表取締役
ジャパネット・高田明氏、“買い物に興味がない私”が会得した「売る極意」

菊地唯夫
ロイヤルHD 会長兼CEO
畑違いの外食業、ロイヤルで必要なことは日債銀での頭取秘書時代に学んだ

出口治明
ライフネット生命 会長
「なぜ?」が腹落ちする快感に導かれた出口治明の読書人生・仕事人生

玉塚元一
ローソン 会長
幼稚舎からの慶應ボーイが「キラキラの人生」を選ばない理由

松本 晃
カルビー 会長兼CEO
カルビーは「良い会社だが儲け方が下手」、だからCEOを引き受けた

小飼雅道
マツダ 代表取締役社長兼CEO
マツダが「他社と違うことをやる」のは、むしろ技術開発に愚直だから

小林喜光
三菱ケミカルHD 会長
勤め人を嫌い、人生の意味を探していた哲学者が経営者になるまで

木川 眞
ヤマトホールディングス 会長
ヤマトグループが絶え間なく新サービスを投入できる理由

岡藤正広
伊藤忠商事 社長
伊藤忠はなぜ商社ナンバーワンになれたのか

鈴木敏文
セブン&アイHD 名誉顧問
鈴木敏文氏が語る、GMSの衰退に歯止めがかからない理由

村井満
日本プロサッカーリーグ チェアマン
命を賭する覚悟で引き受けた財政危機のJリーグ建て直し

御立尚資
ボストン コンサルティング グループ
根っからの「傍流・辺境の人」がコンサルタントになるまで

松井忠三
良品計画 名誉顧問
無印良品の最悪期に社長就任。現場を歩いて見つけた「6つの病巣」

安渕聖司
日本GE合同会社 代表職務執行者社長兼CEO
ひるまずに「選択と集中」をどう判断するか

大山健太郎
アイリスオーヤマ 社長
毎年1000点の新商品は「生活者の困った」から生まれる

伊東信一郎
ANAホールディングス 会長
「何でもやっていい」“放任主義”がLCCを育てた
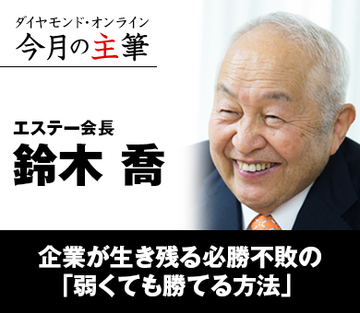
鈴木 喬
エステー 会長
企業が生き残る必勝不敗の「弱くても勝てる方法」
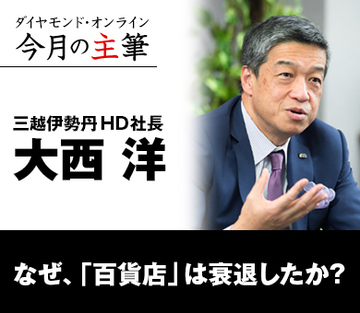
大西 洋
三越伊勢丹HD 社長
なぜ、「百貨店」は衰退したか?
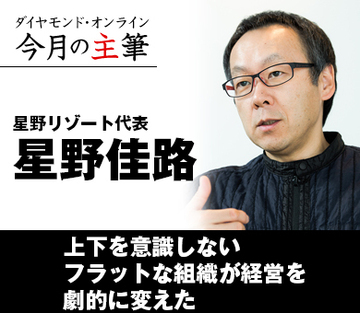
星野佳路
星野リゾート 代表
上下を意識しないフラットな組織が経営を劇的に変えた

樋口泰行
日本マイクロソフト 代表執行役会長
マイクロソフトも陥った「成功体験の罠」

坂根 正弘
コマツ 相談役
経営者は「強いものをより強くする」戦略をためらってはならない