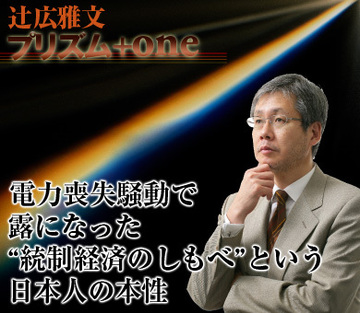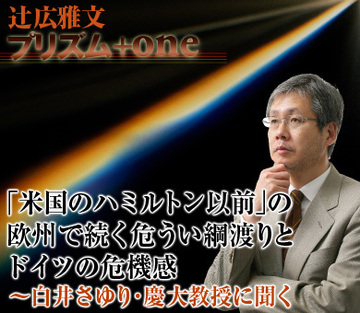年末年始、東京・日比谷公園に設置された「年越し派遣村」に多くの耳目が集まり、職と住居を失った人々の悲惨な暮らしぶりが繰り返し伝えられると、政府与党、野党ともに動かざるを得なくなった。舛添・厚生労働相は「製造業への派遣を規制すべきだ」との考えを表明した。野党も民主党が中心となって、製造業派遣規制に共闘して踏み込もうとしている。
今日のパニック的な派遣切りの主因の一つは、産業界の要望を全面的に政府が受け入れ、雇用の規制緩和一辺倒で対応してきたことにあるから(当コラムの第56回「“派遣切り”の加速は、企業の本質を理解できない政府の自業自得だ(2008年12月18日」)、規制の多面的見直しに進むのは、セーフテイネットの拡充とともに、当然であろう。
だが、与野党ともに、あの年越し派遣村に集った人々が何者なのか、社会にどう位置付けされるべき問題なのか理解していないように思える。政治がいかなる責任を持って対応すべき人々なのか、認識できていないと思われる。
繰り返し報道されたように、彼らが数百円、数千円を握り締め、放置すれば命も危うい人々なのであれば、それは貧困者である。貧困は、洋の東西、政権の右左を問わず、政治がその撲滅に全力を挙げるべき社会問題である。右派のブッシュ米大統領であろうが左派のブレア前英首相であろうが、各国の指導者は必ず「貧困の撲滅」を公式演説で触れ、約束する。
だが、この先進諸国、OECD諸国における“常識”が、日本だけにない。日本政府は1966年に貧困層の調査を打ち切り、再開していない。戦後の困窮期を抜け、高度経済成長を経て、豊かな社会を築いた自負から、もはや貧困はないものとしたのである(当コラムの第4回「貧困をイデオロギー問題として捉えた日本の不幸(2007年11月28日)」)。
だが、それは見たくないものを見ないようにしただけだった。なくなったわけでは、やはりなかった。もはや貧困は、見たくなくてもだれもの視野に入らざるを得ない。現に今、私たちは東京・日比谷でそのごく一部の人々を目の当たりにした。とすれば、自民党も民主党も、貧困撲滅を政権選挙のマニュフェストに重要項目として掲げるべきであろう。むろん、それは数値と具体策に裏打ちされたものでなければならない。
ないものとしてきたものを撲滅するには、まず、その対象を“発見“しなければならない。それには、「貧困ライン」の設定が必要となる。所得で貧困層を定義するのである。参考になるのは、2006年にOECDが発表した、各国の貧困率である。OECDの貧困層の定義は、「全国民を可処分所得の高い順に並べたときに、中央に位置した人の可処分所得額の半分に満たない人の数」であり、日本のそれは15.31%であった。