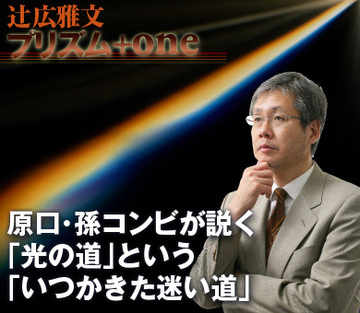辻広雅文
第123回
日本人はいつまでも変わることなく、政府による“統制経済のしもべ”であり続けるのだろうか。そして、この素朴な疑問に対して、大手メディアがいっさい議論を起こそうとしないのはなぜなのだろうか。
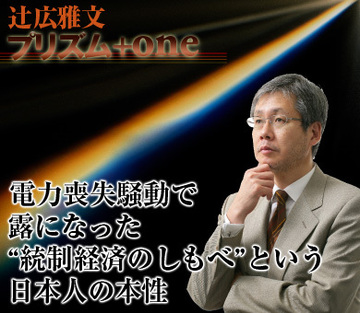
第122回
人々に地震リスクと向き合ってもらい、住宅の質を向上させていく制度設計は、政府の最優先に取り組まなければならない政策だ。だが、政府が介入、強制しても、人々は望む方向を向かない。齊藤誠教授は、「リバタリアン・パターナリズム」による働きかけこそ有効だと語る。
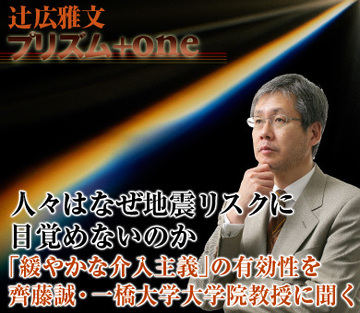
第120回
金融政策は統一されても財政政策はばらばらという欧州の問題を、専門家たちは「ハミルトン以前」と形容する。ハミルトンとは、初の連邦債を発行した米国の初代財務長官だ。今回の財政危機を経て、欧州がハミルトン後に移行する可能性はあるのか。眼前の危機の行方とあわせて、白井教授に聞いた。
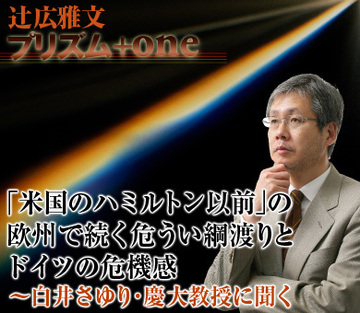
第119回
通貨安競争に巻き込まれ、日本経済は円高によって体力を消耗していく。一方、財政危機を考えれば、いずれは円安に大きく振れることは確実と思われる。円高から円安へ――大転換のショックを和らげる戦略が必要だと、小林教授は指摘する。
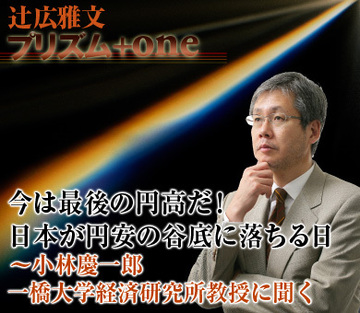
第118回
2010年のノーベル経済学賞は、サーチ理論と呼ばれるモデル構築に対し、MITのピーター・ダイヤモンド教授ら3氏に決まった。サーチ理論は労働市場の分析に極めて有効だ。今井亮一・九州大学准教授に、サーチ理論から見た日本の労働市場の特質を聞いた。
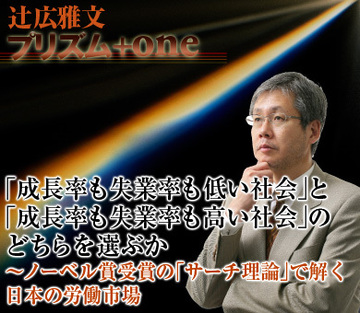
第117回
ワンフレーズによる二分法は上滑りの熱狂を招くという危険は承知しているが、日本にとって、TPPに参加するか否かは総選挙に打って出るほどの分かれ目だ。日本経済を構成するおよそ10%程度の既得権集団だけが左右してよい選択ではない。
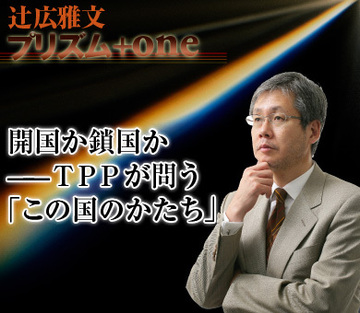
第116回
米国の量的緩和は、もはや金融政策ではない。財政赤字をまるごと買い取ってしまう“財政政策”だ。ドル安誘導とインフレ促進でバランスシート調整の苦境を乗り切ろうとするFRBにつきまとう怪しさ、危うさとは何か。
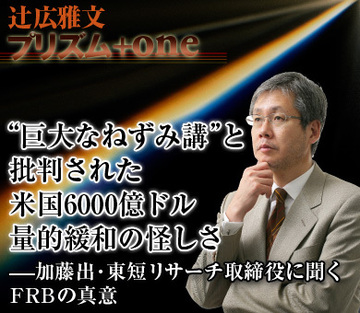
第115回
英キャメロン政権が、戦略性もなく漫然と実施する愚かな財政出動と一線を画し、裁量的な経常支出どころか社会保障にも切り込む一方で増税にまで踏み込む。この日本との彼我の差の背景には、裁量的財政政策の有効性に関する歴史的経験の差がある。
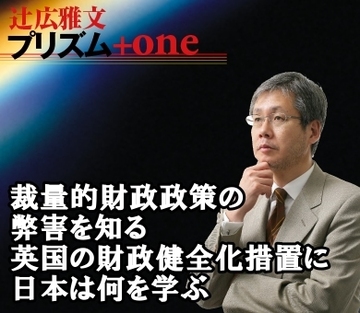
第114回
日銀が「包括緩和」と自称する追加金融緩和に踏み切った。白川総裁 は、それを“異例の措置”だと説明した。従来の政策の延長線上で規模を異例なほど拡大したということなのか。それとも、中央銀行が本来踏み入れてはならない異端の道に進んだという意味なのか。
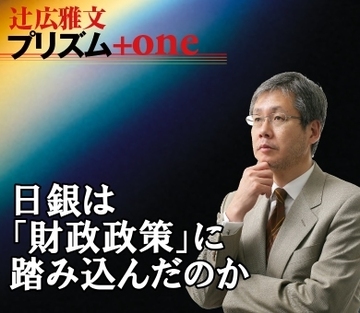
第113回
失業率は質の異なる2種類に分けて考えることができる。「需要不足失業率」と「自然失業率」である。何より問題なのは、仮に効果的な雇用対策が打たれ、労働の需給ギャップが解消されたとしても、常態として日本は3.5~4.1%の失業者が存在するということである。
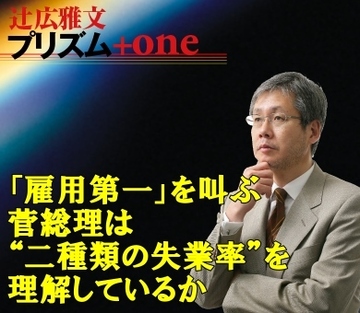
第112回
民主党代表選は菅首相の勝利で終わったが、国会議員票だけ見れば、僅差であり、小沢前幹事長は善戦した。現職の総理大臣という有利な立場にありながら、なぜ菅氏は苦戦したのか。飯尾教授に、代表選の結果分析と民主党政権の今後の課題を聞いた
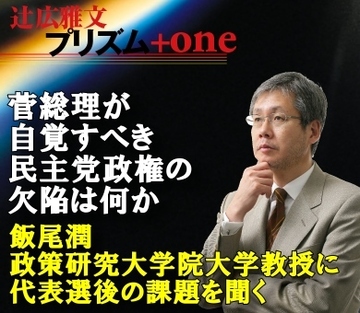
第111回
マスコミは円高に危機感を露わにし、政府・日銀の無策を批判する。しかし「今の円高は想定内」という声がないわけではない。円安信仰に染まった日本の姿勢を転換させる転機とはできないものか。

第110回
2010年度の最低賃金は、全国平均で15円引き上げられることが決まった。雇用の喪失や中小企業の経営への悪影響を指摘する声はある。しかし実際には、より生産性の高い産業構造への脱皮を図るチャンスとして捉えられないだろうか。
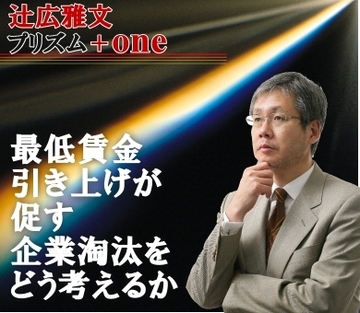
第109回
過去から繰り返し専門家が指摘しているにもかかわらず、日本経済に関しては“常識の非常識”がはびこっている。例えば、「日本は貿易立国である」こと。「輸出依存度が高い」こと。「内需依存度が極めて低い」こと。意外だと驚かれたあなたは、常識の非常識に囚人である。
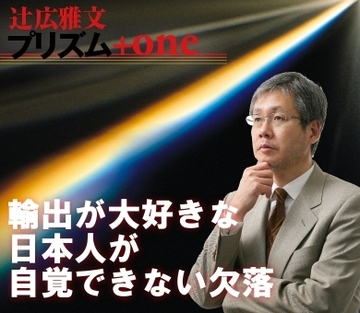
第108回
米国にデフレが忍び寄っている。原因をひと言で言えば、経済が供給過剰状態にあるからである。家計と企業におけるバランスシート調整が、まだ始まったばかりだから、といってもいい。
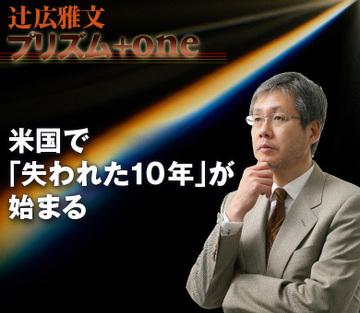
第107回
菅政権は11年度予算で歳出を70兆9000億円に抑え、国債発行枠44兆5000億円を守るという「中期財政フレーム」の二大公約を果たせるだろうか。結論を先に言えば、極めて難しい。しかし、その放棄は国民の失望に加え、国債マーケットの叛乱を呼び込みかねない。
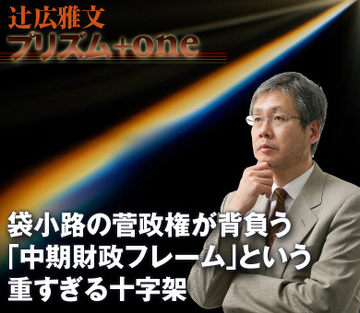
第106回
「消費税10%」に言及した菅政権の支持率が低下している。増税自体への嫌悪、使途が曖昧であるが故の不信――いったい何のための増税か。増税によって不況を克服する「第三の道」とはいかなる政策か。菅首相のブレーンを務める小野善康・大阪大学教授に聞いた。
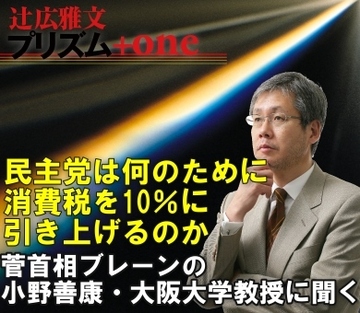
第105回
私たちは常に経済成長を追い求める。だが、経済成長は果たして、どれほど人々の幸福に結びつくのか。新著『競争の作法――いかに働き、投資するか』で経済成長の欺瞞をあぶり出した斉藤誠・一橋大学大学院教授に聞いた。
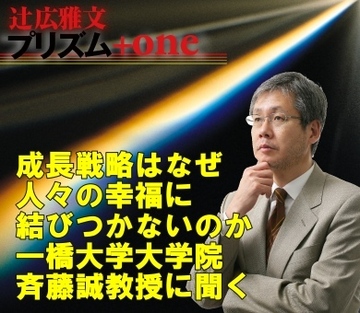
第104回
欧州の地鳴りが止まない。財政危機のマグマがいずれの国で噴出するのか。ギリシャ危機が南欧に拡大し、東欧のハンガリーに飛び火した。マーケットは獲物を狙うがごとく、“次”を探す。白井・慶大教授は、「財政再建は、長く、苦しい、茨の道だ」と、欧州低迷の長期化を指摘する。
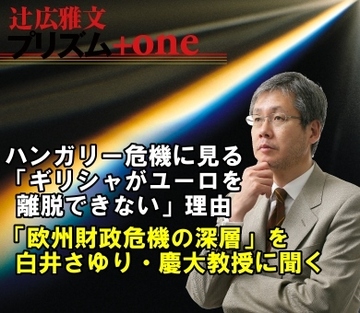
第103回
私たち日本人は市場経済にいまだ不慣れなせいか、しばしば安くてよいモノやサービスの提供を受けるための条件を忘れて議論を迷走させてしまう。原口総務相と孫ソフトバンク社長が説く「光の道」もその典型例だ。