メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が昨年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。
本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章や原稿が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は、抜群におもしろい原稿を書くために押さえるべき「4つの感情」について。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
自分の感情の流れを追おう
ライターであるあなたは、いま取材を終えたところです。いい取材ができた、おもしろい話が聞けたと、職業的な満足を得ているかもしれません。さて、それでいまのあなたはどれくらいの「伝えたい!」を抱えているでしょうか?
どうすればそれを伝えきることができるでしょうか?
あなたの「伝えたいこと」と、読者の「知りたいこと」は、一致するでしょうか?
そもそもあなたは、対象の核心をつかみきれているのでしょうか?
原稿に臨む前、取材を振り返ってライターは、自分の感情の流れを丹念に追っていく必要があります。対象についてなにも知らなかった自分が、そこに飛びつき、「伝えたい!」と思うまでに至った、理解と感情のステップを追っていくのです。具体的には、次の4項目になります。
(1)「おもしろそう!」……動機
取材をはじめる前、その対象についてなにも知らないながらもあなたは、「おもしろそう」と思ったはずです。たとえ編集者からオファーされてはじまった企画であっても、「おもしろそう」と思ったから引き受け、取材に出たはずです。人なのか、事業なのか、思想なのか、プロダクトなのか、研究や学説なのか、あるいは組織なのか。自分がなにに対して「おもしろそう」と感じたのか、その対象を思い返しましょう。
さらにここから、「おもしろそう」と思った理由を、考えていきましょう。ぜひとも会ってみたい人だったのかもしれないし、個人的な関心分野だったのかもしれない。最近話題のキーワードで、勉強するいい機会だと思ったのかもしれない。仕事人としての自分、趣味人としての自分、生活者としての自分、食いしんぼうな自分、あたらしいもの好きの自分。いったいどの自分が「おもしろそう」と思ったのか、思い返しましょう。これは届けるべき読者像を考える際、おおきなヒントになる要素です。
(2)「知らなかった!」……驚き
取材がはじまるとライターは、かならず「知らなかったこと」に遭遇します。
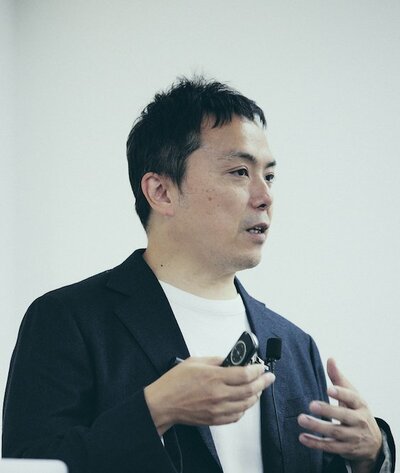 古賀史健(こが・ふみたけ)
古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。「バトンズ・ライティング・カレッジ」主宰。(写真:兼下昌典)
こんな人がいたのか。こんな考え方があるのか。こんな研究データが出ているのか。こんな史実があったのか。あの国には、この都市には、こんな制度があるのか。最新の医療技術は、こんなところまで進んでいるのか。てっきりAだと思っていたけれど、ほんとうはBだったのか。
あなたが「知らなかったこと」は、多くの読者にとっても「知らないこと」である可能性が高いと考えてください。少なくとも、「周知の事実」としてそれを語ると、なにも伝わらないと心得ておいたほうがいいでしょう。取材をはじめる前、自分はどこまでを知っていて、どこから先を知らなかったのか。どこまでが一般常識で、どこから先が専門領域なのか。冷静に考え、冷静に思い出しましょう。
そしてまた、「知らなかったこと」との遭遇には、驚きがともないます。
その驚きの強度(感情の振れ幅)を、忘れないようにしてください。あなたが驚いた情報は、読者にとっても驚きをもたらすものになるでしょう。なんでも知っていて、なにに対しても驚かない専門家の書いた文章は、読者のこころに寄り添いにくいものです。浅学非才で、からっぽのライターだからこそ、おおいに驚き、おおいに感動することができるのです。さらにその感動が、読者にも伝わっていくのです。わかったような顔をせず、醒めた――あるいは舐めた――取材者にならず、いつでも驚くことのできる自分をキープしましょう。
(3)「わかった!」……理解
インタビューを終え、音源を聴き返し、追加の資料を調べ、深く考えていく。すると、どこかの段階で「わかった!」と思える瞬間が訪れます。この人の言っていることが、やっとわかった。インタビュー中には理解できなかったことばの意味が、ようやく理解できた。この資料に出会ったおかげで、わかった。あの人のことばをきっかけに、わかった。
わかった瞬間には、目の前が急に開けたような、数学の図形問題が解けたときのような、えも言われぬ快感があります。そして数学の図形問題と同じく、一度解けてしまえばもう、「なぜ、あのときわからなかったのか」がわかりません。問題用紙を前に悶々と思い悩んでいた自分が、遠い他人のように感じられてしまいます。
自分はなぜ、わからなかったのか。自分はどうして、わかったのか。わからなかった自分は、どこでつまずいていたのか。どんな誤解や先入観のおかげで、回り道をしたのか。いつ、どんな扉を開け、何段くらいの階段をのぼって、どんなふうに理解へとたどり着いたのか。途中、どんな道しるべがあれば助かったのか。あのとき、どんなことばで説明してほしかったのか。
自分なりの理解に至った道筋を丹念にたどり、地図をつくるようにその道を再現しましょう。「自分のような浅学非才の人間でさえ、この道を歩けば理解できる」。そう思える道(ロジック)をつくることができれば、きっと読者も同じように理解してくれるはずです。
(4)「もったいない!」……衝動
対象について一定の理解が得られたからといって、そのまま原稿に取りかかるのは早計です。対象を好きになり、対象への理解が深まるほどあなたは、もどかしさをおぼえるはずです。こんなにすばらしい人が、ほとんど誰にも知られていない。こんなにすばらしい活動が、誤解のなかで過小評価されている。こんなにすばらしい思想が、傍流に追いやられている。こんなにすばらしいプロダクトに、粗悪品が出回っている。
もどかしさの正体をひと言であらわすなら、「もったいない!」です。
その人は、組織は、お店は、活動は、いったいなにが「もったいない!」のか。なにが足りなくて、なにが過剰で、なにを理由に誤解を受けているのか。自分ならどうやって誤解を解き、どうやって真意を伝えていくのか。
長い取材を通じて見つけた「もったいない!」にこそ、コンテンツの核心があるのだと考えましょう。そして「もったいない!」の衝動があるからこそ、雄弁になり、気持ちのこもった原稿が書けるのです。
いい取材は、「動機」にはじまり、「驚き」があり、「理解」に至って、やがて「衝動」をもたらします。動機のない原稿、ライター自身が驚いていない原稿、わからないままに書いた原稿、そして衝動に乏しい原稿、これらはすべてコンテンツの強度を欠いています。動機・驚き・理解・衝動までのストーリーラインをすべて読者と共有できたとき、そのコンテンツは抜群におもしろいものとなるのです。
(続く)







