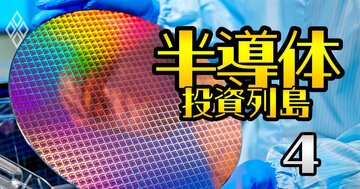日の丸半導体の競争力を削いだ日米半導体協定。1986年から10年間続いた。
日の丸半導体の競争力を削いだ日米半導体協定。1986年から10年間続いた。Photo:The Asahi Shimbun/gettyimages
1980年代の絶頂期の日の丸半導体を知る元経営者で、最高齢の一人である川西剛・元東芝副社長(95歳)。日本企業が高シェアを謳歌していた時代に、何が起きていたのか?日本製半導体の出荷が厳しく制限されていた日米半導体摩擦のさなか、実はひそかに行われていた、ある「打開策」とは?特集『高成長&高年収! 半導体160社図鑑』の最終回では、川西氏に当事者しか知り得ない当時を振り返りつつ、今熱狂を迎えている半導体業界をどう見るか、古巣の東芝への思いなど、入居中の高齢者住宅で2時間にわたって語ってくれた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 鈴木洋子)
日本で最初にファウンドリーをやったのは東芝
でも自社デザインを捨てられず続かなかった
――1980年代、日本はなぜ半導体で世界トップに立てたのでしょうか?
振り返ると、「追い付け追い越せ」だったからなんですよね。資源もない、しかも米国に戦争で負けた日本が、その米国を相手に米国で生まれた半導体であるメモリーで戦う、ということで日本企業はみんな燃えていた。しかもそこで圧倒的に勝った、ということは当時の日本人のアイデンティティーの確立には大きな意味を持った。それに関わることができた僕は本当に幸福だったと思う。
そして、「何を作るか」ではなく、「いかに作るか」の生産プロセスを徹底して追求していた。それが、結果的にはメモリーやトランジスタなどの単一の汎用品を作るときに強みとなって出た。また、ソニーや松下電器産業(現パナソニック)という顧客が日本にいたことも日本の半導体メーカーを大きく支えてくれた。時計にしても電卓にしても日本に巨大なマーケットがあり、当時は世界一流のお客が日本に集まっていましたからね。幸運でした。それから、シェアを争うライバルが日立製作所やNECなどで、みんな日本にいて、日々隣同士で切磋琢磨できたことも大きかったですね。
80年代の日本の半導体の強さは、基本になる物作りのところを徹底してやっていたことにありました。でも、それを日本よりもうまくやったのが、現在の台湾TSMCをはじめとするファウンドリーですよね。半導体のデザインはやらず、物作りに特化した。本来ファウンドリーは、日本こそがやるべき事業だったと思うけど、自分の半導体も作る総合電機はどうしても自分のデザインを捨てることができなかった。
実は日本で最初にファウンドリーをやったのは東芝だったんですよ。米LSIロジック(現アバゴ・テクノロジー)向けにゲートアレイ半導体(セミカスタム半導体の一種)を作って成功したんだけど、結局デザインを東芝に知られてしまうから、と警戒されて、事業としては続かなかった。TSMCは一切自社でデザインを持たない、と割切ることができたからあそこまで成功した。
――そして80年代は、日米半導体摩擦で日本企業が大きなダメージを受けた時代でもありましたね。
当時は、日本の工場の歩留まりと個数の報告を米国に義務付けられていたんだよ。そして、米国製半導体を強制的に購入することも義務付けられていた。屈辱ですよね。でも実は、当時アンチ日本の最右翼だった米モトローラを味方に引き入れて、東芝はすごくうまくやったんですよ。あれは僕の実績、といってもいいかもしれない。
それまで栄華を極めていた日本の半導体が凋落するきっかけとなったのが80年代の日米半導体摩擦だ。だが、その当時の逆境をかいくぐる奇策もあったという。その内幕や、東芝、日立、三菱電機、NECの経営陣の判断はどこが間違っていたのか、さらには、中国との付き合い方、過去の国策会社が失敗した理由など、話題は多岐にわたった。そして20年間の空白を経て反転攻勢に転じようとする国策半導体会社ラピダスの成功の鍵についても川西氏は語ってくれた。