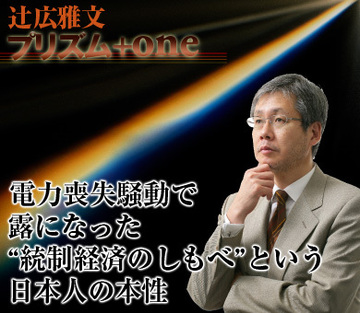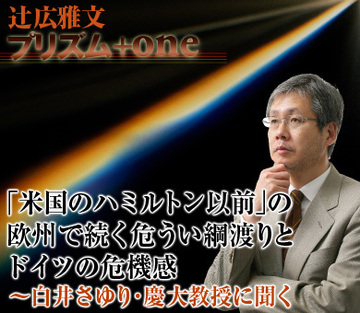故後藤田正晴氏は『語り遺したいこと』(岩波書店)の中で、“政治主導の意志決定システム”の構築に走る小泉改革の危うさを説いた。後藤田氏自身が戦後二十数人の首相に接した経験から、「優れた方もいたが、そうでない方も少なくなかった。総理大臣の権限強化は避けたほうが安全だ」と警告したのだった。
当時、小泉純一郎首相は国民の強い支持を得て、自民党と霞ヶ関が結びついた旧来型の意思決定システムを打破すべく、例えば、あらゆる政策決定において自ら主催するとともに民間議員に提言権限を持たせた「経済財政諮問会議」をフル活用した。
後藤田氏は、その経済財政諮問会議が憲法改正につながる首相公選制まで答申するに至って、「逸脱だ」と厳しく批判した。同時に、霞ヶ関の縦割り割拠主義のために設置された内閣府の混乱を指摘した。
確かに、危うさはあった。
小泉首相の片腕として経済財政諮問会議のみならず経済政策全般を取り仕切った竹中平蔵氏(現慶応大学教授)は大臣として審議会を設置する際、テーマも委員の人選も審議日程も、私的ブレーンのみに相談して決めた。官僚は完全にカヤの外で、大臣の政策意図も展開も読めないという状態に置かれた。
また、小泉構造改革に関わる幾多の審議会には小泉チームの学者、評論家がダブって配置され、まるで同好会のようなインナーサークルで改革の設計、実行が進んだ。まるで、霞ヶ関数万人の仕事を特定の数十人が引き受け、変革を進めることが可能であるかのようだった。後述する郵政改革の不適切な民営化の図面も、ここで引かれたのだった。道路公団改革の中身の空疎さは、早くも露呈しつつあった。
だが、私は当時、その危うさに耐えねばならないのだと考えていた。何より、旧来型の意思決定システムは機能不全に陥っていた。自民党と霞ヶ関の旧結合は、高度成長期の“富の分配”にのみ有効な過去の遺物であることが明らかだった。バブル崩壊後の金融システム改革にも、低成長時代に対応すべき歳出削減にも、対応できないのだった。政治は“損失の分配“をしなければならない時代に移っていた。新しい時代の国家戦略設計機能が必要だった。となれば、百害あって一利なしの旧来型意思決定システムは破壊するしかない。破壊するのだから、危ういに決まっている。問題は、新しい政治主導の意思決定システムをいかに構築し、修正し、使いこなすかにある。そうした資質ある政治家が多いとは思えない。時間はかかるだろう。そうだとしても、それができあがるまでの間、危うさに耐えるしかない。変革期とはそういうものなのだ――。