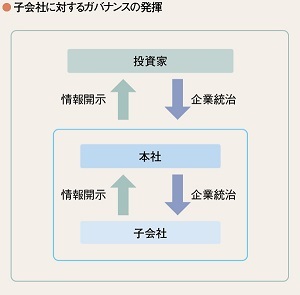1990年代に入って重要性が叫ばれてきたキャッシュフロー経営はすっかり日本に定着した感があります。一方、同じ頃から強調されてきた企業価値の向上についてはいまだ十分に咀嚼されていない企業・戦略も見られるようです。たとえば、M&Aをテコに企業価値を高めるうえで、日本企業固有の問題はあるのでしょうか。この点について、企業価値評価(バリュエーション)の本家ともいえるコンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーに、新版となる『企業価値評価第6版』邦訳版の出版を記念して書き下ろしてもらった特別寄稿を2回に分けてお送りします。同社の豊富なM&A支援の経験から見えてきた日本独自の課題とは?
日本企業はM&Aの数を増やしつつあるが、成功例と言われるものはまだ少ない。M&Aが本質的に価値を創出したのか、という問いに対しては、様々な研究があらゆる角度から行われており、総じて価値創造に至ったと明示的に言える案件は少ない、という論調である。
確かに、一般的に日本企業は欧米企業に対してM&A案件に対して高いプレミアムを払っていることを示すデータも存在し、その結果、リターンが期待通りに得られないケースは多いものと想定される。
一方で、短期的には高値掴みに見えたとしても、それが中・長期的な成長プラットフォームとなったり、長年の不振の時期を経たのちに、再建がなされて収益貢献が最も高い部門へ成長している事例もあり、M&Aについては、誰の視点(ステークホルダー)で、どの期間(短期・長期)をとって検証するかにより、その価値や成否については評価が異なることになる。
したがって、M&Aは、戦略の観点から狙いを明確にし、妥当性の検討を十分に行ったうえで、CEOやCFOが網羅的に企業価値創造を評価して実行する必要がある。そしてその企業価値創造の検討に際しては、何も買収側の話だけではなく、事業売却による価値創造も含めて検討すべきものである。特にこの点は、まだ日本企業には浸透していない。
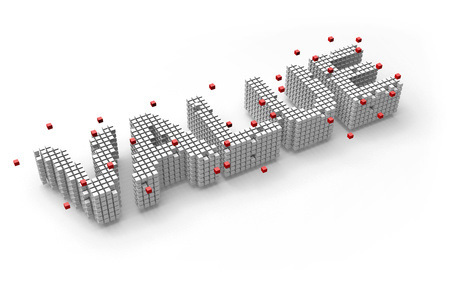 日本で価値創造できたと名言できるM&Aは少ない
日本で価値創造できたと名言できるM&Aは少ない
日本企業においても近年、企業価値評価の手法についての理解度は大きく向上してきていると感じる。日本企業のクロスボーダーM&Aが増加する中で、実際に案件を経験した人材が増えてきており、投資銀行などの出身者を積極的に採用し組織スキル強化に努めている企業も多い。
ただ、企業価値評価を実施するスキルは向上してきたものの、M&Aをツールとしてうまく活用することができている企業はいまだ少ないというのが筆者らの感覚である。M&Aを成功させるためには、手法そのものに対する習熟だけではなく、M&A検討にかかわる全体の検討プロセスについて、より幅広い視点から検討を進めることが必要である。本稿では、マッキンゼーのこれまでの日本におけるM&A支援の経験から、日本企業のM&Aプロセスにおける改善点をステップごとに議論してみたい。
ステップ0:M&Aプロセスの全体像
M&Aのプロセスは、成長戦略の一環としてM&Aを検討するところから始まる。そして、ターゲット会社の選定、デュー・ディリジェンスを経たのちに売買契約書を締結、そののちに発生する事業統合、買収後マネジメントプロセスまでを含めて考えるべきである。
事業買収プロセスの前段階では、全社戦略の特定、そこからの買収戦略の策定、そして、買収対象会社の特定とその評価を行う。そもそも、M&Aが成長戦略の結果として本当に必要とされているのかどうか、疑わしいケースがある。事業環境を十分に精査したうえで、M&Aが戦略的に求められていることを確認したうえで案件を検討すべきであり、円高だから、余剰キャッシュがあるから、という理由だけでM&Aの検討を進めることは非常に危険である。
買収実行時には、デュー・ディリジェンス力とそれを交渉や買収価値に反映させるスキルが求められる。膨大な資料の中から、バリュー・ドライバーに直結する情報を引き出し、価値算定式に織り込むことが求められる。客観的な見地から、会計・法務だけでなく、ビジネス自体についてのデュー・ディリジェンスを実施することが必要である。また、最後に、買収後の統合プロセスにデューディリジェンスの結果を反映させて、想定されたシナジーを実現し、リスクを回避する統合プロセスを進める必要がある。
ステップ1:戦略策定から対象会社の特定まで
日本企業では、M&A案件の検討にあたって、社外の第三者から持ち込まれるものを検討するという受け身の姿勢であることが多く、自社から能動的にM&Aのターゲット企業を発掘していくということが、まだまだなされていない。持ち込み案件は、かならずしも戦略と十分にリンクするものではなく、その結果、買収後の経営がうまくいかないような場合に、「そもそもなぜ買収したのだろうか」というような疑問すら生むことになってしまう。いったいどのような買収候補がいるのかということすら理解しないまま、持ち込み案件に飛びつく、というようなことさえ発生してしまっている。
加えて、投資銀行、投資ファンド、コンサルティングファーム等の情報ソースとの付き合い方・使い方の経験が乏しく、特に、投資ファンド等のFinancial buyerとどのように付き合っていくかに戸惑っている、あるいはうまく付き合いきれていない場合が多いのが日本企業によく見られる特徴である。
ステップ2:デューディリジェンスの実施
客観的ビジネスDDの不足
日本では、DDがどうしても会計・税務および法律の面からの分析に偏ってしまっていることが多い。客観的なビジネスDDという概念をしっかり持ち、それを実践している日本企業は少ないのが現状であろう。
さらに、ビジネスDDを社内の事業部等が担当することが多いため、市場成長や競争環境を客観的な視点で分析することを徹底できていない。そのため、希望的な観測に基づいてしまうことがあり、マネジメントケースについて十分に、かつ、建設的にチャレンジすることができないままとなってしまう。
また、日本企業においては、ビジネスDDだけではく、M&A案件自体の責任者が事業部にあるケースが散見され、対象企業の技術や製品について、どうしても魅力あるものとしての評価にバイアスがかかる傾向にある。そのため、クリティカルな技術や製品についても、その判断を楽観的観測に基づいて行ってしまうことになりがちである。
バリュエーションにおける相場感覚の不足
自社が競合他社と比べて、市場からどのような評価をされているのかという疑問をよく経営者の方々から受けることがある。M&Aを実行する際にも、買収対象としている企業が市場からどのような評価を受けているか疎く、適切な手法が社内で定められていないケースも多い。これらの自社・他社のバリュエーションに関して、実際に筆者らは以下の様なケースを目にしてきている。
■自分のピア企業がどこにあたるのか、定義ができていない。競合他社との評価の差について十分な検証ができていない
まず、自社と競合が市場から受けている評価の差について十分に理解できていないケースである。例えば、「自社の売上・利益は競合A社よりも大きいのだから高く評価されているはずだ」という発言を良く耳にするが、成長率や資本の効率性、バランスシートの健全性など、株式価値の要素となる指標について網羅的に把握できているケースは稀である。また、株式市場からの評価に対しても疎く、自社の株価のバリュエーション、競合との違い、その理由を把握できていないことも多い。そのため、数十年前のイメージのまま競合を評価しているケースも散見される。
■買収対象事業のバリュエーションについての認識もできていないため、評価マルチプルが適切でないことも多い
次に、買収対象企業について、バリュエーションを行う際、必ずしも適切でない評価方法を行っているケースが挙げられる。P/E(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、企業価値/EBITDA(有形・無形固定資産償却前営業利益)などのマルチプル評価を自分たちのご都合主義的に活用しているケースもある。また、過去に遡って、買収対象企業がどのようなマルチプルでトレードされてきたかを検証せずに、結果的に割高な買収金額を掴んでしまっているケースもある(シクリカルのトップのバリュエーションで見てしまったケースなど)。
バリュエーションスキルの不足
日本企業も近年企業価値評価のスキルを向上させてきたとはいえ、M&A専属チームを常に設置し実際に経験・スキルを蓄積させてきている日本企業はまだ稀である。そのような体制の下で、買収・売却を、短いデュー・デリジェンスの期間で行い、正しい判断を行うことは至難の技である。こういったスキルの不足により、以下に挙げるような課題がよく見られる。
■DCFのバリュエーションがバリュー・ドライバーベースになっていない
バリュエーションを行う際、買収対象企業(事業)の将来キャッシュフローを予想し、DCFを用いてバリュエーションをすることが一般的である。しかし、大体の場合、企業価値を算出する際に、営業利益率、ROIC、みなし税率、資本効率性などのバリュー・ドライバー(企業価値を大きく左右する要因)がモデルのベースになっていない。そのせいで、どのような前提でキャッシュ・フローを予想しているかが明確でなくなり、モデル作成者の主観が大きく入り込んだ、偏った予想になりがちである。また、このようにバリュー・ドライバーベースになっていないケースでは、あらゆる環境変化を想定したシナリオ分析が困難で、柔軟性の高い経営判断を妨げてしまう。
■割引率について、(インフレキシブルな)社内ルールを画一的にあてはめているケースが多く、案件ベースで適切な設定ができていない
企業価値を大きく左右しがちであるWACCや永久成長率に、社内ルールを画一的に当てはめているケースが多い。例えば、米国の企業であれば、WACC7%、永久成長率2%といった形で、業種やその企業の成長性などは全く加味していないことが多い。このことによって、本来は成長率が高い業種であっても、過小評価されたり、逆に過大評価してしまうリスクがある。
シナジー検討の甘さ
買収対象企業との間に期待されるシナジーを検討する際に、潜在的なシナジー項目を網羅的にカバーしていないケースがある。例えば、サプライチェーンのそれぞれのプロセスで起こり得るシナジー効果を網羅し、バリュエーションに埋め込めていないことがある。具体的には、コストシナジーは重複する事業における人員削減のみを考慮し、共同購買に対する検討を行わないことが挙げられる。
そして、実現性が高いものも低いものも、画一的にディールのバリュエーションに含んでしまっているケースもある。たとえば、不透明な情報で算出した研究開発の効率化等に関しても、最大額をディールのバリュエーションに入れ込んでしまっているケースがある。どこまでをバリュエーションに含むかという見極めがM&A経験が少ないために、不明確になってしまっているのだ。
マッキンゼーでは、買収後のシナジーを描く際に、「Open the aperture(シナジー展開)」というフレームワークを用いることがある。これは、シナジーの方向性を、下記の3つに分けて、それぞれどういったものが有り得るか検討するツールである。
(1)既存事業の保護によるもの
(2)統合効果の刈り取りによるもの
(3)変革機会の模索によるもの
(1)については、既存顧客や販売数量を維持する、人材流出を防止する、といったことが挙げられる。(2)については、重複する間接機能の効率化や、クロスセルの実施などが該当する。(3)は、M&Aを機にオペレーションや事業領域を抜本的に変革するようなシナジーを指す。たとえば、両社ともにこれまで展開していなかった地域へ進出する、一部間接業務を完全にアウトソースする、などである。
こういった新たな事業機会の創出に繋がるシナジーは、既存事業の延長線上にあるシナジーよりも、より大きな企業価値を創出するものである場合が多い。ただ、既存事業の延長線で考えていては、検討から漏れてしまうことも多い。だからこそ、このような包括的な分析を踏まえて、さまざまな可能性を検討しつつ最終的な統合後の姿を描いていくことが必要なのである。
(続きは次回「ステップ3:買収後のインテグレーション設計とシナジー創出について」)