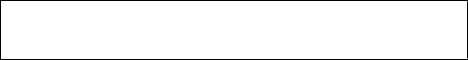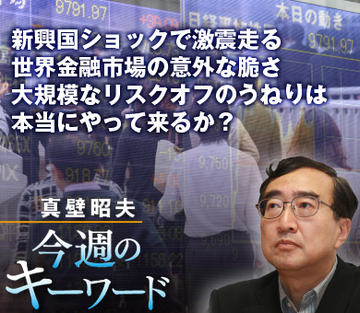米住宅市場の回復の勢いが弱くなってきている。イエレンFRB議長も議会証言でその問題に触れていた。
今回の米経済の回復を牽引してきた重要な柱の一つが住宅セクターであるだけに、当面は注意が必要だ。昨年の途中までは、ファンド筋が積極的に割安物件を購入していた。しかし、FRBが量的緩和策縮小を示唆してから長期金利が急騰し、資金調達コストが上昇した。また、家計のバランスシート調整の進捗とともに、競売に出てくる割安物件が減少してきた。投資家は、「低金利の資金で投げ売り物件を買っていく」という戦術が使えなくなったため、彼らの住宅購入はピークアウトした。
代わりに、景気回復の流れに乗って、個人の買いが増加してくれればよいのだが、その勢いが今ひとつ加速しない。景気回復といっても、その“果実”が富裕層へ集中的に流れてしまい、中所得層の収入がさほど伸びていないことが理由の一つに挙げられる。2000年以降の税引き後の中位所得の伸びは、米国では+0.3%にとどまっている。英国とカナダの+19.7%、オランダの+13.9%、ドイツの+1.4%よりも低い(「ニューヨーク・タイムズ」紙)。
また、高騰し続けている大学授業料の問題の余波が住宅市場に押し寄せてきた、という解釈も見られる。1993年を基準にして、日米の消費者物価指数の大学授業料の推移を見てみよう。今の日本は1.3倍強になっている。一方、米国の大学授業料は3.3倍だ。
親が通常の会社員の場合、米国では親が子供の大学の費用を負うことは一段と難しくなっている。このため、学生ローンの借入額が増加する大学生が多くなっている。卒業後に多額の負債を抱えたカップルの場合、住宅ローンを申し込んでも断られるケースが近年多い。