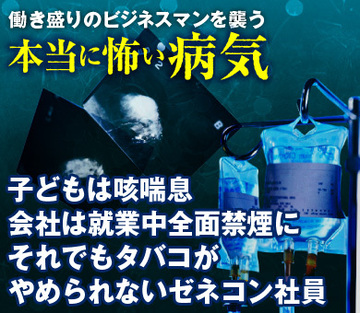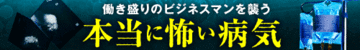妻の突然死から、抗うつ剤でも治らない
“落ち込み”を体験したLさん(55歳)
定年を前に、
妻が突然亡くなる
Lさんが会社の同僚の送別会を終えて、自宅インターフォンを押したのは夜中の12時過ぎだった。インターフォンを押しても、返事が無いので鍵を使って家に入ったが、いつもとなにかが違う。違和感を持ちながら居間の蛍光灯のスイッチを入れると、あおむけに倒れている妻の姿が目に飛びこんできた。Lさんは直感でわかった。「もう息をしてない」と…。
こんな夜中にどうしてよいかわからないが、とりあえず救急車を呼んだ。救急車を待つ間に、東京で住んでいる2人の娘に連絡をした。サイレンを消して自宅に来た救急隊員に言われた。
「残念ですが、お1人で亡くなっているので、検死のお医者さんを呼びます。その方に相談してください」
夜中に娘2人が駆け付けた。それから、葬儀までの慌ただしさはあまり覚えていない。しかし自分がしっかりしなければならない。泣いてはならないと心に決めていた。涙を見せずに初七日までをのりきった。
妻が亡くなって1週間。そろそろ会社に出社しなければならない。Lさんは定年を間近に控えていたため、残業の多い営業から毎日ほぼ定時に帰宅できる庶務に異動していた。
この数ヵ月は家での夕飯の機会も増えていた。千葉県に自宅を構えて15年。2人の娘が働きはじめたことで、Lさん夫妻の家計もやっと落ち着いてきた。姑の介護も終わり、娘2人を社会に出したことで「やっと夫婦2人で水いらず、のんびりできる」と思った矢先の“最愛の妻の死”だった。「最近頭が痛いと言っていた妻の声をもっと真剣に聞くべきだった」、そう後悔し続けた。
四十九日の後、
突然の不眠に襲われる
葬儀後、会社に復帰したLさんに周囲はとても優しかった。東京に住んでいた娘たちも自宅に戻ってきてくれ、何かと気遣ってくれる。
しかし、どんなに優しくされても、慰めの言葉をかけられてもLさんは、いつも夢の中にいるようだった。昼間は気丈にふるまっているが、夜が辛い。1人で和室に布団を敷いて寝ていると、闇のような不安と寂しさが襲ってくる。