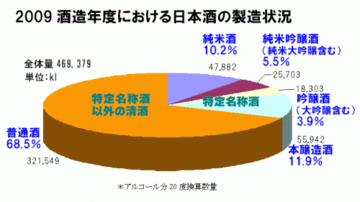「酒なんてどれも一緒。夏でも酒は燗して飲むのが当たり前の土地柄だから、味の違いなんてわからないって」
2001年9月、秋田県庁・食品産業振興チームから「消費者は今どんな酒を望んでいるのか。日本酒のトレンドについて県の酒造組合でレクチャーをお願いしたい」との要請を受け、有給休暇を取って秋田へ飛んだ。
冒頭のコメントは、当時30代の県庁職員A氏に「Aさんが秋田の酒でよく飲む銘柄は?」と尋ねた際に浴びせられた、痛烈な先制パンチだった。
“護送船団”的な空気が
支配していた秋田の酒造界
 純米吟醸無濾過生原酒 袋吊り〔季節限定品〕
純米吟醸無濾過生原酒 袋吊り〔季節限定品〕3,000円(1.8L/税込み) 720ml(1,500円/税込み)もある。*価格は送料の関係で店ごとに異なる
酒造組合の会議室には“美酒王国秋田”(=秋田県酒造組合のキャッチフレーズ)の蔵元5社が列席されていた。「新政」「太平山」「飛良泉」「福乃友」のトップと「大納川」の専務を前に日本酒おたくの御託を並べた。
「地酒に力を入れている東京の料飲店では今、秋田の酒がほとんど置かれていない」
「秋田ブランドの酒を指名して注文する人は東京ではまず聞かない」
「お隣の山形県からは『十四代』という新星が現れて首都圏で大ブレークし、山形県酒を牽引している」
「米どころ、酒どころという好イメージと、清冽な水、寒冷な気候という酒造りに適したインフラが秋田には備わっているのだから、消費者に『秋田の酒はたいしたことない』といわれる前に、全国区で通用する旨い市販酒を造り出してほしい」
蔵元の反応はおしなべて冷ややかだった。
「東京のトレンドはそうなのかもしれないが、ウチの酒は地元ではよく飲まれている」
「東京と秋田では給与格差があり、秋田で高い酒は売れない」
「売れ筋の吟醸酒を造らないわけでもないが、東京に出荷して売れなかったらリスクが高すぎる」