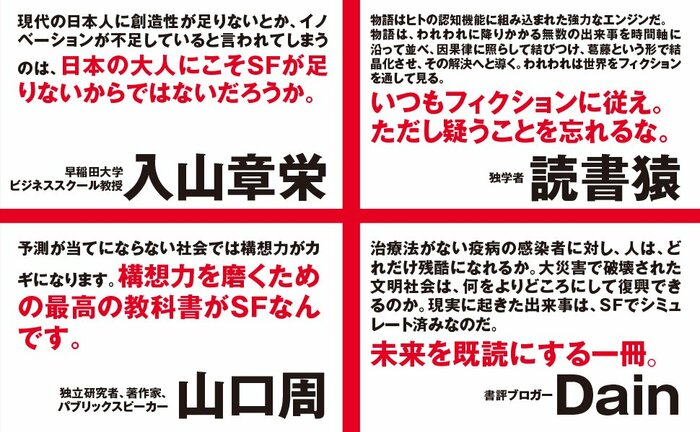『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。今回は、夏休み特別編。都知事選以降に有名になった「あの人の小説」を紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
安野たかひろは、新進気鋭のSF作家でもある
2024年、東京都知事選で無所属ながらもテクノロジーを前面に押し出した提言から選挙運動の構築で大きな話題をさらった安野たかひろ。その経歴は開成高校卒業後東京大学、その後ボストン・コンサルティング・グループを経てAIスタートアップ企業を二社創業とエリート中のエリートといった華々しいものだが、実は文芸方面の実績もある。1万文字以内と短めの小説賞の星新一賞受賞者であり、中長篇小説の公募賞であるハヤカワSFコンテストの優秀賞も受賞と、新進気鋭のSF作家でもあるのだ。
都知事選立候補時の単著はハヤカワSFコンテスト受賞作の『サーキット・スイッチャー』のみだったが(短篇として、「小説すばる」掲載でディープ・フェイク技術とVTuberがテーマの「ディープ・フェイカーズ」とアンソロジー『AIとSF』所収の国産大規模基盤モデルがテーマの「シークレット・プロンプト」がある。)、つい先日(7月16日)、最新長篇が早川書房から刊行されたので、今回は本作(松岡まどか、起業します)をメインに紹介していこう。安野貴博はその経歴からAI関連技術全般への造形が深く、『サーキット・スイッチャー』も完全自動運転が実用化された2029年の至近未来を舞台にして、自動運転のアルゴリズムがもたらした悲劇と、オープンソースの可能性を描き出す作品で、著者の知識と思想が遺憾なく発揮された長篇であった。
スタートアップ立ち上げの「意義と絶望」を描くAIエンタメ長篇
それに続く新刊『松岡まどか、起業します AIスタートアップ戦記』は、副題の通りAIについての話だが、そのテイストは前作と比べると大きく異なり、一言でいえばビジネス書寄りの小説になっている。とはいえお勉強に終始しているわけでもなく、スタートアップで重要なことは何なのか、またどうやって資金調達を成立させるのか。プレゼンをどう決めるのか、仲間を集める過程でどのような困難があるのか──が、おそらく自身の実体験も踏まえながら詳細に描かれていて、胃の痛くなる臨場感が伝わってくるスタートアップ戦記に仕上がっている。
物語の舞台はほぼ現代。日本有数の大企業である「リクディード」社のインターン生だった女性大生の松岡まどかが主人公だが、彼女は社内の派閥闘争に巻き込まれて大学4年生の3月という一番ぎりぎりのタイミングで「内定切り」を食らってしまう。しかし彼女には就職以外にも「プランB」があって──と、スタートアップの設立に踏み出すことになる。というのも、松岡は少し前にビジネス用のSNSで、ある企業の創業者からコンタクトされ、コーヒー一杯1000円超えのカフェで会い、そこで「松岡さん、スタートアップを作るんだ」とアホほど胡散臭い勧誘を受けていたのだ。
「そうすれば、自分らしく働ける。会社のやり方にとらわれたり、搾取されたりしない……あ、そもそもスタートアップが何かはわかるかね?」
松岡は曖昧に首を横に振った。
(……)
「短期間に成長しようとする企業をスタートアップというんだ。起業する人はたくさんいるけど、殆どの会社は急成長なんか目指さない。例えば脱サラしてカフェをはじめる人は多いけど、ああいうのはスタートアップとは言わない」(p.35)
でも、スタートアップなんて私にできる気がしません……というと、むしろまともに働いたことがない今は従来の考えにそまっていないからこそいいんだとか、ザッカーバーグもイーロン・マスクもジョブズもゲイツもみんなろくに新卒で就職なんかしてないとめちゃくちゃな説得を受け、最終的に札束を見せられすぐにそれを出資しようと言われてしまう。その場では即答を避けた松岡だったが、内定切りにあった衝撃からこの提案を受けることと衝動的に決断し契約書にサインをしてしまう──。
当然彼女はほぼ騙されていた。その契約では買取請求権(期待する成長が見込めなくなった場合、株式を創業者が買い取らないといけない)が設定されていて、契約締結日から一年で出資時の時価総額の100倍になっていなければならない。それが達成できなければ、一億の借金を背負うことになっていた──という冒頭から、ゼロから立ち上げた企業を一年で10億規模の会社にスケールさせるビジネス戦記が始まるわけである。
魅力1:スタートアップあるある「主人公がどんどん嫌なやつになっていく」
起業するっていってもやりたいことがあるわけでもない女子大生が何を? と思うところだが、松岡は普段から自分の周囲の音を全部学習させたAI群を育て、開発するのが趣味であり──と、AIを活用したビジネスモデルの構築を模索していく。冒頭の展開やその後訪れる危機の数々(古巣のリクディードから嫌がらせを受けたり、ランサムウェア攻撃を食らったり)は都合が良いものばかりで、このあたりのテイストは「もしドラ」などの小説系ビジネス書感が強い(実際勉強になる面も多い)。
ただ、もちろんそれだけの小説ではなく、先に書いたようにお仕事ものであったり、スタートアップものとしての魅力もたくさんある。
たとえば松岡は最初AIに詳しいちょっと有能な女子大生程度の女性で大半のことがうまくできない。会社をどうしたいかというビジョンもないし、ピッチ(投資家、出資者へのプレゼン)も下手だし、自分がトップなのに社員に敬語で話しかける。
しかし、これではスタートアップを成立させることは難しい。中心的なエンジニアは絶対に有用な人物が必要だし、おどおどして自信がなさそうならついてくれるわけもない。松岡自身がリクディードインターン時代から「定時で帰りたい」人間だったが、一秒を争うスタートアップで毎日定時に帰らせられるわけもない。
そのため、女子大生だった松岡はだんだん嫌なやつになっていく。たとえば、自社(ノラネコ)のエンジニアの採用を行っている時、面接を行っていた松岡が「働き方はどんな感じなんですか?」と聞かれて、みんな長時間労働をしていることから「ありのままを伝えることはとてもできないぞ」と考え、『少なくとも、意に反して長時間労働させられてる人はいません。立ち上げ期なんで忙しいときもありますが、将来的には働きやすさを重視した組織づくりをしようと思っています』(p.175)と「嘘は言ってない」ラインで返答するところなど、嫌なリアリティがある。
スタートアップをチーム足らしめているのは未来への期待だから、自分自身が未来への希望を持てなくても希望があるように振る舞って明るい顔をし続けなければいけない。舐められないようにメイクをし、へらへらと笑わないようになり、出会った人をみな人材として評価し、常に頭の中で採用可能性をジャッジするようになる。社員の感情に細かく付き合うこともなくなり──と、事業を継続させるためにだんだん嫌なやつになっていく過程がじっくりと描きこまれているのである。
魅力2:「事業のシミュレーション」がリアル
とはいえそれでどんどん松岡が嫌なやつになるだけの小説だと胸糞が悪いだけなので、本作ではきちんと希望も描き出されていく。彼女たちの事業はリクディードと競合する採用分野でのAI活用(最初はAIヘッドハンター)から始まり、次第に会社の理想──技術で、人に寄り添い、人を助ける──が固まってきて、いっぱしの経営者として、事業として、芯を太くしながら成長していくのだ。
このあたりは(小説、フィクションである以上著者を過剰に重ね合わせるのは危険だけれども)著者の思想が垣間見える部分であり、都知事選で安野たかひろを知った人にとっても興味深い部分かもしれない。事業が具体的にどのような内容なのか、採算がとれそうなのかといったシミュレーションも細かく描きこまれていくので、そのあたりを楽しみに読むのもいいだろう。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からのスピンアウトです。