ファミリーマートが“自発的”企業へと脱皮し、強くなりつつある。その立役者は、親会社の伊藤忠商事から来た上田準二社長だ。「業界三番手、でも中身は三流だった」。成長が踊り場を迎えたコンビニエンスストア業界で、辛らつな言葉を笑顔で発しながら、上田社長はファミマの何を変えたのか。(取材・文/『週刊ダイヤモンド』編集部 新井美江子)
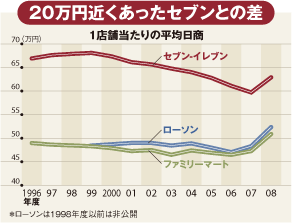
「本部とは、誰の、どういう考えを指すか理解できているのか」。上田準二社長の改革は、この問いかけから始まる。
2000年前後、コンビニエンスストア業界は、“市場の成熟化”という見えない敵に、初めて直面した。
業界3位のファミリーマートは、1998年度から既存店売上高が前年割れに陥落。一店舗当たりの平均日商も下落し続け、首位のセブン‐イレブン・ジャパンとの差は20万円近くにまで拡大した。
そんな状況に危機感を募らせた筆頭株主の伊藤忠商事が2000年、ファミマ立て直しのため、顧問として送り込んだのが上田現社長だ。
顧問当時、伊藤忠時代からの現場主義を貫き、スーパーバイザー(加盟店に対して経営・営業指導する社員。SV)とともに、半年にわたって店舗を回った上田社長は、SVが指導相手の加盟店に向かって発していた言葉に愕然とした。「本部が言ってるんで、お願いします」。
「なぜその指導が必要なのか、理由を説明できているSVがいない。会社の戦略が伝わっていない証拠だった」(上田社長)
02年、現職に就任した上田社長は、改革を断行する。その1つが、社の戦略の徹底共有を実現する組織体制の確立だった。
まず、社長と社員、社員と加盟店などのコミュニケーションを強化するため、“ディストリクト制”に組織を転換。地域編成を再分化し、ディストリクト(地域の管理部署)の数を増やして一ディストリクト当たりの統轄店舗数を約600店舗から約350店舗に減らした。



