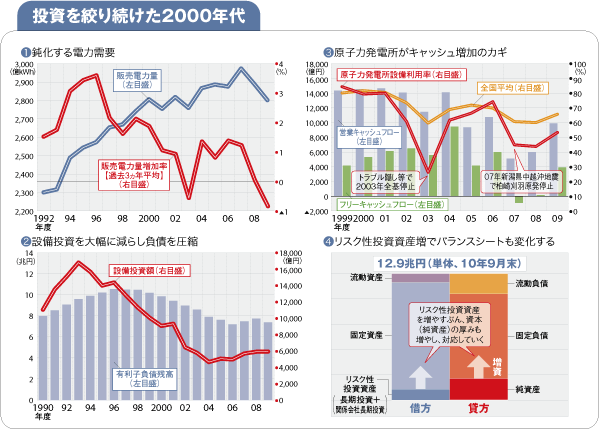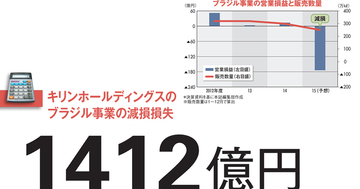海外へ最大1兆円の投資を盛り込んだビジョンを発表し29年ぶりの大規模増資を実施した東京電力。地域独占の企業体がなぜ海外か。そこにスリム化の果てに成長の糧を失った巨艦の危機感があった。
「かつては英語が話せるよりも(原子力発電所と関係のある)新潟弁や福島弁がうまいほうが評価された」(東京電力国際部関係者)
そんな東電も目下、海外事業を支える人材の確保や育成に力を入れ始めた。昨秋に発表した「2020ビジョン」では海外事業を中心に最大1兆円を投じることを明言。2020年度には海外を主とした成長事業だけで経常利益1200億円を稼ぎ出す計画だ。連結後の最高益4412億円(06年度)と比べればその大きさがわかる。さらに低炭素化に向けた2兆5000億円規模の投資も行う。柏崎刈羽7号機以来20年ぶりとなる東通原発1号機(17年運転開始予定)などが主な対象となる。
11年5月に還暦を迎える東電にとってこのビジョンの意味は大きい。徹底した守りの経営から攻めの経営への転換宣言にほかならないからだ。東電幹部は「人口が減少するなか国内のパイを奪うか海外に目を向けるしかない」と言う。東電の屋台骨を支えてきた電力事業の構図をふかんしてみよう。
もともと国内の電力会社は「燃料調達→発電→送配電→売電→料金回収」まで一貫した事業を行っている。経営の要は電気を使う顧客を増やすことと、発電所や送配電線といった設備に投資していかに効率よく回収するかだ。東電は09年度、約2860万の顧客に全国の33%に当たる2802億キロワット時の電力を販売。約13兆円に上る総資産を力の源泉にして、約5兆円の売上高につなげている。だが、成長の糧となる電力需要はもはや限られてきた。
図(1)にあるとおり、販売電力量の増加率(過去3ヵ年平均)は1996年度の3.6%から09年度にマイナス0.8%に落ち込んだ。供給計画では19年度に約3200億キロワット時になるとうたうものの、年平均1%の伸びにすぎない。
電気が重要なエネルギーであることは言うまでもない。そのため費用に対し一定の利益が出る電気料金の仕組みと地域独占が認められ、コスト意識そっちのけで多額の設備投資を続けてきた。図(2)のように東電も93年度に設備投資額が1兆6800億円と頂点を迎えた。有利子負債は96年度に10兆5300億円までふくれ上がり、自己資本比率は10%に低下した。