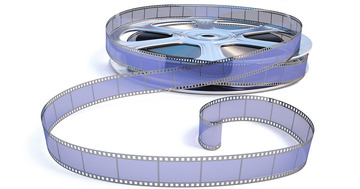墨職人・伊藤亀堂 Photo by Takeshi Shinto
墨職人・伊藤亀堂 Photo by Takeshi Shinto
油を燃やして採取した黒色の煤と、動物の骨や皮でからなる「にかわ」を煮て混ぜ、香料で香りをつける──。1200年にも及ぶ墨づくりの伝統が今、消滅の危機に瀕している。最大の産地の一つである三重県鈴鹿市で最後の1人となった墨職人・伊藤亀堂の仕事と思想を追った。(取材・文=武田鼎)
「飽き性」サラリーマン
職人の世界へ入る
朝3時半。真っ暗なうちから伊藤亀堂の仕事は始まる。昼過ぎまで、ひたすら墨を作り続ける。手の感覚はほとんどなくなるほどの寒さだ。墨作りはカビが大敵。気温が低い10月から4月の早朝に作らなければならない。作業場には原材料となる煤が舞う。壁という壁が煤につもり、10分もいればすぐに顔中煤まみれ、鼻の穴の中まで真っ黒になる。
祖父の代からこの作業場で墨を作り続けるのが3代目になる伊藤亀堂だ。1200年にも及ぶ墨づくりの伝統を守り、墨職人としては唯一、国から「伝統工芸士」として認められている。くわえタバコで一服する様子はいかにも「職人」といった風情が漂う。
亀堂が「墨の世界」に入ったのは今から32年前、20歳の時のことだ。当時、鈴鹿の町には50人以上もの墨職人が集い、大賑わいを見せていた。高校を卒業してサラリーマンとして自動車業界で働いていたが、「1人で墨作りをする親父がね、なんかきつそうだったんですわ」。そこで土日に「軽く手伝おう」という気持ちで墨作りを始めたところ、その奥深さにのめり込んでいった。「21歳になる前にスパッと辞めてね。親父に弟子入りです」。懐かしそうに振り返る。