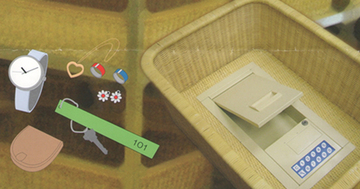「あれは、泣ける本でしたねー」と、花田雄一さん(仮名)が言う。
「そんなに泣けましたか」
「特に、主人公が特定産業振興法を成立させようとして燃えるところ。それと何でしたっけ、主人公が最後に言うセリフ……」
「離れること、忘れることの難しさ」
「そう、それです。まさに泣けちゃいます」
小説『官僚たちの夏』に見る
経済成長下の通産官僚の建前と本音
時は1960年代のはじめ、旧通産官僚たちは必死で「あること」を心配していた。
「日本の産業界は、いまや総力をあげて外資を迎え撃たねばいかんところへ来ている。みんなが自分のことばかり考えていたのでは、日本は滅びる。戦争中と形こそちがうが、挙国一致のときなのだ。国家総動員の精神で行かんと、日本は立ちゆかなくなりますぞ」
『官僚たちの夏』(城山三郎著、新潮文庫)のなかで、主人公の風越信吾は財界関係者に向かい、こう呼びかけた。風越のモデルは、実在した大物官僚だ。その風越を中心とするグループが日本と日本経済の行く末を按じ、満を持して国会に提出した法案が「指定産業振興法」。実際には「特定産業振興法」という。
法案の狙いは大きく2つある。建前で言えば、それは迫り来る自由化と外資の攻勢に対抗するため、国内産業の合併と資本増強を促し、国際競争力を強くするための法案だ。が、小説では、こんな通産官僚の本音も描写されている。
「すでに許認可権の多くを手放した通産省としては、行政指導という政策手段が中心になる。だが、これだけでは、いかにもたよりなく、心もとない。法的な裏付けもないし、全体的な展望も持てなくなる。金で動かそうにも、省の予算は、各省中ドン尻に近く、たとえば農林省にくらべて、十分の一にすぎない。もはや、ムチもアメも持たぬ無力な状態であった」
安月給で昼夜を問わずモーレツに働く通産官僚たちは、アメリカ政府からは「ノートリアス(悪名高き)」と揶揄されるほど恐れられていた。ならば、国内ではそれだけ頼りにされていたかというと、そうではない。1960年代に入る頃には、財界を中心に「通産省無用論」まで叫ばれていた。
高度経済成長を突き進む日本、そして日本企業には、外資であろうが資本は資本という割り切りが芽生えつつあった。自信をつけた財界、とりわけ、通産省による新たな融資規制を恐れた銀行の幹部たちは、官僚によるこれ以上の統制を嫌がり、法案反対へと動いた。
1963年、官僚たちの必死の根回しにもかかわらず、法案は審議未了で廃案となる。