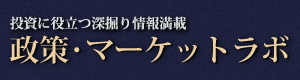4月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、国債購入の上限撤廃などの追加緩和を決めた日本銀行 写真:つのだよしお/アフロ
4月27日、新型コロナウイルスの感染拡大を巡り、国債購入の上限撤廃などの追加緩和を決めた日本銀行 写真:つのだよしお/アフロ
「最後の貸し手」。経済危機時に民間が萎縮してお金の流れが凍結したとき、中央銀行が平時とは異なるスタンスで資金の貸し出しや債券購入を行う役割のことだ。
新型コロナウイルス禍が経済に与える打撃を和らげるため、現在先進国の多くの中銀が「最後の貸し手機能」を全開で発揮している。しかし、どの程度異例なことが行われているのかを認識しておく必要はあると思われる。
歴史を振り返ると、「最後の貸し手」という概念が定着したのは1873年に英国人のウォルター・バジョットがその必要性を強調した『ロンバード街』を出版した後である。それ以前はダーウィンの『種の起源』が1859年に出版されたことに象徴されるように、経済界でも「自然淘汰」「適者生存」の原則を重視する思想が欧州では強かった。安易な救済策はモラルハザードを助長するという懸念もその背景にあった。
それに対してバジョットは恐慌時には中銀が市中に資金を潤沢に貸し付け、信用の収縮を防ぐべきだと主張した。ただし彼が提唱し、その後定着した「最後の貸し手」のルールは、当局からの融資は全ての希望者に対して望む金額を、健全な担保の範囲内で、懲罰的なレートで実施されるべきだ、というものだった。
つまり、危機下であっても無制限の大盤振る舞いは許容されないとバジョットは考えていたのだ。それを認めると、中銀に深刻な貸し倒れの損失が生じ、最終的には国民は増税によってそのコストを負担することになってしまうからである。