
加藤 出
「日本国債は一度もデフォルトしていない」「自国通貨建てなら国債は安全だ」。積極財政論を支えるこうした言説は、形式に偏った危うい理解にすぎない。戦後日本は、インフレによって国債の実質価値が大きく損なわれる“インフレ税”という形で、実質的なデフォルトを経験しているからだ。衆議院解散を機に積極財政継続の観測が強まり、日本でトラス・ショック型の混乱が起きれば、英国以上に深刻化する恐れがある。

パウエルFRB議長は9月の講演で株価の高水準に言及し、10月FOMCでの利下げは「データ次第」と述べた。7月会合では株価収益率(PER)や社債スプレッドの過熱に警戒が示され、9月には国際決済銀行(BIS)も、世界的なリスク・オン持続に懸念を表明。だがトランプ政権は大幅利下げを迫り、中央銀行の独立性を揺さぶっている。独立性が崩れた先に何が起こり得るのか。その一端はトルコの経験が物語り、日本銀行にとっても決して人ごとではない。

米中関税合意で不確実性は一時緩和したが、米国経済の先行き不透明感は強い。日本は日銀の低金利政策による円安と生活コストの高騰、膨張する国債発行に直面し、適切な対応がなければ「トラス・ショック」のような深刻な経済危機の再来が現実味を帯びつつある。

米FRB(米連邦準備制度理事会)が利下げをした一方、日本銀行は12月19日に政策金利の引き上げを見送った。日銀は「賃金と物価の好循環」が遠のくことを恐れて利上げに慎重だが、日本経済にとっては逆効果になる可能性が高い。
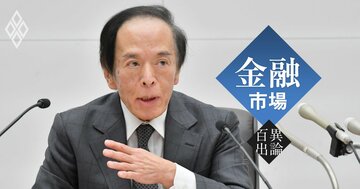
スイスの最低賃金は4300円前後と、日本の約4倍だ。高給が実現できる背景を分析すると、日本経済に何が必要なのかが見えてくる。

日本では通常、新紙幣が発行された後も、旧紙幣は引き続き使える。ところが海外の事例を見ると、一定期間たった後に旧紙幣の法的通用力が失効する国もある。その成功事例と失敗事例から、日本でも旧紙幣を使えなくするよう前向きに検討すべき理由を解説する。

3月18日~19日の金融政策決定会合で、日本銀行はマイナス金利の解除などを決定した。今回の利上げ局面は、直近2回の利上げとの環境の違いや、米国の金融政策の動向をつぶさに観察すると、次の利上げ時期は10月より早まる可能性も浮上する。

1月22日~23日の金融政策決定会合で、日本銀行はマイナス金利の解除を見送り、大規模な金融緩和政策を維持した。日銀のメッセージから、マイナス金利の解除の時期は近づいており、金融政策正常化に向けて動き始めていることは歓迎できる。ただし、「賃金と物価の好循環」という説明には危うさがある。

#21
日本銀行の植田和男総裁は金融政策の修正を進めてきたが、そのペースは海外から遅いと見なされている。金利上昇に注目が集まる2024年、日銀の金融政策はどうなるのか。政策修正の時期と条件を予測しよう。
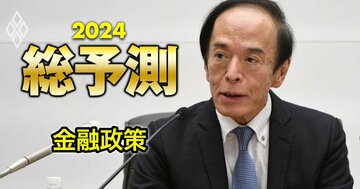
10月31日の金融政策決定会合で、日銀はYCCを再修正した。一定の評価はできるものの、海外投資家の目には別の姿が映る。

植田和男日銀総裁がYCC(イールドカーブ・コントロール)政策の柔軟化に動いた。ところが、政策修正後は円安に動いている。中央銀行の慎重で曖昧な姿勢は、別のリスクを浮上させることにもなる。

植田和男日銀新体制が発足して約2カ月が経過した。この間、円は対ドルで6%も下落、物価はなお4%を超える高水準にあり、市場関係者の間では「黒田東彦前総裁と実はあまり変わらないのでは」という不安が渦巻いている。インフレをあえて無理に2%へ押し上げる必要はないというスイス中央銀行の主張をひもとくと、日銀の説明との違いが鮮明になる。

日本銀行が10年間、超低金利で国債を買い続けたことは何を意味するのか。戦前に高橋是清が講じたリフレ政策と当時の経済状況、経済誌の論考を手掛かりに探っていこう。

日本銀行の総裁に、経済学者の植田和男氏が就任する見込みだと報じられた。『週刊ダイヤモンド』2014年5月3・10日合併号における植田和男氏と私の対談で、植田氏は異次元緩和後の出口の難しさを吐露していた。

日本の物価上昇率が、41年ぶりの高水準で推移している。中でも生活必需品は全体以上に顕著だが、日本銀行は物価見通しが低いことを理由に、長期金利を低く抑えるイールドカーブ・コントロール(YCC)政策を継続している。日本経済の将来を考えると、その弊害はあまりにも大き過ぎる。

#4
突然の「長期金利の許容幅拡大」によってマーケットを驚かせた日本銀行。だが、異次元緩和の出口に向けて、次なる施策の余地は小さいと東短リサーチの加藤出氏は予測する。超低金利に慣れ切った企業や家計は金利の大幅な上昇に耐えられない。また欧米諸国の景気後退は日本経済を冷やし、日銀の手足を縛る。

#6
2022年は世界的なインフレを受けて各国中央銀行が利上げに踏み切る中、日銀の黒田東彦総裁は政策変更を拒み続けた。23年春の任期満了に伴う体制刷新で、長期金利固定の終了はあるのか。金融政策を転換する時期と条件を検証した。

今の日本銀行の金融政策に対して、国民はもっと怒りをぶつけていいのではないか。不必要な円安圧力をかけて国民の実質的な購買力を奪い、政府の政策パッケージとの矛盾も隠しきれなくなっている。日銀はインフレ目標を大義名分にしてこの政策を続けていくつもりだが、同目標の正当性を否定する歴史的、国際的な研究も世界中に幾つも存在している。日本国民にとって本当に望ましい経済・金融政策を議論すべき時期だ。

日本は、日本銀行による異次元金融緩和の長期化が原因である「わな」にはまり、抜け出せなくなっている。そのことは、最近特に問題視されている日本の賃金が上がらない要因にもなっている。今の日本が陥っている深刻な悪循環の実態に迫る。
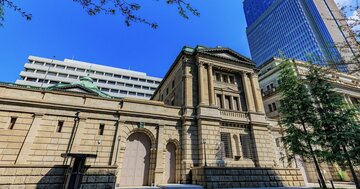
多くの国々がインフレ・値上げに苦しみ始め、「利上げラッシュ」の様相を呈している。その中でも日本銀行は大規模な金融緩和の継続を表明。長期金利を0.25%以下に抑えつけ、事実上の“固定相場制”に留め置く方針だ。世界各国の金利上昇幅と比較すれば、その異様さは際立つ。日銀がどれだけの窮地に立たされているのかを分析する。
