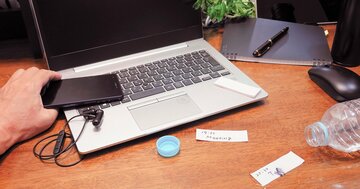変化に対して悲観的すぎても楽観的すぎてもいけない。自分はどう生きたいのか、私たちはどんな選択をするべきなのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
変化に対して悲観的すぎても楽観的すぎてもいけない。自分はどう生きたいのか、私たちはどんな選択をするべきなのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
レビュー
2020年のコロナショックで、私たちはさまざまな我慢を強いられた。目に見えぬ感染のリスクに怯え、世界中で大規模な経済活動の縮小が起きた。つらい状況にはちがいないが、発見もあった。新型コロナウイルス感染防止対策として在宅勤務に切り替える企業が続出した。オフィスに行かなくても仕事はできるということを、多くの人が実感したのではないだろうか。
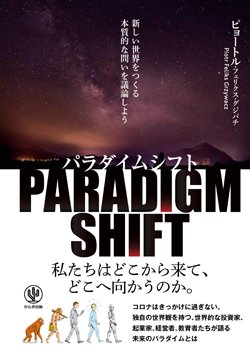 『パラダイムシフト 新しい世界をつくる本質的な問いを議論しよう』 ピョートル・フェリクス・グジバチ著 かんき出版刊 1760円(税込)
『パラダイムシフト 新しい世界をつくる本質的な問いを議論しよう』 ピョートル・フェリクス・グジバチ著 かんき出版刊 1760円(税込)
コロナ危機をきっかけとして、いたるところで既存のパラダイムに大激震が走った。こうしたタイミングこそ社会の問題と向き合い、本質的な「問い」について考えるチャンスだと著者は主張する。本書『パラダイムシフト 新しい世界をつくる本質的な問いを議論しよう』には、そうした「問い」のもとに未来を切り拓く投資家、起業家、教育者など21名のインタビューが掲載されている。
彼らの声は、働くことや教育のあり方、そして自分自身の生き方まで幅広い視点から本質に迫り、新たなパラダイムへと向かう私たちの背中を押してくれる。
パラダイムが変わると、判断の物差しも変わってしまうため、新しいパラダイムは受け入れがたいものだ。また、世の中が激変しているときには認知バイアスによって思考が偏りやすい。だからこそ、バイアスの存在に自覚的であることは、適切な意思決定をするうえできわめて重要だ。