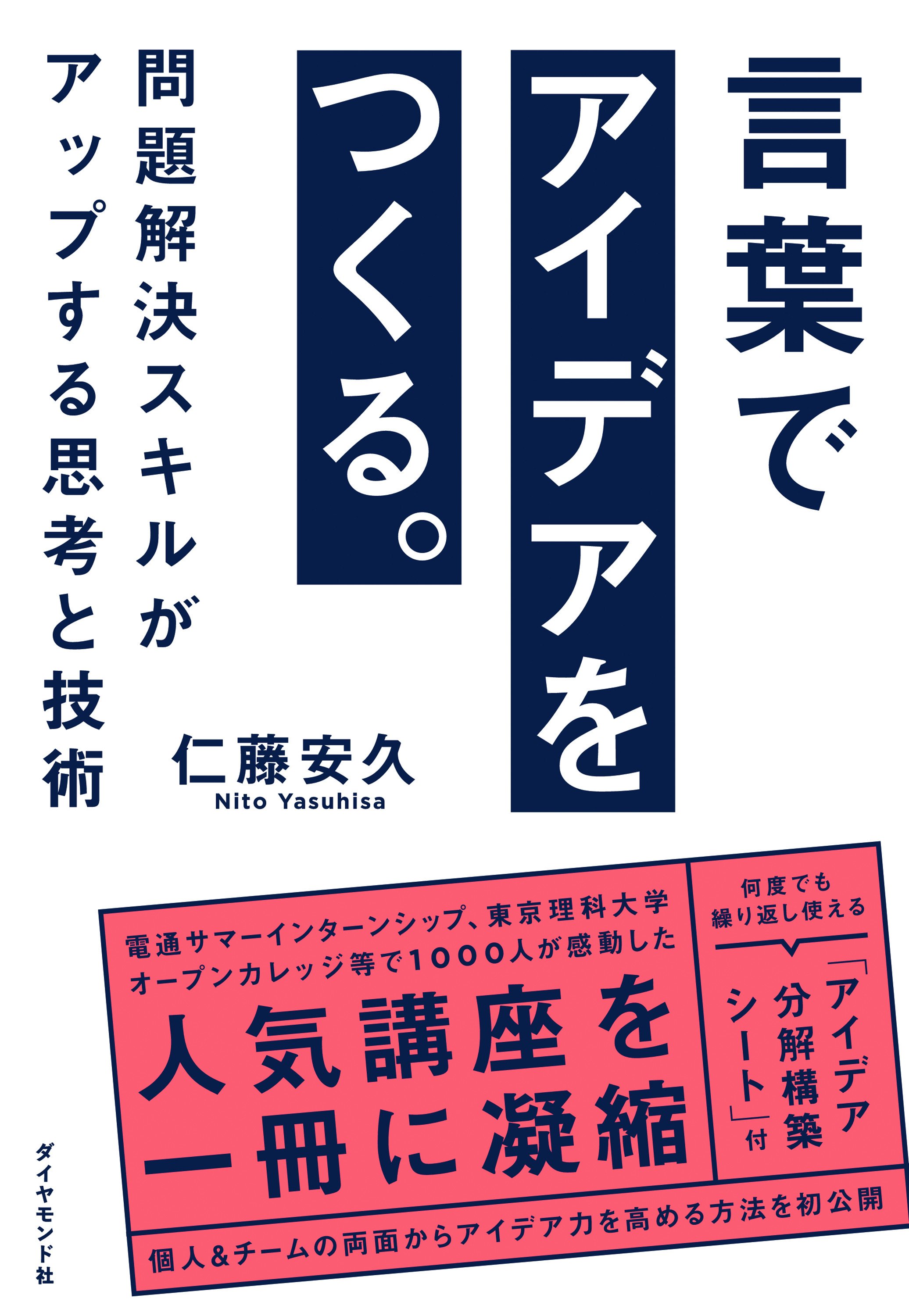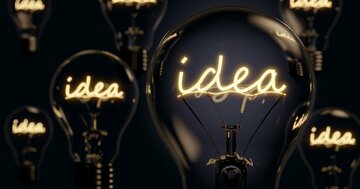価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ブレストの際は、
チームの組み方にも工夫を
次に、ブレストや議論が活性化しない、いいアイデアが出ない、という悩みについて考えていきましょう。この場合、問題点はどこにあるのでしょうか。
ひとつは、以前にも触れたように「正解を求めすぎる」というところにあるかもしれません。でも、他にもチームの組み方やブレストの進め方にも問題がありそうです。
ここでは、ブレインストーミングのそもそもの定義や説明は省きますが、多くの場合に、まずチームの組み方に問題があるケースが多いように感じます。
「部署内で来期の売上を上げるためのブレストをする」
「チーム内で新規事業のアイデアについて話し合う」
「うちの課の来年の方針についてアイデアを出し合う」
こういったブレストが、なかなかうまくいかない、とよく相談されます。
先述した通り、15人ほどの部署みんなで話し合いをしても、活発な議論は到底期待できません。せめて5人ずつの3チームくらいに分けてブレストをして、その後で、各チームごとにアイデアのシェアをするのがおすすめです。
そのときに大切なのが、チーム分けもアイデアを持って行うことです。
なんとなく、ランダムに決めるなどはいけません。なぜなら、「うまくいった」「いかなかった」は時の運になってしまい再現性がないためです。きっとその集団ごとに、いいアイデアが出てきやすくなるチーム分けがあるはずです。
では、チーム分けには、どんな仮説を持って臨めばいいでしょうか。
(1)いかにメンバーの心理的安全性を保てるか
まずは、心理的安全性が確保されていることが大事です。
たとえば、部署の上長を呼ぶことがマイナスに働くケースも多くあります。会議の主導権を持っていかれてしまったり、上長に評価されそうだと考えるアイデアだけを発言するとか、メンバーが萎縮したり、遠慮したりしてしまいます。
また、男性ばかりのチームに女性がひとりだけとか、年齢層の高いチームに若手ひとりだけというのも、違った視点が入ったり、少しだけ緊張感が生まれ、うまく働くケースもあります。しかし、萎縮したりするケースもあるでしょう。もちろん人や組織の雰囲気にもよりますが、いずれにしても、誰かの心理的安全性が保てない、というのはよくないわけです。
「みんなの心理的安全性」が確保されているか、ということを検証するためにも、このメンバー分けなら心理的安全性は確保される、という仮説を持ってチーム分けをしましょう。
(2)特性ごとにチームに分けるか、
多様性のあるチームに分けるか
チーム分けはくじ引きのような偶然性に任せるのではなく、できればリーダーが恣意的に分けることをおすすめします。チームの分け方に仮説を持って、どんなチーム分けが機能するのかを試していくのがいいと思います。
「特性ごとに分ける」というのは、若手チームとシニアチームに分けるとか、内勤チームと営業チームに分けるなどです。
この考え方のいいところは、「そうそう、それあるよね」とか、共感型で意見がどんどん出てくることです。アイデアをそれぞれのチームで発展させていくことにも向いています。
「多様性のあるチーム」というのは、先ほどの特性で言ったような年齢や職種などで分けるのではなく、できるだけいろいろな属性を持った人たちが交じるようにチームを組むようにすることです。
多様性のあるチーム分けの場合、共感が少なくアイデア出しが不活性化することがあります。そういうときは、「できるだけ自分の立場からだとこう見える、といったような意見を遠慮せずに出すようにしましょう」など、リーダーがセットアップしてあげると、議論も活発化していきます。
他にも、視点はあるように思います。チームでアイデアが出やすいようにするために、ぜひ仮説を持っていろいろと試してみてください。
(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)
株式会社Que 取締役
クリエイティブディレクター/コピーライター
1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。
2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。
2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。
2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。
2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。
受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。