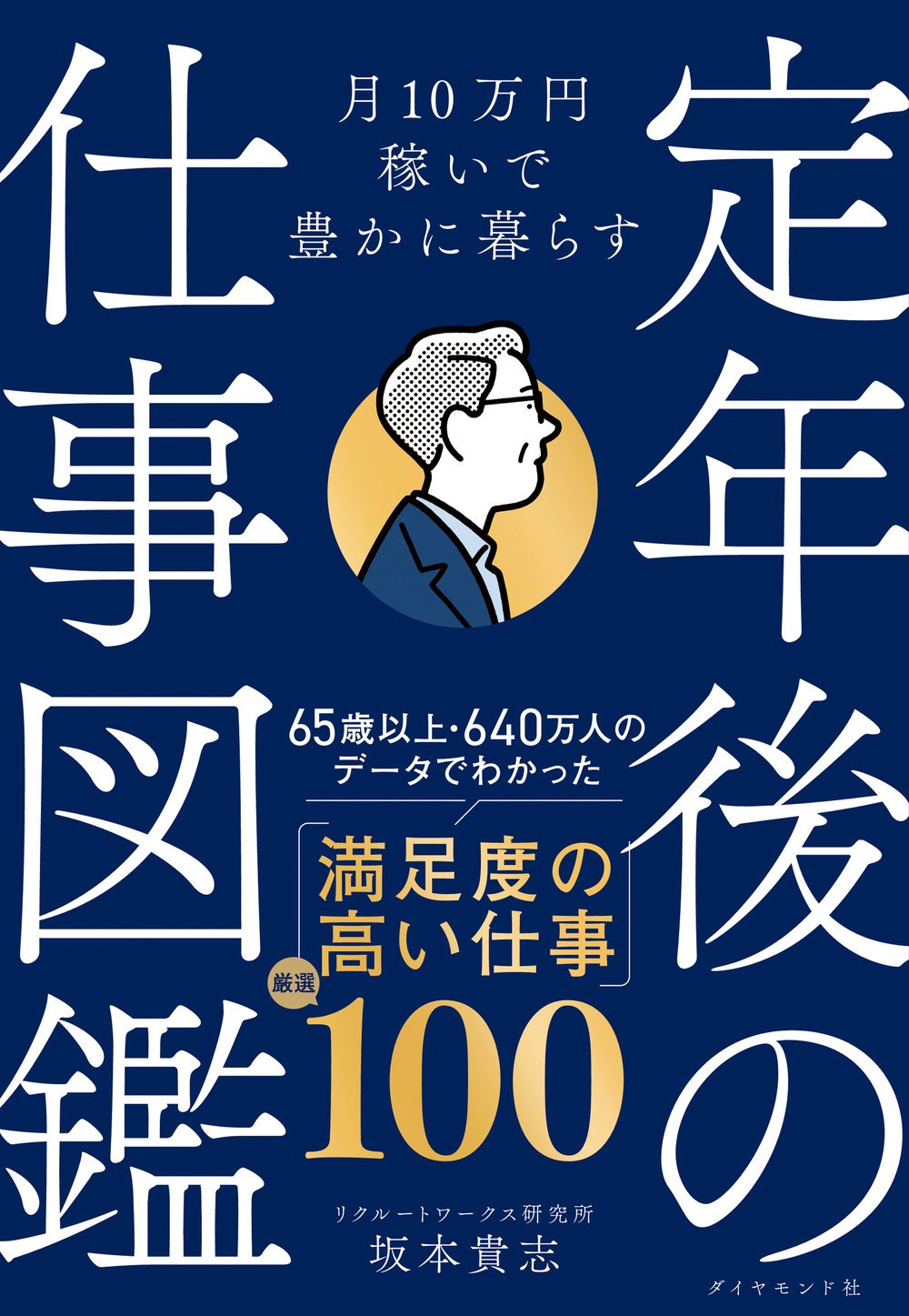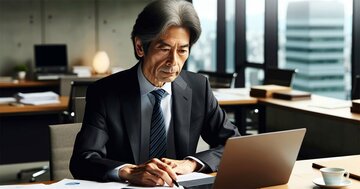「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。
定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。
※この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
60代半ばまでに「住宅ローンを完済」できたかが勝負
「定年後の支出」の中で特に重要ポイントとなるのが、住宅に関する費用だ。
「持ち家か賃貸か」の問題は必ずしもどちらかひとつに正解が定まるという性質の問題ではないものの、あくまで定年後の家計の「収支」という視点からみれば、持ち家に軍配が上がるだろう。60代半ばまでに持ち家のローンを完済し、住居費の支出を限りなく少ない状態にしておくことが望ましい。
住宅に関するデータを確認すると、70歳以上の92.4%が持ち家を取得しており(※1)、純貯蓄額の推移をみても、「住宅・土地のための負債」は40代で約1300万あったものが50代で643万まで減り、60代で163万まで減少している(※2)。
データからは、多くの人がしっかり働けるうちに住宅ローンの大半を返済する選択をしていることがわかる。
高齢期に住宅取得を前提に考える理由は、やはりフローの収入を確保しておきたいからだ。賃貸の場合は寿命が続く限り賃料が毎月発生してしまうことから、いざという時のために貯蓄を常に多く残しておく必要性が生じる。一方、持ち家の場合は人生における住居に関する支出が先に概ね確定できるため、将来の不確実性を減らすことができる。
もちろん借家にも仕事や家庭の都合に合わせて気軽に転居できるメリットがあり、長生きを想定したうえで十分なストックを蓄えることができれば問題ない。また子どもが小さいうちは通勤・通学に便利な立地の借家で暮らし、子育てを終えた後に老夫婦で暮らす小さな住居を取得するのも現実的な選択のひとつだ。
あるいは持ち家を取得済みであっても、世帯人数の減る定年後は広い家から小さな家に住み替えることも積極的に考えてよい。住居の問題は高齢期の家計に大きな影響を与える。住宅の状況に応じて、高齢期の働き方も考える必要があるだろう。
※1 総務省「家計調査」2024年、2人以上世帯
※2 総務省「家計調査」2023年