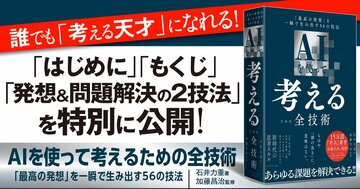「“悩む”だけの時間は無駄です」
最近、仕事で「考える」ことが増えていませんか? 新商品やサービスの企画。販売や宣伝の立案。マネジメント、採用、組織運営の戦略など。従来の方法が通用しなくなったいま、あらゆる仕事で「新しく考える」ことが求められます。でも、朝から晩まで考え続けた結果、何も答えを得られずに1日が終わる――そんな経験のある人が多いのでは。
「その悩み、一瞬で解決できます」。そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に発想や思考の研修をしてきた石井力重氏です。古今東西の思考法や発想法を駆使して仕事の悩みを解決してきた石井氏ですが、なんとAIを使えば誰でも素晴らしい発想ができると言います。そのノウハウをまとめたのが、書籍『AIを使って考えるための全技術』。この記事では同書から、「革新的な解決策を見つける方法」を紹介します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「普通のやり方」では通用しない課題を解決するには
AIは賢く使えば「問題解決」にも十分に役立てることができます。
その方法の1つが、技法「異質の取り入れ」。
そのプロンプトはこちらです。
〈課題や目的を記入〉
この問題の解決に、まったく異質な要素を7つあげ、それぞれを取り入れた案を考えてください。それにはどのような効果がありますか?
目の前にある課題や改善したい商品・サービスをAIが理解した上で、そこから距離のある「異質」なコト・モノを7つピックアップ。そこから新しいアイデアを導き出してもらいます。
課題はあるけど、通りいっぺんな方法では壁を突破できないときや、イノベーティブなアイデアを探したいときに使ってください。1人でもチームでも使える技法です。
プロンプトの最後で「効果」を聞いているのも、この技法の特徴。異質なコト・モノの組み合わせだけを問うと、効果がわからないアイデアを生成しがちな傾向があるからです。AI自身に効果まで答えさせるプロンプトにすることで、有用性、効果性を考慮したアイデアを生成してくれるようになりました。
「書類提出」を徹底させるアイデアを考えてみよう
イノベーションを必要とする課題はいろいろありますが、いわゆるまっとうな方法では解決・解消にいたらないお題に技法「異質の取り入れ」は適しているでしょう。
たとえば、「属人的」な問題。
どの会社にも、事務作業が苦手で後回しにしちゃう人がいます。普通の呼びかけでは効果がなくて、注意する方が疲れてしまう。地味なお題かもしれませんが、こんなことにも活用いただける例として、実践してみましょう。
〈私は企業で経理をしています。社内の請求書提出の締め切りが守られないことに悩んでいます〉
この問題の解決に、まったく異質な要素を7つあげ、それぞれを取り入れた案を考えてください。それにはどのような効果がありますか?
こうした社内ルールは、ついつい厳罰化の方向にアイデアが寄りがちですが、おそらくイタチごっこですよね……。この問題、AIはどうクリエイティブに解決してくれるのでしょうか。
社内の請求書提出の締め切りが守られない問題を解決するために、まったく異質な要素を取り入れた7つの案を考えてみましょう。それぞれの要素がどのような効果をもたらすかも検討します。
1. ゲーミフィケーション(遊戯化)
請求書の提出をゲームのように楽しくする。提出期限を守った従業員にはポイントを付与し、一定期間ごとに最もポイントの高い従業員に報酬を与える。
効果:モチベーションの向上と競争心を刺激し、期限を守ることの重要性を楽しく学べる。
2. ビジュアルトラッキングシステム
進捗状況をビジュアルで表示するシステムを導入。請求書の提出状況を一目で把握できるダッシュボードを作成する。
効果:進捗の可視化により、提出遅延の原因を迅速に特定し、対処することができる。
3. マインドフルネスセッション
定期的にマインドフルネスやストレス管理のワークショップを開催し、従業員の精神的なウェルビーイングをサポートする。
効果:ストレス軽減により、仕事の効率が上がり、期限内に請求書を提出することが容易になる。
4. クロスファンクショナルチーム
経理部門と他の部門の間でクロスファンクショナルチームを組み、相互理解とコミュニケーションを深める。
効果:部門間の連携強化により、請求書提出のプロセスがスムーズになり、締め切り遵守が促進される。
5. バーチャルリアリティ(VR)トレーニング
VRを活用して、請求書提出のプロセスを体験するトレーニングを実施する。
効果:従業員が仮想環境で実践的な経験を積むことで、プロセスの理解を深め、エラーを減らすことができる。
6. フレキシブルワークスケジュール
従業員に柔軟な勤務時間を提供し、個々の生活リズムに合わせた労働を可能にする。
効果:ワークライフバランスの改善により、従業員の満足度と生産性が向上し、期限内提出へのコミットメントが強化される。
7. 人工知能(AI)アシスタント
AIを用いて請求書の提出プロセスを自動化し、提出締め切りが近づいていることを従業員にリマインドする。
効果:自動化により手続きの負担が軽減され、従業員が締め切りを忘れるリスクが低減する。
これらの案は、従業員のモチベーション向上、プロセスの透明性強化、生産性の促進、ストレスの軽減、部門間の連携促進、新技術の活用による効率化を目指しています。それぞれの方法が異なるアプローチを提供し、請求書提出の締め切りが守られるような環境を構築することが期待されます。
切り口が7つ登場しました。どの切り口を深めていくかは、あなた次第。これが、AIと人が共に考える「人機共想」です。
個人的には「マインドフルネス×伝票」なんて組み合わせに強く惹かれるところがありますが、それはさておき。
意外な要素の組み合わせから生み出されるアイデアはイノベーティブ度が高くなりやすい半面、当初は受け入れにくかったりするものです。かすかな可能性をじっくり見極める姿勢でAIの回答を読んで、従来にない解決策や企画の芽となるアイデアを発見していくことをおすすめします。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、こういったAIを使って問題解決するための56の方法を紹介しています)