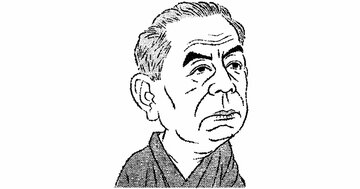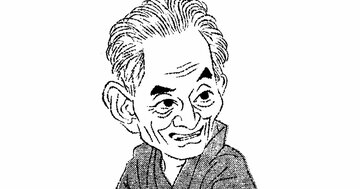【自己投資】なぜ今、仕事ができる人ほど志賀直哉を読むのか? その納得の理由
文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
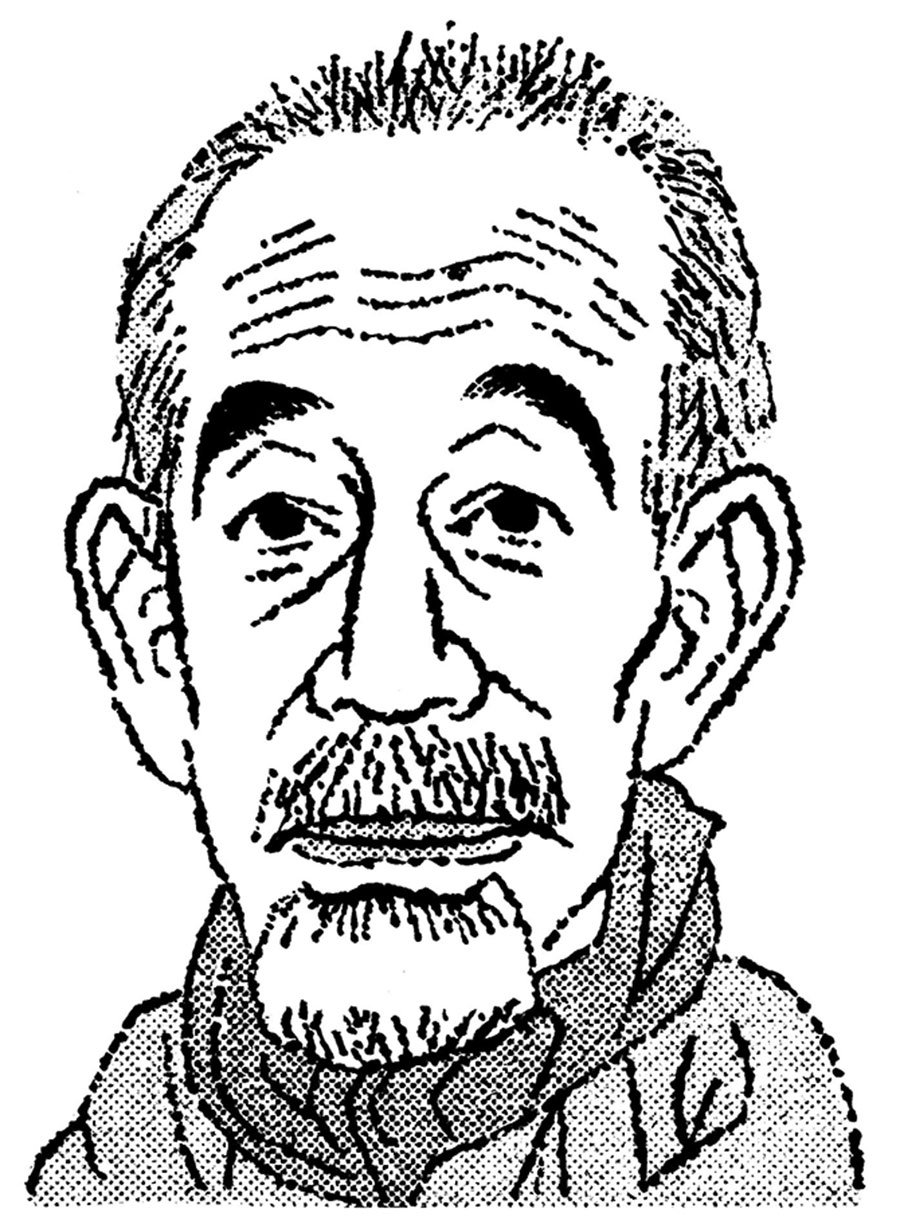 イラスト:塩井浩平
イラスト:塩井浩平
「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち
志賀直哉のおすすめ著作①
生と死を見つめた私小説の傑作
◯『城の崎にて』(『小僧の神様・城の崎にて』新潮文庫に収録)
自身のけが療養中に滞在した城崎温泉を舞台にした短編小説。日本の私小説の金字塔的作品です。なお、直哉が泊まったのは兵庫県豊岡市城崎町にある「三木屋」という宿で、国登録有形文化財になっています。現在も宿泊可能なので、『城の崎にて』を携えて訪れてみるのもいいかもしれません。
志賀直哉のおすすめ著作②
魂の成長を描く、唯一の長編
◯『暗夜行路』(新潮文庫)
「短編小説の名手」と呼ばれた直哉が唯一書いた長編小説。主人公・時任謙作は単身、旅に出て、尾道で暮らすようになります。そして、幼少期のトラウマや家族との葛藤を経て、自身の傲慢さや執着を捨て去り、成長する姿を描いています。注目は、鳥取県にある大山に登る有名なシーン。大自然と一体化していく夜明けの景色を、ぜひ一度読んでみてもらいたいです。
「私小説」は日本文学ならではのジャンル?
明治維新で「近代小説」と呼ばれる西洋の文学が、日本にも入るようになりました。近代小説は17~18世紀のヨーロッパで、市民社会の成熟とともに、自分たちの身近な生活や社会問題を描く新しい表現方法として登場しました。
これに対して「私小説」は、作者自身の経験や感情をそのまま作品に反映させるジャンルで、その代表的な作家が直哉です。西洋の小説では、作者と作中人物の人格が分かれているのが一般的でしたが、日本では「作中人物=作者」という自伝的な手法が発展しました。
こうして「私小説」は、日本独自の小説ジャンルとして確立していったのです。