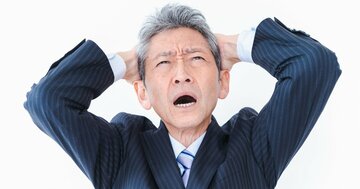銀行預金とはワケが違う! 仮想通貨を持つ親が亡くなる前に子が聞くべき「ひと言」
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!【親は】子に迷惑をかけたくなければ、【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
デジタル時代の新たな課題
“見えない資産”の相続
相続の手続きで、今後困る人が増えると考えられるのが、仮想通貨(暗号資産)の相続です。
暗号資産は法定通貨ではありませんが、インターネット上で決済手段として使われており、日本円との交換も可能なため、財産的な価値をもちます。
そのため、被相続人が暗号資産をもったまま亡くなると、遺産分割協議や名義変更、相続税申告などにも関わってきます。
家族が知らない「秘密の資産」が招く混乱
存在に気づいても、引き出すのは至難の業
暗号資産の存在を家族に知らせないまま亡くなると、確実に相続の場面で困ります。
暗号資産の存在を把握できるとは限らず、できたとしても相続手続きは一筋縄ではいきません。銀行や証券会社なら、戸籍謄本や遺産分割協議書などを持参すれば手続きをしてもらえますが、暗号資産はそうはいかないからです。
まずは取引所のドアを叩くことから
亡くなった家族が暗号資産をもっていたことがわかったら、まずは取引所に連絡して相続が起きたことを伝えましょう。
たとえば、日本の大手暗号資産交換業者「ビットフライヤー」の場合、問い合わせフォームから被相続人と代表相続人の情報を連絡すると、その後の手続きの案内を届けてくれます。
銀行手続きとは異なる必要書類の壁
相続税申告の鍵を握る「残高証明書」
必要書類は取引状況などによって変わりますが、基本的には銀行の名義変更と同様に戸籍関係や印鑑証明書などの書類が求められます。
この連絡のときに合わせてやっておきたいのが、「残高証明書」の発行です。相続の連絡をすれば自動的に発行してもらえるとは限らないので、最初から依頼しておくのが無難です。
「日本円でいくら?」そのひと言が後々を楽にする
最難関! オフラインに眠る「コールドウォレット」
さらには相続開始日時点で、日本円に換算していくらなのかを書いてもらっておくと、相続税申告のときなどに役立ちます。
暗号資産のなかには、インターネットに接続されていないハードウェアなどで情報が管理されているものがあり、「コールドウォレット」と呼ばれています。
故人しか知らない「鍵」がなければ、資産は永遠に凍結
絶対に捨てないで! 故人のスマホやパソコン
コールドウォレットの場合、取引所で管理されているわけではないので、所有している暗号資産にアクセスするための情報を引き継いでおかないと、相続人であっても使うことはできません。
情報が残っている可能性のあるスマホやパソコンを処分すると、永遠に換金できなくなってしまう恐れもあります。
家族をトラブルから守る、生前のひと工夫
あなたの資産、本当に「遺産」になりますか?
このような相続後のトラブルを避けるには、生前に暗号資産を換金しておくか、必要な情報にアクセスできるように相続人に説明しておくなどの工夫が必要です。
暗号資産をもつこと自体を否定するつもりはありませんが、相続のときに家族が困るリスクが高いことは認識しておきましょう。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)