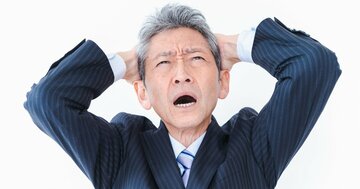相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/8/-/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.png) Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
生前の相続税対策は何ができる?
![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/f/6/550/img_7cc7e22bf5d82608913d21cbac49351b525581.jpg) 『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ
『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ
3つ目の相続税対策「生前贈与」
――なぜ優先度は3番目?
無知 3つ目の相続税対策が、「生前贈与」ですね。優先度が3番目になるのは、なぜですか?
前田 注意点がいろいろとあるからですが、まずは生前贈与のメリットから説明しておきましょう。
生前贈与とは?
「あげます」「もらいます」で成立する契約
前田 そもそも生前贈与とは、ある財産を無償で相手方に贈ると意思表示をして、相手方がこれを承諾することによって成立する民法上の契約の一種です。簡単にいえば、「あげます」「もらいます」と
いう合意があれば、生前贈与ができるわけです。
なぜ節税になる?
相続税の課税対象を“直接”減らせる
前田 生前贈与が相続税対策になるのは、相続税の課税対象となる財産を直接減らせるからです。単純にいえば、生前に子どもに累計1000万円を贈与しておけば、相続税がかかる財産の金額を1000万円
減らせるので、ダイレクトに節税につながります。
落とし穴:贈与税に注意!
やり方を間違えると逆効果に
国税 ただ、生前贈与をすると、もらった人に贈与税がかかりますよね。
前田 そうです。贈与税は税率が高いので、やり方を間違えると、相続税の節税が無意味になるほど多くの贈与税を納めることになってしまいます。
無知 じゃあ、意味がないじゃないですか!?
カギは「非課税枠」の活用!
暦年課税制度を知ろう
前田 そこで意識したいのが、「贈与税のかからない範囲で生前贈与をする」ということなんです。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの課税方法があります。相続時精算課税制度はのちほど説明するとして、まずは暦年課税制度について説明しましょう。
年間110万円まで非課税!
「暦年課税制度」の基礎控除
前田 暦年課税制度で贈与税を計算する場合、年間110万円の基礎控除があります。つまり、その人が1年間で受けた贈与が110万円以内であれば、贈与税がかからないということです。この場合、贈
与税の申告自体する必要がないので、手間もかかりません。ちなみに、平成12(2000)年までは年間60万円でしたが、平成13(2001)年から現在まで年間110万円で継続しています。
10年×3人で3300万円!
コツコツ型でも大きな節税効果に
国税 110万円というと、それほど大きな影響はなさそうに思えますが、やり方次第ですよね。
前田 はい。年間110万円ですから、毎年10年間続ければ1100万円を贈与税なしで生前贈与できます。もし、子ども3人に10年かけて110万円ずつ贈与するなら、合計3300万円を贈与でき、相続税のかかる財産を大幅に減らせます。
国税 それだけ課税財産の金額が減れば、かなりの節税効果が見込めますね。