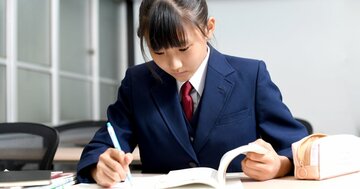写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「ワンランク落とす」のではなく、「子どもに合う6年間を選ぶ」という発想が中堅校にはある。先生の面倒見や校舎の充実ぶり、スマホ指導の丁寧さなど、実際に見て初めて気づく魅力は多い。数字や偏差値だけでは分からない“わが子に合う環境”を探すことが、これからの学校選びの新しい基準になる。中堅校の魅力に迫る連載第23回。(進学塾VAMOS代表 富永雄輔、構成/ライター 奥田由意)
近年のトレンド「中堅校人気」
中堅校が近年人気を集めています。特に地方から東京に出てきた家庭や第一子が中学受験をする家庭は、中堅校の充実ぶりに驚かれるでしょう。「こんなにすごい学校なのか」と説明会に足を運んで初めて気づく人も多いようです。
中堅校の長所はなんといってもひとりひとりの子に合わせた教育の面倒見のよさです。また、運動場の設備や校舎の充実ぶりを見るだけでも、ここに子どもを預けたいと思うかもしれません。
ただし、多くの保護者は、10年以上前の情報に基づいた中堅校のイメージを持っているのではないかと思います。現在の中堅校は大きく変わっています。
例えば、本郷、洗足、鴎友、吉祥女子といった名だたる難関校も、15〜20年前は今よりも入りやすい学校でした。これらの学校は、子どもをしっかり育て、丁寧な教育をした結果、難関校へと成長しています。
今、親の情報感度が高まり、こうした中堅校の良さに気づく保護者が増えています。たとえば、近年の教育環境で大きな違いが出るのは、スマートフォンとの付き合い方です。中堅校では、スマホの使い方ひとつとっても上位校とは全然違います。
上位校ではスマホに関しては「自己責任」で使用するようにとだけ注意して、生徒の使い方には一切関知しない傾向があるのに対し、中堅校では適切な指導をしてくれます。詐欺サイトやアダルトサイト、出会い系サイトに近づかないといった基本的なルールはむろんのこと、その一歩上の「付き合い方」や「使いこなし方」まで教えてくれるのです。
例えば、ある上位校では、スマホの使用が前提となっており、ラインのグループや学校ドライブでの資料共有など、現代社会に適応したシステムを導入しています。授業中に音が出ると没収されるなどといったルールはありますが、基本的に生徒には「大人」としての自己管理を求めます。
一方で多くの中堅校では、より管理された環境で、スマホとの適切な付き合い方を教えてくれます。こうした面からも、お子さんのタイプに合わせて学校を選ぶことの大切さが見て取れると思います。