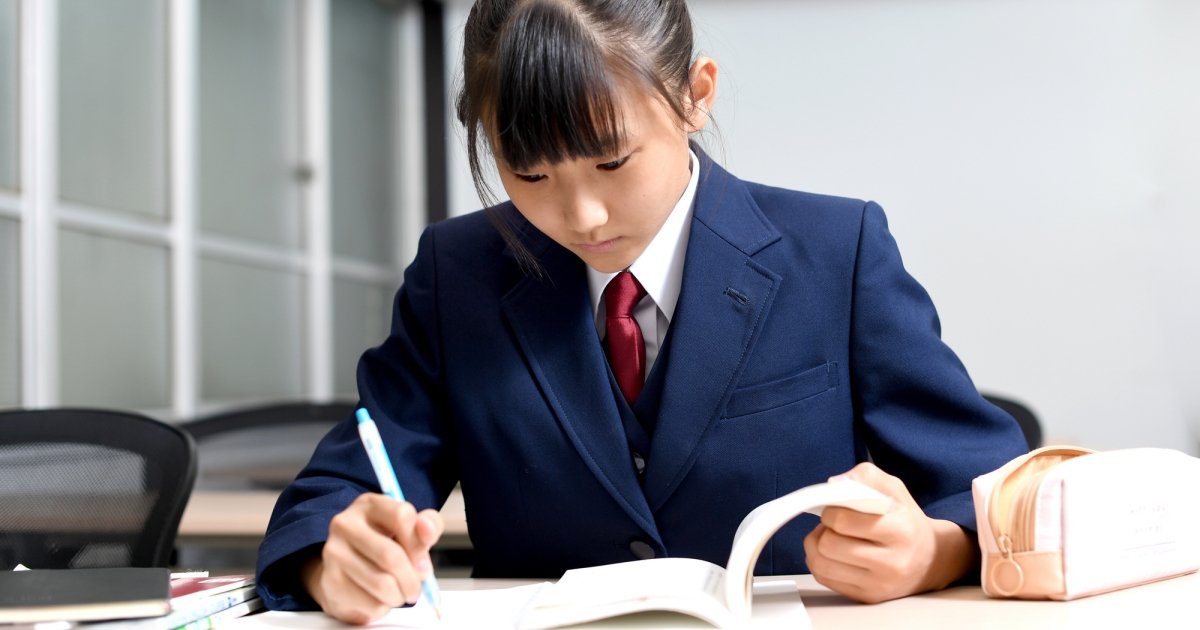 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
中学受験の世界で「中堅校」の人気がかつてなく高まっている。本郷や攻玉社、洗足、鴎友、吉祥女子といった学校が歩んできた道を思い出す人も多いだろう。では、いま現在の「中堅校」とはどんな学校なのか。入試の特徴のほか、どこに魅力があり、なぜ保護者の心をとらえているのか――くわしく解説する連載第22回。(進学塾VAMOS代表 富永雄輔、構成/ライター 奥田由意)
中堅校はなぜ人気なのか?
“努力で入れる”という前提
近年いわゆる「中堅校」の人気がこれまでになく高まっています。正確な定義はさまざまありますが、多くの保護者が中堅校を選ぶ理由として最も大きいのは「努力すれば入れる可能性が高い学校」である点でしょう。
中堅校の魅力は、適切な努力をすれば、かけた時間や労力が結果に反映されやすい学校だということです。とはいえ、「中堅校だから入試問題が簡単で、入りやすい」というわけではありません。
近年の中堅校の入試難易度は確実に上がっています。ただ、その難しさの質が上位校とは異なります。今
回は中堅校が難化した背景となぜそこまで人気なのかを解説していきます。
中堅校がなぜ人気なのか。最近の上位校の入試問題を見ると、小手先の対策では手も足も出ないような思考力を問う問題が極端に増えています。
例えば渋渋(渋谷教育学園渋谷中学校)の国語の問題などは、保護者自身が「こんなに難しい問題を12歳の子どもが解けたとして、そのことに意味があるのだろうか」と疑問に思うほど難解です。こうした思考力を試す問題を楽しめない子どもを、無理して上位校に入れても意味がないという判断があるのは当然のことです。
同じ偏差値でも、苦行の末の合格と、楽しく問題を解きながら到達した合格では子どもにとっての意味が違います。







