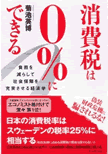癌の母、脳梗塞の後遺症に悩む父を介護し、看取る。自らの体験による、老いた両親と共に生きた『永久の別れ』までの日々を綴った本書の読みどころを、著者・岡山徹氏が紹介します。
 |
| ダイヤモンド社刊 1500円(税別) |
30年近く離れて暮らしていた両親が、ある日、「夏休みに遊びに行く」と言って、我が家にやってきた。その「夏休み」はやがて、「冬休み」になり、「春休み」となり、2人はとうとう何年も我が家に住み着いてしまった。
なにせ、我が家は4部屋もあり、主に使っているのは1部屋で、他はろくに使っていなかったから、ただでさえ、東京で再び暮らしたがっていた母にとっては、目の前にニンジンがぶら下がっているようなものだった。若者の街、吉祥寺も近いし、交通の便はよく、東京の利便性を存分に味わえる場所にあったから、母にとってなじみのない、茨城の田舎よりもはるかに暮らしやすく、こんな便利なところに息子1人で暮らさせるわけにはいかない、わたしたちも暮らさなければと思うのは人情だ。
やもめ暮らしの食卓に、なつかしい母の手料理の花が咲いた。いろいろな事情もあったけれど、幸せな日々が3年間ほど続いたそんなある日、母が胃の激痛に襲われた。ちょうど正月の出来事だった。
調べていくうちに、医者に胆管癌だと宣告されて、目の前が真っ暗になった。日本の母親のほとんどがそうであるように、ご多分にもれず苦労ばかりしてきた母は、酒もタバコもやらず、たまに好きな日本酒を一口飲んでは頬を染めるぐらいで、料理、炊事、洗濯が好きな典型的な専業主婦だった。かつての日本の母親の原型をすべて兼ね備えた、良妻賢母の典型のような人だった。人に尽くすのが好きという今では考えられないような主婦像が、かつてはあったのである。もちろん、ミセス・パーフェクトかというと、そんなことはなく、かなり気の短いところもあったし、頑固なところは天下一品で、一度言い出したら、てこでも動かないのは、空襲のさ中、爆弾が降りそそぐ防空壕の中で、夫婦げんかをして水を張ったバケツに顔をつっこんで死のうとしたエピソードでも分かっていただけると思う。
そんな母親が癌にかかり、死の宣告と受け取った僕の懊悩が始まった。やっと父と3人で幸せな日々を送り、これからはまがりなりにも親孝行ができるぞと張り切っていた頃の出来事だった。