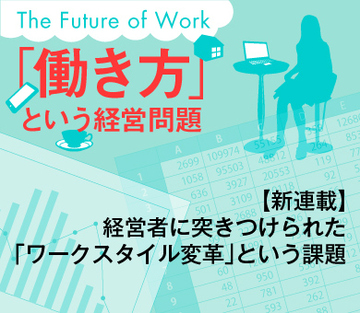ワークスタイル変革に対する
誤った認識
製造業の生産現場における改善活動の進展と比べて、ナレッジワーカーの生産性の低さが日本の課題であるとの論調をよく聞く。
確かに、長く不毛な会議、氾濫する電子メール、分断された稟議・承認プロセスなど、ナレッジワーカーの業務効率を阻害する問題は多くの企業が抱えているといえる。そのため、多くの企業が業務改革やワークスタイル変革に取り組む際に、ナレッジワーカーを第一の対象と考える傾向にある。
一方で、情報化の手が行き届いていない現場業務を多数抱える企業は少なくない。小売業、サービス業、運輸業、建設業、医療・福祉業、外食・ホテル業などは人手による作業が多い業種であり、それ以外の業種においても設備保全、保守サポート、倉庫・輸配送、顧客対応などパソコンに頼らない業務に従事するスタッフを多く抱えている。
また、多拠点を展開する事業や、場所を移動して作業を行うスタッフを多く擁する事業形態も存在する。こうした現場業務の情報化やワークスタイル変革は遅々として進んでいないのが実態といえる。
今、改めて問われる現場力
実際には、ナレッジワーカーの生産性よりも、こうしたビジネスの最前線である現場の対応力向上が急務であり、これに対する改善の効果が大きいという企業が多いのではないだろうか。多くの場合、本部スタッフなどのナレッジワーカーよりも現場スタッフのほうが人数が多く、改善の効果は大きいはずである。
また、現場の対応力はビジネスに直接影響する。『現場力を鍛える』(遠藤功著、東洋経済新報社)では、「オペレーションというと、単に日常業務をこなすだけの戦略性の低い企業活動と捉えられがちであるが、現実にはオペレーションの優劣が業績を大きく左右している」「そもそも、戦略を正しくやりつづけ、結果を出す主体は経営者でもなければ、戦略スタッフでもない。その実行主体は企業のオペレーションを担う『現場』である」と述べている。