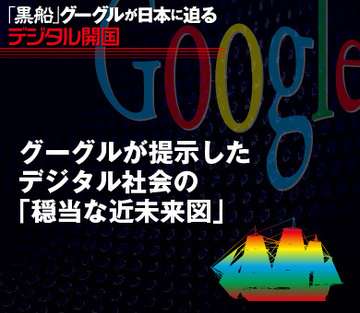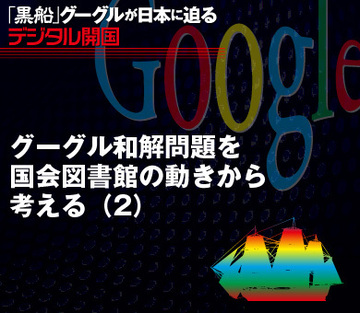グーグルから「独立した」版権登録機関
今回の和解案において、重要な役割を果たすプレーヤーとして版権登録機関(レジストリ)が設立されることになります。この版権登録機関は、ニューヨークに設置され、グーグルがその設立費用と初期運営コストとして3450万ドルを拠出しますが、運営は著者と出版社の代表者がそれぞれ同数参加する理事会によって行われます。つまり権利者によって運営され、グーグルからは独立した存在ということです。
この版権登録機関の存在を検討することは、実はこれからの日本の出版界を考える上で極めて重要な問題を浮かび上がらせることになります。著者の原稿は出版社によって本となり書店を通して読者に届けられるとともに、図書館の蔵書となって書店での流通が終わった後も本へのアクセスが保証されます。この著者、出版社、図書館、読者の関係がデジタルの時代でどう変わるのか、変わらざるを得ないのか。この問題を考えるてがかりが、版権登録機関の検討によって浮き彫りにされてくるのです。
ここまで和解に基づく権利者の利益について説明してきましたが、著者や出版社の権利行使や利益の分配請求はすべて版権登録機関に対して行うこととされています。逆に言えば、権利行使や利益分配は、権利者自身が版権登録機関に対して自らの情報を提供しない限り実現できないということです。一般的に、著作権などの知財の権利を集めて利用しようとする場合、まず利用者が権利の所在や状況を確認することが大きな手間となります。しかし、今回はグーグルによるデジタル化が進行しており、また利益の分配も予定され、解決一時金の支払いも約束されています。デジタル化を止めること、利用の範囲を限定すること、一時金を受けとること、それらのいずれも権利者が自ら版権登録機関に申し出ることによってのみ実現します。登録のインセンティブが存在しているということです。
この結果、版権登録機関は労せずして700万冊に及ぶ書籍の権利情報を入手することができることになります。この機関の存在をどう評価すればよいのでしょうか。先日来日した原告側弁護士は、この版権登録機関について「権利者のために、グーグルが合意内容に従って正しく著作物の利用を行い、適正な支払いを行うように監視するための機構」という説明をしています。つまり、和解における合意事項の枠内で権利者を代表し、グーグルの行動を監視するということです。