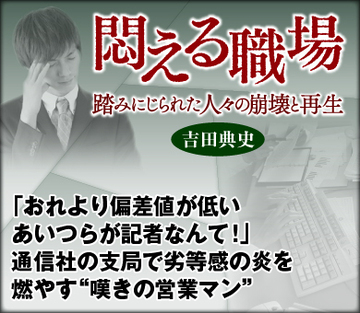編集長は、夜間部を卒業したことも、コネクションで入社したことも社外の者には隠している。それは、社内の数人しか知らないことだ
編集長は、夜間部を卒業したことも、コネクションで入社したことも社外の者には隠している。それは、社内の数人しか知らないことだ
今回は、ある主要出版社の編集長(部長)を紹介しよう。50歳を越え、定年が見えつつあるが、依然として「野心」が消えない。二十数年前から引きずる劣等感や、会社で昇格が遅れているコンプレックスなどが重なり、極度に屈折している。
この男性の生き様から、読者諸氏は何を感じるだろうか。意識の高い20~40代のビジネスパーソンは、こんなレベルの人材でありながら、役職に就いて、怠慢なことをしているなんて、理解ができないと思うのではないだろうか。
しかし、これが現実なのだ。この編集長のような人は、企業社会で決して少数ではない。むしろ相当な数に上る。ところが一部のメディアで、「企業ではリストラなどで人材の淘汰が進んでおり、実力主義の職場になりつつある」と唱える。果たして、そんなことが本当に言えるのだろうか。
アベノミクスが始まって以降、ここ数年にわたる好景気で、むしろ世間では、企業における人材のセレクトについて、真摯に議論する論調も消えつつあるように思える。そんな世の中の空気に一石を投じるためにも、今回のテーマを取り上げてみた。
母校に響く耳障りなダミ声
劣等感の塊のような編集長
それは、“だみ声”で知られる中小企業の名物社長の取材を終えた後だった。その男の歩くリズムが軽快になる。50歳を越えているとは、思えないほどだ。数メートル後ろを歩いていた40代半ばのフリーライターの甲賀との距離が、瞬く間に開く。その差は10メートルほどになっていた。
右手に見えてきたのが、そびえ立つ大学の講堂だった。そばにある学生食堂に、2人は入った。甲賀が汗をハンカチで拭きながら椅子に座ると、男はつぶやく。その声は、普段よりもはるかに大きくなっていた。顔の表情も違う。いつもは眉間にしわを寄せているが、今日は笑顔だった。
「ここは、母校です……」
誰も聞いていないのに、学生時代のことを話し始めた。周囲の学生を見る目は優しい。いつもは職場で、20~30代の編集者を抑えつけるような高圧的な雰囲気を醸し出す。