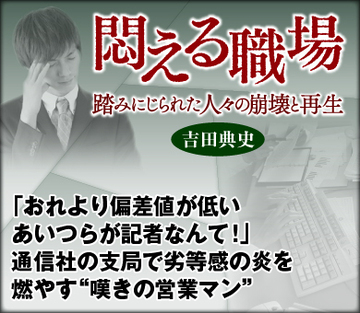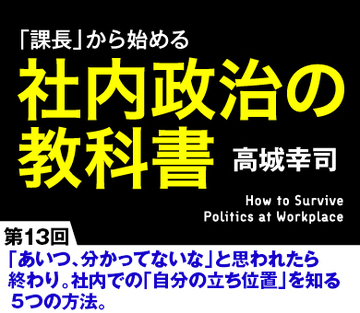>>(上)より続く
「著者」の氏名をフルネームで堂々と語る、力の入れ方だった。「著者」がいながら、なぜ編集者が書くのかは、一部で「代筆」が行なわれているという業界の実情を知らない人には、理解しがたいだろう。本来は隠すべきことかもしれないが、編集長はひるまなかった。それにしても、1冊200ページの本を書き終えるのに「4日」や「6日」は、ホラの吹き過ぎである。それほどに劣等感が強いのだろう。
「書き上げた」というのも、胡散臭い。正確には、著者やライターが書き上げたものを多少、手直しをしたに過ぎない。「4日」や「6日」でできることは、たかが知れている。
異様に膨張するコンプレックス
そして、誰もいなくなった――。
この編集長に限らないが、一部の編集者には「書くこと」に根強いコンプレックスや、それとは裏腹に憧れの思いがある。特にこの編集長のように、若かりし頃、全国紙や通信社の記者になりたかった者は、驚くほどに「書くこと」に執着する。
しかし、出版社の編集者の「書く力」が、通信社や全国紙の記者職のレベルになることは難しい。そんな人材育成のノウハウはなく、体制や環境も整っていない。たとえ記者がいたとしても、それは出版社の「記者」であり、全国紙や通信社の記者との間には、取材力や執筆力において、克服しがたい差がある。
だからこそ、劣等感は一層屈折したものになる。ましてや、この編集長のように昇格で遅れをとり、落ちこぼれ寸前になると、コンプレックスは異様なまでに膨れ上がる。
編集長は食堂で酔っぱらいのように話し続ける。「あの人の本は、実は俺が書いた。5日くらいで……。みんなに言わないでね……」
いつしか、隣の学生たちはいなくなっていた。
こんなレベルでありながら、現在の出版社で、編集長という部長級の社員になることができたのはなぜか……。それは、他になり手がいないからだ。